コラム詳細
2024/01/15
autorenew2026/01/06
半数程度が働きながら障害年金を受給できる!受給が難しいケース2つ
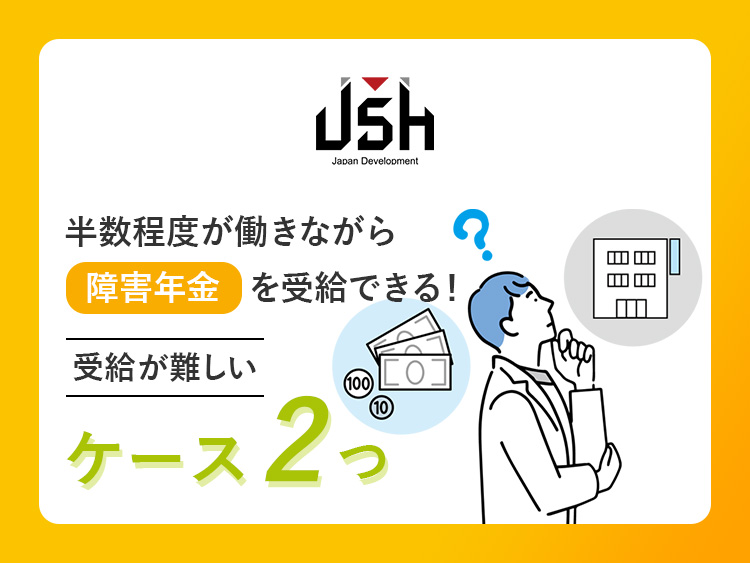
「働きながらでも障害年金は受給できるの?今後仕事をしようか迷っている」
「働くと障害年金受給が停止するって本当か?なぜ受給が停止するの?」
現在障害年金を受給している方においては、仕事を始めると障害年金の受給が停止してしまうのか気になるところですよね。
結論から言うと障害年金の受給は障がいがある方の状態により個別に認定審査をするため、一概に受給が継続できるとは言えません。しかしながら、2019年時点においては、障害年金受給者の約半数が仕事をしている状況です。
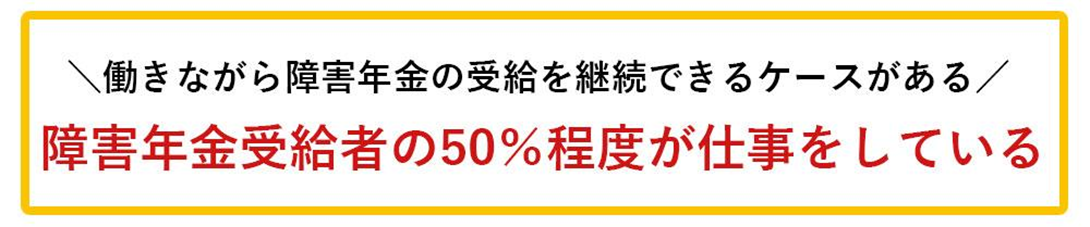
働きながら障害年金を受給するときに、停止となり得る代表的なケースには次の2つがあります。とくに、仕事をすることで障がいが軽くなったと捉えられてしまうと、受給額の減少や受給停止につながる可能性があります。
| 働きながら障害年金を受給するときに停止になり得るケース |
| ・障がいが軽くなったと判断された場合 ・20歳前傷病による障害基礎年金の場合 |
働きながら障害年金の受給を継続するには、あらかじめリスクを理解して慎重に検討することが大切です。
そこで、この記事では働きながら障害年金を受給できる理由や根拠、働きながら障害年金を受給するときに停止になり得るケースなどをまとめて解説していきます。後半では、少しでも受給できる可能性を高める方法にも触れているので必見です。
| この記事のポイント |
| ●障害年金は働きながらでも受給できるのかわかる ●働きながら障害年金を受給するときに停止になり得るケースがわかる ●働きながら障害年金を受給したいときに事前に知っておきたいポイントがわかる |
仕事を理由に障害年金が一度停止すると、再開が難しくなる可能性があります。適切な判断をするためにも、ぜひ参考にしてみてください。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
【目次】
1.障害年金は働きながら半数程度が受給できている
2.働きながら障害年金を受給するときに受給停止になり得る2つのケース
3.働きながら障害年金を受給したい場合は慎重に判断するべき
4.働きながら障害年金を受給したいときに知っておきたいポイント
5.働きながら障害年金を受給するときのQ&A
6.まとめ
1.障害年金は働きながら半数程度が受給できている

障害年金は働きながらでも、半数程度の障がい者が受給できている状態です。
| 障がいの種類 | 障害年金受給者の就労率 |
| 身体障がい | 48% |
| 知的障がい | 58.6% |
| 精神障がい | 34.8% |
※障害年金受給者(20~59歳)のデータ
参考:厚生労働省「障害年金制度」
10年前の2009年のデータと比較すると、どの種類の障がいも働きながら障害年金を受給している方が増えています。
| 障がいの種類 | 2009年の障害年金受給者の就労率 | 2019年の障害年金受給者の就労率 |
| 身体障がい | 38.1% | 48% |
| 知的障がい | 47.9% | 58.6% |
| 精神障がい | 18.6% | 34.8% |
※障害年金受給者(20~59歳)のデータ
参考:厚生労働省「障害年金制度」
働きながら障害年金を受給している障がい者が仕事で得る年間収入は「0~50万円」が多く、障害年金以外に一定の収入を得ていることが分かります。
| 働いている障害年金受給者の本人の仕事による年収 | |
| 0~50万円 | 46.9% |
| 50~100万円 | 17.4% |
| 100~150万円 | 12.0% |
| 150~200万円 | 7.0% |
| 200~300万円 | 6.3% |
| 300~400万円 | 3.8% |
※等級・国民年金・厚生年金の平均値
参考:厚生労働省「障害年金制度」
1-1.障害年金の受給条件に就労の有無は含まれていない
働きながらでも障害年金を受給できるのは、障害年金の受給条件に就労の有無が含まれていないためです。下記は公表されている障害年金の受給条件ですが「就労をしていない」などの記載はありません。
| 年金の種類 | 受給条件 |
| 障害基礎年金 自営業の方・初診日が20歳前の方など |
(1)初診日に国民年金保険加入期間・20歳前の期間などに該当する (2)初診日の前日までに保険料の納付要件を満たしている (3)障がい認定日または20歳に達したときに障がいの状態が1級~2級に該当している |
| 障害厚生年金 初診日に厚生年金保険に加入していた方 |
(1)厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある (2)初診日の前日までに保険料の納付要件を満たしている (3)障がい認定日に障がいの状態が1級~3級に該当している |
ただし、障害年金のそもそもの定義は「病気やけがで生活や仕事などが制限される場合に受け取ることができる年金」です。障害年金の受給基準を見ても労働の有無は問われないものの、仕事や日常生活に何らかの制限があることを基準としていることが分かります。
| 等級 | 受給基準 |
| 1級 | 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできない状態 身の周りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)・入院や在宅介護を必要とし活動の範囲がベッドの周辺に限られる方 |
| 2級 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない状態 家庭内で軽食を作るなど軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)・入院や在宅で活動の範囲が病院内・家屋内に限定される方 |
| 3級 | 労働が著しい制限を受けるまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする状態 日常生活にはほとんど支障はないが労働には制限がある方 |
※障がい者手帳の等級と障害年金の等級は異なります
参考:日本年金機構「障害年金ガイド」
このように見てみると、障害年金の受給条件に仕事の有無は含まれないものの「仕事ができる状態であることと障害年金の受給は無関係とは言い切れない」でしょう。障害年金の受給は障がいの状態や日常生活、仕事への影響などを障がい認定基準と照らし合わせて総合的に判断しているので、慎重に検討する必要があります。
1-2.有期認定の場合は定期的に受給の見直しがある
障害年金には「永久認定」と「有期認定」の2種類があります。
| 種類 | 概要 | 更新の頻度 |
| 永久認定 | 状態の緩和や改善が見込めず治療の効果が期待できない場合
例:失明・手足の切断など |
更新不要で受給できる |
| 有期認定 | 状態の緩和や改善が見込める場合
例:がん・精神障がいなど |
1~5年周期で更新手続きをする |
永久認定は、治療の効果が期待できない場合に受けられる認定です。更新が不要なので、基本的には仕事を開始しても認定審査に影響がありません。有期認定は、障がいの改善が見込まれる場合に受けられる認定です。1~5年周期で更新手続きをおこなう必要があります。
その際に「以前よりも障がいが軽くなった」「仕事ができる改善が見られた」などと判断された場合には、障害年金の減額や停止につながる可能性があります。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
2.働きながら障害年金を受給するときに受給停止になり得る2つのケース

働きながら障害年金が受給できるかどうかは障がい者の状態により個別に認定審査をするため、一概には言えません。その上で、働きながら障害年金を受給するときに停止になる可能性がある2つのケースをご紹介します。どのようなことが受給停止の原因になる可能性があるのか、あらかじめ把握しておきましょう。
| 働きながら障害年金を受給するときに停止になり得るケース |
| ・障がいが軽くなったと判断された場合 ・20歳前傷病による障害基礎年金の場合 |
2-1.障がいが軽くなったと判断された場合
1つ目は、障がいが軽くなったと判断された場合です。先ほども触れましたが、障害年金は病気やけがで生活や仕事などが制限される場合に受け取ることができるものです。障がいにより生活や仕事が制限されない状態まで回復したと判断されると、受給が停止になる可能性があります。
肢体障がいや目や耳の障がいなど仕事をしても障がいの程度が変わらないことが明確な場合は、仕事が障害年金の受給に影響することは少ないと考えられています。
例えば、耳が聞こえにくい障がいがある方は、仕事を開始することが病気の回復に直結しません。障害年金2級の聴覚の認定基準は「両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの」と明記されているので、働いていても聴力レベルが90デシベル以上であれば障がい自体が軽くなったと判断されることはないでしょう。
同じように、車椅子を利用しながら仕事をしている方は、仕事内容をしたとしても身体の状態は変わっていません。このように、障がいが軽くなったから仕事をしているのではなく障がいの程度は同じで障がいを抱えながら働ける環境が見つかった場合は、受給への影響は少ないと考えられます。
一方で、精神障がいの方や内臓に障がいを抱えている方は、仕事の内容や働き方によっては「就労ができている=障害の程度が軽度なのではないか」と判断されてしまう可能性があります。精神疾患や内科系疾患の場合は言葉の記述で評価する項目が多く、基準が少しあいまいなためです。就労状況の捉え方によっては、障害年金の受給の停止や減額につながることがあると考えられます。
| 【仕事を開始したらすぐに受給が停止するわけではない】
障害年金の受給を受けている期間に仕事を開始したからといって、急に受給が停止するわけではありません。基本的には、次回の更新までは支給は継続します。次回の更新時の認定審査時に仕事をしていることが反映されて受給の継続、もしくは減額や停止などの判断が下ります。 |
2-2.20歳前傷病による障害基礎年金の場合
2つ目は、20歳前傷病による障害基礎年金の場合です。20歳前傷病は、20歳の誕生日よりも前に初診日がある方が対象です。例えば、生まれつきの障がいがある場合や幼い頃にケガや事故に遭った方が該当します。20歳前傷病による障害基礎年金は年金の加入を要件としていないため、下記のような所得制限があります。
| 20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限 | |
| 前年度所得が472.1万円を超える場合 | 全額支給停止 |
| 前年度所得が370.4万円を超える場合 | 2分の1の支給停止 |
※2023年時点の金額
※扶養親族がいる場合:扶養親族1人につき所得制限額に38万円を加算など扶養家族に関する加算あり
例えば、20歳前傷病による障害基礎年金の受給者が年間で480万円の所得を得た場合は、翌年の障害年金支給が停止になります。
20歳前傷病による障害基礎年金は、毎年本人の所得確認が必要です。前年所得に基づく給対象期間は10月分から翌年9月分なので、所得制限がかかると10月分から翌年9月分までの障害年金の受給額が減額、もしくは停止します。
参考元:日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
3.働きながら障害年金を受給したい場合は慎重に判断するべき

ここまで解説してきたように、障害年金の受給は一人ひとりの状況を認定基準と照らし合わせながら総合的に審査をします。とくに障害年金の受給を開始した後に仕事を始めた場合は、更新時に仕事を理由に「等級が下がる」「受給が停止する」などの判断が下される可能性があり、一概に障害年金の受給が継続できるとは言えない状態です。
減額や受給停止が起きた場合は「4-2.障害年金が停止になった場合は審査請求を検討する」でも触れているように再審査請求ができますが、一度受けた判断を覆すことは難しいケースもあります。働きながらでも障害年金の受給を継続したいと考えている場合は、慎重に判断することが大切です。
3-1.受給が継続できるか迷ったら相談をする
「仕事を開始したいけれど、障害年金の受給が継続できるか分からない」と悩んでいる場合は、自己判断は避けたほうがいいでしょう。どのような働き方なら障害年金を受給できる可能性があるのか、そもそも障害年金の受給を継続することは難しいのかなど細かな判断は、専門的な知識や今までの経験がないと分からないことが多いです。
働きながらの障害年金の受給については、下記のような窓口で相談できます。
| 【障害年金の相談ができる窓口の一例】
・年金事務所 |
「障がいがあるけれどパートタイムで働きたい。その場合に障害年金はどうなるのか?」など詳しい状況を説明して障害年金が継続できる可能性はどの程度あるのか聞いてみると、判断材料になるでしょう。
3-2.働きながら障害年金を受給できた裁判事例
仕事をしていることなどが理由で障害年金の受給が認められず、訴訟を起こした事例があります。発達障がいと軽度の知的障がいがある男性は、就労していることなどを理由に障害年金の支給が認められませんでした。
そこで、支給を認めないのは不当だとして、不支給処分の取り消しを求めて訴訟を起こしました。東京地方裁判所は国の不支給決定を取り消し、障害基礎年金2級の支給いを命じました。国は控訴せず判決が決定し、未払い分の障害年金と今後の障害年金の支払いが決まりました。
弁護士は「就労が続いていると障害年金が支給されないケースがあるが、支援の状況を丁寧に判断すべき」と話しており、働きながら障害年金を受給するときの判断のあいまいさを指摘しています。
参考:高知新聞「障害年金450万円支給へ 東京地裁が命令、国が敗訴」
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
4.働きながら障害年金を受給したいときに知っておきたいポイント

ここでは、働きながら障害年金を受給したいときにあらかじめ知っておきたいポイントをご紹介します。障害年金の認定審査は書面でおこなうので、自分の状況をしっかりと伝えることが大切です。少しでも受給できる可能性を高めるにはどのようなことができるのか分かるので、参考にしてみてください。
| 働きながら障害年金を受給したいときに知っておきたいポイント |
| ・審査員に就労の状況をしっかりと伝える ・障害年金が停止になった場合は審査請求を検討する |
4-1.審査員に就労の状況をしっかりと伝える
働きながら障害年金を受給するには、就労の状況を細かくしっかりと伝えることが大切です。ただ単に「仕事をするようになりました」という事実のみを伝えてしまうと「仕事ができるようになった=障がいが軽くなった」と捉えられてしまう可能性があります。
他の従業員の手助けがあり何とか仕事ができている、障がいがあっても仕事ができるように配慮をしてもらっている状況であっても、この部分をしっかりと伝えないと認定審査に反映されません。
例えば、発達障がい・知的障がい・症状性を含む器質性精神障がい・統合失調症の判断基準には、下記のような記載があります。簡単に言うと仕事をしている事実だけで判断せず仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容なども考慮したうえで判断するという内容です。
| 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。 |
精神障がいがあっても判断基準には「就労状況の考慮」の要素があるので、下記のようなことを細かく記載するように心がけてください。
・仕事の内容
・仕事をしている時間
・職場での配慮や援助(例:仕事内容に配慮があり取り組みやすい作業をしている)
・仕事をするうえでの壁(例:障がいによりコミュニケーションが難しい)
病院からの診断書や仕事の有無だけでは分からない部分を伝えることで、現状を汲み取り認定審査をしてもらえるでしょう。
4-2.障害年金が停止になった場合は審査請求を検討する
万が一、仕事をしているという理由で障害年金の受給が停止になった場合は、審査請求ができます。審査請求とは障害年金の認定審査結果に納得できなった場合に、再度審査をし直してもらう手続きのことです。
処分を知った日の翌日から3ヶ月以内であれば、審査請求をすることが可能です。地方厚生局内に設置されたている社会保険審査官に、文書または口頭で請求できます。
審査請求をするときには決定を覆すために、審査請求の理由を明確に記載しなければなりません。また、診断書などの証拠も必要なので、時間と労力がかかることを念頭に置いておきましょう。
参考:日本年金機構「年金の決定に不服があるとき(審査請求)」
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
5.働きながら障害年金を受給するときのQ&A

最後に、働きながら障害年金を受給するときによくある質問をご紹介します。
5-1.障害年金をもらいながら働く場合の税金はどうなりますか?
障害年金をもらいながら働く場合は、障害年金分は非課税・働いて得た給与は課税対象となります。
| 所得の種類 | 課税の有無 |
| 障害年金 | 非課税所得 |
| 働いて得た対価(給与) | 課税所得 |
参考:国民年金機構「非課税所得とは、どのようなものですか。」
例えば、年間で障害年金を60万円、給与を200万円得た場合は、給与分の200万円のみ課税対象です。ただし、障がいのある方の状況に応じて、様々な控除が受けられる可能性があります。控除の内容は下記を参考にしてみてください。
参考: 国税庁「障害者と税」
5-2.障害年金を受け取っていることは会社に知られますか?
障がいのある方が会社に直接申告しない限りは、基本的には障害年金を受け取っていることは知られません。障害年金は非課税所得でかつ、社会保険料に関係ありません。そのため、基本的には障害年金の有無が会社のおこなう業務に何らかの影響を与えることがありません。
5-3.働きながら障害年金を受給する場合に所得制限はありますか?
「2-2.20歳前傷病による障害基礎年金の場合」を除き、基本的には所得制限はありません。冒頭で述べたように、障害年金を受給しながら年収400万円以上稼いでいるケースもあります。もちろん、心身の状況に応じて無理のない範囲で働くことが重要ですが、基本的には所得制限はなく自由に働けます。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
6.まとめ
いかがでしたか?働きながら障害年金の受給ができるのか分かり、働き方や仕事を検討できるようになったかと思います。最後にこの記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。
〇障害年金は働きながらでも、半数程度の障がい者が受給できている状態
〇障害年金の受給条件に就労の有無が含まれていない。ただし、障害年金自体が「病気やけがで生活や仕事などが制限される場合に受け取ることができる年金」なので、仕事をしていることが無関係であるとは言い難い
〇働きながら障害年金を受給するときに停止になり得るケースは次の2つ
・障がいが軽くなったと判断された場合
・20歳前傷病による障害基礎年金の場合(年間の所得制限がある)
〇障害年金の受給は一人ひとりの状況を認定基準と照らし合わせながら総合的に審査をしている。働きながら障害年金を受給できるか迷ったら相談できる機関に相談する
〇働きながら障害年金を受給したいときに知っておきたいポイントは次の2つ
・審査員に就労の状況をしっかりと伝える
・障害年金が停止になった場合は審査請求を検討する
働きながら障害年金を受給している障がいのある方は一定数いらっしゃいますが、障害年金の性質上就労状況と障害年金の受給継続を切り離して考えることは難しい側面があります。判断に迷った場合には信頼できる機関に相談しながら進めるようにしましょう。
おすすめ記事
-

詳細を見る
2026年1月16日
【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件
「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]
法律・制度
-

詳細を見る
2026年1月13日
水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説
「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]
法律・制度
-

詳細を見る
2026年1月13日
ロクイチ報告とは|概要から提出意義、押さえるべき知識まで徹底解説
「ロクイチ報告とはどういうものか知りたい」 「用紙が届いたのだが、必ず提出しなければいけな[...]
法律・制度










