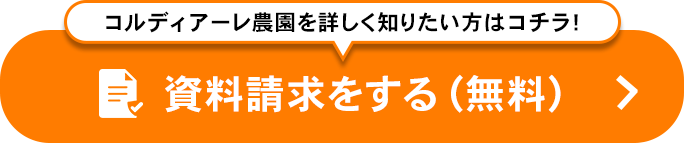コラム詳細
2025/04/08
autorenew2026/01/06
【事例あり】障がい者雇用のよくあるミスマッチと回避のための取り組み
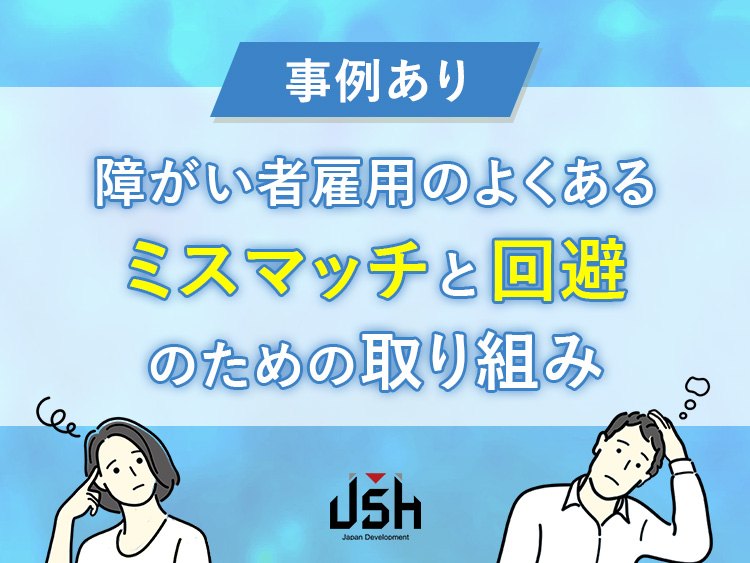
「障がい者雇用の課題の一つとしてよく挙げられる『ミスマッチ』とは、具体的にどのようなものなのだろう?」
「障がい者雇用におけるミスマッチを回避するためには、どんな取り組みが必要だろうか?」
障がい者雇用について検索をしていると「ミスマッチ」という言葉を頻繁に見かけますが、ミスマッチが具体的にどのようなものを指すのか、イマイチ分からない方もいるのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、障がい者雇用においてよく見られる「ミスマッチ」には、以下のようなものが挙げられます。
| 障がい者雇用でよく見られる3つのミスマッチ |
| ・障がい者の能力と業務レベルのミスマッチ
・障がい特性と企業の体制・設備のミスマッチ ・障がい者がイメージする仕事と実際の仕事内容のミスマッチ |
上記のような3つのミスマッチの事例に共通しているのは、根本的に障がい者と企業の相互理解が足りていないことが要因だと言えます。
したがって、むやみに対策するのではなく、障がい者と企業が相互理解を行うことができる環境や仕組みを作り、その上で対策していかなければ、障がい者雇用におけるミスマッチを回避することはできません。
そこでこの記事では、障がい者雇用でよくあるミスマッチを事前に知り、回避できるように、
・障がい者雇用におけるミスマッチや事例
・ミスマッチを回避するための適切な対処法
についてお伝えしていきます。
障がい者雇用におけるミスマッチを解消することで、法律を遵守しつつ企業の社会的責任を果たすことにも繋がるため、これから障がい者雇用に取り組む方はぜひ最後まで読み進めてください。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
【目次】
1. 【事例】障がい者雇用でよく見られる3つのミスマッチ
2. ミスマッチを起こさないためには障がい者との相互理解が必要
3. 障がい者雇用のミスマッチを起こさないためにやるべき取り組み
4. 自社だけで障がい者雇用のミスマッチへの対応が難しいと感じるなら外部支援を上手く利用しよう
5. まとめ
1.【事例】障がい者雇用でよく見られる3つのミスマッチ

障がい者雇用は、企業にとって真摯に取り組むべき重要な課題の一つですが、様々なミスマッチが発生しやすい分野でもあります。
そこでまずは、企業側でよく見られる障がい者雇用のミスマッチを具体的な事例とともにご紹介します。
| 障がい者雇用でよく見られる3つのミスマッチ |
| ・障がい者の能力と業務レベルのミスマッチ
・障がい特性と企業の体制・設備のミスマッチ ・障がい者がイメージする仕事と実際の仕事内容のミスマッチ |
それでは、それぞれを詳しく見ていきましょう。
1-1.障がい者の能力と業務レベルのミスマッチ
1つ目は、障がい者の能力と業務レベルのミスマッチです。
具体的には、以下のようなミスマッチがよく見られます。
| 障がい者の能力と業務レベルのミスマッチの具体例 |
| ・能力や意欲以上の業務レベルを求められるケース
・高いレベルの業務を希望するのに簡単な仕事しか与えられないケース |
実際に、以下のような事例もありました。
| 能力や意欲以上の業務レベルを求められるケース |
| A社では、法定雇用率の達成に向けて、将来の管理職・幹部候補となる総合職を基準として障がい者を採用しました。
実際には、障がいのある従業員本人の能力以上の高度な仕事を割り当て、総合職と同じ制度で業務に対する評価を行ったのです。
結果として、障がいのある従業員の多くが目標達成に苦労し、ストレスや不満が蓄積されることになります。
さらに、周囲の一般社員からも「同じ処遇なのに仕事が出来ない」という不満が生まれたため、職場の雰囲気が悪くなってしまいました。 |
| 高いレベルの業務を希望するのに簡単な仕事しか与えられないケース |
| B社では、能力が高く「働きたい!」と意欲のある障がい者に対して、単純で簡単な業務のみを割り当てました。
結果として、せっかくスキルと意欲が高い従業員を雇用しているにも関わらず、従業員のモチベーションやキャリア成長の機会を奪ってしまうことになってしまいました。
さらに、従業員からは「自分の障がいについて何回説明すればいいのか」という不満の声が上がり、組織全体の理解や支援が不足していることが浮き彫りになりました。 |
このように、障がい者それぞれで能力が異なるにも関わらず、個人の特性や個性を理解しないまま業務を割り振ってしまうことで、上記のようなミスマッチが起こってしまうのです。
また、障がい者本人がどんな仕事をどれくらいやりたいと考えているのかを把握しないまま、画一的な作業を割り当てることで、キャリアの意向へのミスマッチにも繋がります。
1-2.障がい特性と企業の体制・設備のミスマッチ
障がい者雇用においてよくあるミスマッチの2つ目は、障がい特性と企業の体制・設備のミスマッチです。
具体的には、以下のようなミスマッチがよく見られます。
| 障がい特性と企業の体制・設備のミスマッチの具体例 |
| ・障がいの特性と職場内の物理的な環境に乖離があるケース
・障がいの特性について社内での理解が不足しているケース |
実際に、以下のような事例もありました。
| 障がいの特性と職場内の物理的な環境に乖離があるケース |
| C社では、法定雇用率達成に向けた取り組みとして視覚障がい者を採用しました。
その従業員は優秀なプログラマーでしたが、資料の文字が小さい・読み上げツールが準備されていないなど、職場環境がその人の能力を生かせる状況ではありませんでした。
また同僚からの理解も得られていなかったことから職場内に居場所のなさを感じて、その従業員は突然退職することになったのです。 |
| 障がいの特性について社内での理解が不足しているケース |
| D社では、障がいのある従業員から人事部門と配属部門の上司に対して「電話対応が苦手なため、電話対応は免除してほしい」との申し出がありました。
しかし、この情報が同僚に共有されていなかったため、上司不在時に同僚が電話対応を指示してしまい、その従業員は辛い思いをすることになりました。 |
このように、企業が障がいの特性について十分理解できていないことで、物理的・心理的に働きやすい職場環境を用意できず、上記のようなミスマッチが起こってしまいます。
1-3.障がい者がイメージする仕事と実際の仕事内容のミスマッチ
3つ目は、障がい者がイメージする仕事と実際の仕事内容のミスマッチです。
具体的には、以下のようなミスマッチがよく見られます。
| 障がい者がイメージする仕事と実際の仕事内容のミスマッチの具体例 |
| 障がい者が認識するスキルレベルと企業側の期待度に差がある |
実際に、以下のような事例もありました。
| 障がい者が認識するスキルレベルと企業側の期待度に差があったケース |
| E社では、軽度の知的障がいの方から応募があり、総務部で採用前の職場実習を行うことにしました。
その方のエントリーシートには「パソコンが使える」と記載されていたため、企業側は多少の期待感を持っていましたが、いざ実習が始まると想定外の事態に直面しました。
その方のパソコンスキルは基本的な操作に止まり、実際の業務で必要な複雑な表計算やデータベース操作には対応できなかったのです。
社員たちは丁寧にサポートしましたが、業務を行うのに予想以上の時間がかかり、効率が下がってしまいました。 |
このように、障がい者本人が認識しているスキルと企業で行う業務の実態がそもそも食い違っていたことで、上記のようなミスマッチが起こってしまうのです。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
2.ミスマッチを起こさないためには障がい者との相互理解が必要

障がい者雇用におけるミスマッチを防ぐためには、企業と障がいのある従業員との相互理解を徹底することが一番重要です。
先ほどご紹介した事例を見ても分かるように、障がい者雇用のミスマッチは、障がいの特性や障がい者本人の能力に対する認識がズレていることが主な原因として考えられます。
企業側と障がいのある従業員の間で、
・お互いの期待や能力
・本当に必要な配慮
・障がいの特性
について十分なコミュニケーションが取れていないことが、大きなズレを生む原因となっているのです。
例えば、「1-1.障がい者の能力と業務レベルのミスマッチ」でご紹介したB社のケースでは、障がい者本人の意向に対して企業が簡単な業務のみを割り当てたことでミスマッチが起こっていました。
しかし、障がい者本人の意向と企業が任せられる業務レベルについて事前に擦り合わせができていれば、ストレスや不満が溜まるほどのミスマッチにはならなかったはずです。
他にも、「1-2.障がい特性と企業の体制・設備のミスマッチ」でご紹介したD社のケースでは、障がいのある従業員とその上司、それ以外の社員で障がい特性に対する認識や理解が食い違っていたことからミスマッチが起こっていました。
このケースも、障がいの特性について企業が本人とよく話し合い、その情報を社内全体に周知していれば起こらなかったミスマッチでしょう。
このように、どのようなミスマッチでも、障がい者本人と企業側が相互理解を徹底することが前提であると言えます。
その上で、障がい者雇用におけるミスマッチを起こさないために、企業がやるべきその他の取り組みについては、続けて詳しく解説しますのでどうぞこのまま読み進めてください。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
3.障がい者雇用のミスマッチを起こさないためにやるべき取り組み

ここからは、障がい者雇用のミスマッチを起こさないために企業がやるべき取り組みについて、詳しくご紹介していきます。
企業がやるべき具体的な取り組みは、以下の通りです。
| 障がい者雇用のミスマッチを起こさないためにやるべき取り組み |
| ・企業の方針を明確にして採用活動を行う
・継続的なコミュニケーションと支援を行う ・それぞれの障がい特性に応じた業務設計やサポートを提供する |
それでは、それぞれを詳しく見ていきましょう。
3-1.企業の方針を明確にして採用活動を行う
障がい者雇用のミスマッチを防ぐためには、まず企業側が障がい者雇用に対する方針を明確にした上で採用活動を行うことが重要です。
方針を明確にして採用活動を行うと、自社の方針に共感する人だけが応募者として集まってくれるため、応募時や面接の時点で起こるミスマッチを防げます。
具体的には、以下のような内容を細かく決めて、採用活動の段階で周知することが重要です。
| ・障がい者雇用を通じて実現したい社会的価値や、企業としての成長目標
・部門ごとの採用人数や配属先 ・障がい者が従事する具体的な業務内容 ・障がい者雇用を担当する部署や責任者 ・キャリアアップの機会や育成プラン ・障がい者雇用に関する社内研修や教育の方法 |
このような方針を明確にして、募集の段階で明確に示しておくことで、障がい者雇用におけるミスマッチの芽を摘み取っておくことができるでしょう。
3-2.継続的なコミュニケーションと支援を行う
障がい者雇用を安定させるためには、従業員を雇用した後も継続的なコミュニケーションと支援を行うことが不可欠です。
障がいの有無に限らず、実際に働いてみないとわからないことは多々あるはずです。
そのため、「採用時にしっかりコミュニケーションを取って、ミスマッチを回避できた」と考えていても、業務を行う中で小さなミスマッチが出てくる可能性はあります。
このため、採用時だけではなく長期的な視点でしっかりコミュニケーションを取って、お互いがミスマッチだと感じることを早期に解消することが重要なのです。
具体的なコミュニケーションの取り方には、以下のようなものが挙げられます。
| ・定期的な面談を実施する
・専門の相談員や相談窓口を設置する ・チャットアプリや目安箱など、対面じゃないコミュニケーション方法を用意する |
このように、継続的にコミュニケーションを取り合える仕組みを整えることで、障がいのある従業員が退職してしまったり、企業側に損失が出たりするほどのミスマッチは生じなくなるはずです。
3-3.それぞれの障がい特性に応じた業務設計やサポートを提供する
継続的なコミュニケーションの仕組みが整ったら、ヒアリングした内容に基づいてそれぞれの障がい特性に応じた業務設計やサポートを提供することも大切です。
それぞれの障がい特性や能力に応じて業務設計を行うことで、本人の能力を最大限発揮できる環境を整えられるため、企業や業務に対する「こんなはずではなかった」という大きな不満やミスマッチが起きづらくなります。
例えば、具体的な障がい特性に応じた業務設計やサポートには以下のようなものが挙げられます。
| ・障がいの特性に合わせた業務内容や配属先にする
・勤務時間や業務量を個別に設定する ・障がいの特性に合わせて必要な設備やツールを導入する |
このような取り組みは「合理的配慮」とも呼ばれ、障がい特性に応じた合理的配慮の提供は「障害者雇用促進法」によって定められた企業の法的義務でもあります。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
4.自社だけで障がい者雇用のミスマッチへの対応が難しいと感じるなら外部支援を上手く利用しよう

障がい者雇用におけるミスマッチへの対応を自社だけで行うのが難しいと感じる場合は、外部の支援機関やサポートを活用するのがおすすめです。
専門の支援機関やサポートを活用すれば、ミスマッチを回避するための取り組みもスムーズかつ効果的に進めることができます。
具体的な支援機関と受けられるサポートには、以下のようなものがあります。
| ハローワーク | ・障がい者を雇い入れる準備のサポート
・職場定着支援 ・雇用管理へのアドバイス ・雇用率未達成の企業への具体的な指導 ・助成金や支援制度活用の提案
|
| 地域障害者職業センター | ・セミナーの案内や企業内研修のサポート
・ジョブコーチの派遣
|
| 障害者就業・生活支援センター | ・関係機関との連絡や調整
・雇用管理に関する助言 ・障がい者雇用に関する情報の提供
|
| 就労移行支援事業所 | ・障がい者の紹介
・人材雇用後の定着支援 ・企業説明会や実習の実施機会の提供 |
| 民間の障がい者就労支援サービス | ・障がい者雇用に関する戦略の立案
・職場環境の整備に関するアドバイス ・企業のニーズに合わせた人材の紹介 ・農園型、サテライトオフィス型などの特殊な雇用形態の提案 ・社内の障がい者雇用担当者向けの研修 |
障がいのある従業員と企業の両方にとってより良い関係を構築し、安定した障がい者雇用を実現するために、困ったことがあれば積極的に利用するといいでしょう。
| 【障がい者雇用のミスマッチを回避したいなら、株式会社JSHにご相談ください】 |
| 障がい者雇用における企業と従業員のミスマッチを回避して、企業にとっても、障がいのある方にとっても安心につながる障がい者雇用を実現したいという企業様を、当社は支援しています。
当社が運営する農園型障がい者雇用支援サービス「コルディアーレ農園」では、企業様と働く意欲のある障がいのある方をつなぎ、
・農園スタッフによる日々の業務や送迎のサポート ・看護師含む専門スタッフによる定着支援のサポート
などを通じて、障がいのある方が安心して働ける支援を行っています。
弊社の農園型障がい者就労支援サービスを導入していただいている企業様は190社以上、継続率は99%(2024年6月時点)となっており、障がいのある方が安心してご活躍されていることがお分かりいただけるかと思います。
障がいのある従業員とのミスマッチを起こさないための業務設計やサポート提供についてご不安な場合は、ぜひ以下よりコルディアーレ農園の詳細をご確認ください。
|
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
5.まとめ
この記事では、「障がい者雇用でよく見られるミスマッチの事例」と「ミスマッチを起こさないためにやるべきこと」をそれぞれご紹介しました。
この記事でご紹介した、障がい者雇用でよく見られるミスマッチの事例は以下の通りです。
| 障がい者雇用でよく見られる3つのミスマッチ |
| ・障がい者の能力と業務レベルのミスマッチ
・障がい特性と企業の体制・設備のミスマッチ ・障がい者がイメージする仕事と実際の仕事内容のミスマッチ |
また、障がい者雇用のミスマッチを起こさないためにやるべき取り組みには、以下のようなものが挙げられます。
| 障がい者雇用のミスマッチを起こさないためにやるべき取り組み |
| ・企業の方針を明確にして採用活動を行う
・継続的なコミュニケーションと支援を行う ・それぞれの障がい特性に応じた業務設計やサポートを提供する |
上記のような取り組みを自社だけで行うのが難しいと感じる場合には、外部の専門支援機関やサポートを活用することがおすすめです。
安定した障がい者雇用を実現するために、この記事がお役に立てれば幸いです。
おすすめ記事
-

詳細を見る
2026年2月10日
ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説
「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]
事例
-

詳細を見る
2026年1月16日
【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件
「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]
法律・制度
-

詳細を見る
2026年1月13日
水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説
「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]
法律・制度