コラム詳細
2024/10/15
autorenew2025/12/19
障害者差別解消法に違反したときの罰則や実際の違反事例を解説
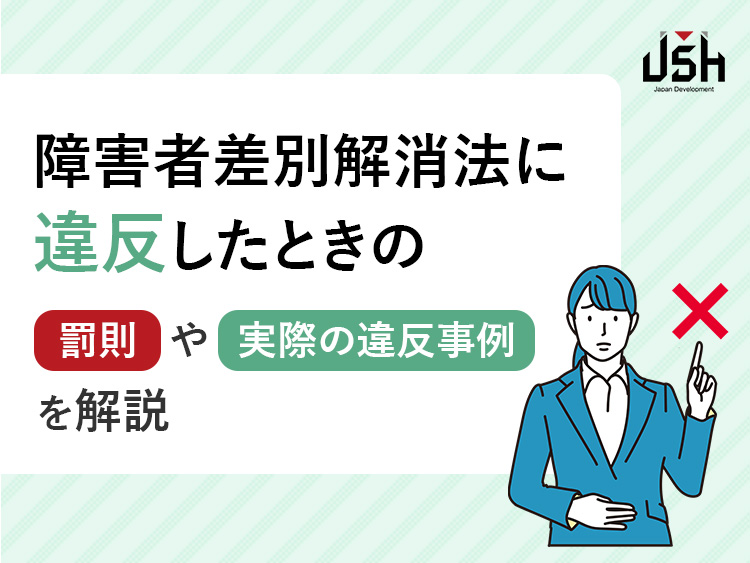
「障害者差別解消法に違反した企業は、どうなりますか?」
このように、合理的配慮ができていない場合や不適切な対応をしてしまった場合はどうなるのか、と今まさに不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から申し上げると、2024年7月現在、事業者が障害者差別解消法を守れなかったケースがあっても、今すぐに罰則が科せられることはありません。
「障害者差別解消法」とは、正式名称を「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、平成25年6月に制定された法律です。
この法律は、行政機関や事業者に対して障がいを理由とする差別の解消を目的とし、障がいのある人への「不当な差別的取扱い」の禁止と「合理的配慮」の提供を義務付けています。
前述のように、ただちに罰則が課せられることはありませんが、以下のような場合には行政処置などの罰則が科されることがあります。
| ・行政機関から状況報告を求められたときに、正しく応じなかった場合
・企業が自主的に改善できないと判断された場合 |
また、仮に罰則の対象とならなかったとしても、障害者差別解消法に違反するようなことがあれば、「障がい者を差別している企業」と捉えられ企業イメージの悪化につながりかねません。
そのため、違反は絶対に避けたいものです。
そこでこの記事では、障害者差別解消法の違反について、以下の内容を解説していきます。
| この記事を読むとわかること |
| ・障害者差別解消法に違反すると科される罰則
・障害者差別解消法の違反事例 ・企業(事業者)が障害者差別解消法を違反しないためにできること |
この記事を読めば、障害者差別解消法に違反した場合について詳しく知ることができます。
また記事の後半では、違反しないために取り組むべき対策についても解説しているため、ぜひ最後までご覧ください。
障害者差別解消法の概要や義務化の内容など、法律自体について詳しく知りたい人は、こちらの記事を参考にしてください。
障害者差別解消法とは?事業者に義務化された合理的配慮も詳しく解説
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
【目次】
1. 障害者差別解消法に違反してもただちに罰則が課せられることはない
2. 障害者差別解消法に違反したときの罰則と該当ケース
3. 障害者差別解消法の実際の違反事例3つ
4. 障害者差別解消法を違反しないためにできること3つ
5. まとめ
1. 障害者差別解消法に違反してもただちに罰則が課せられることはない

冒頭で解説したように、現時点では同法に違反したからといって、即座に罰金や罰則が科されることはありません。
実際に、内閣府による「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律についてのよくあるご質問と回答」のページでも、以下のように解説されています。
| Q7.企業などがこの法律に違反した場合、罰則が課せられるのでしょうか。
A.この法律では、民間事業者などによる違反があった場合に、直ちに罰則を課すこととはしていません。 |
引用:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律についてのよくあるご質問と回答<国民向け>|内閣府
この法律の主な目的は、障がい者に対する差別の解消と合理的配慮の促進にあります。そのため罰則を設けることよりも、社会全体の理解を深めることに重点が置かれています。
なお、障害者差別解消法に関して罰則が全くないわけではありません。法律違反を繰り返した場合などには、罰則が科される可能性があります。
具体的にどのような場合に罰則が科されるのか、その内容については、次の章で詳しく説明していきます。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
2. 障害者差別解消法に違反したときの罰則と該当ケース

繰り返しになりますが、この法律に違反したからといって、即座に罰則が科されることはありません。
しかし、以下の2つのケースでは、罰則が科されることがあります。
| ・行政機関から状況報告を求められた際に、正しく応じなかった場合
・企業が自主的に改善できないと判断された場合 |
行政機関から状況報告を求められた際に正当な理由なく報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合には、罰則として20万円以下の過料があります。
さらに行政によって、企業が自主的に改善できないと判断された場合、以下のような行政措置がとられる可能性があります。
| ・助言
・指導 ・勧告 など |
多くの場合、20万円以下の罰則や行政措置そのものは、企業の負担にはなりません。
しかし障害者差別解消法違反に対する罰則や行政措置は、ニュースなどで公開されることもあり、「障がい者に対して差別的な企業」と企業ブランドイメージ低下につながるリスクがあります。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
3. 障害者差別解消法の実際の違反事例3つ

ここまで、障害者差別解消法に違反したときの罰則について解説してきました。
とはいえ、実際にはどのようなケースが法律に抵触するのかわからないという人もいるでしょう。
そこでこの章では、以下のように実際に発生した障害者差別解消法の違反事例を3つ紹介します。
| ・【顧客に対する差別事例】知的・発達障がい者に一律で付き添いを要求
・【施設利用者に対する差別事例】精神障がいを理由に公共施設の利用を制限 ・【従業員に対する差別事例】特例子会社による合理的配慮義務違反 |
それでは、それぞれの違反事例を見ていきましょう。
3-1. 【顧客に対する差別事例】知的・発達障がい者に一律で付き添いを要求
| 航空会社が知的・発達障がい者に一律で付き添いを求めたケース |
これは、新潟市の航空会社が、ホームページ上で知的障がいや発達障がいのある利用者に対して「一律で付き添いを求める」という案内文を掲載していた差別事例です。
国土交通省は、この文が障害者差別解消法で禁じている「障がいのみを理由とした搭乗拒否」に該当する可能性があると指摘し、航空会社に対して口頭で案内文の修正を提案しました。
指摘を受けた航空会社は、問題となった案内文を即座に修正しました。
参考:国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針 P35
3-2. 【施設利用者に対する差別事例】精神障がいを理由に公共施設の利用を制限
| 自治体が精神障がいを理由に公共施設の利用を制限したケース |
これは複数の自治体が、精神疾患や障がいを理由に以下のような公共施設の利用を制限する条項を設けていた差別事例です。
・庁舎の利用
・教育委員会の傍聴
・公民館や公園、プールの利用 など
この件では、文部科学省と総務省が各自治体に対して規定の見直しを通知しています。
3-3. 【従業員に対する差別事例】特例子会社による合理的配慮義務違反
| 特例子会社が合理的配慮義務違反で訴えられたケース |
特例子会社とは、「障がい者雇用の促進と安定を図るため」に設立される子会社の事です。
このケースでは、その特例子会社が障がいの特性に配慮した措置を講じる義務を怠ったことにより従業員から訴訟されました。
具体的には、高次脳機能障がいのある従業員による「指示は1度に二つまでにしてほしい」「ブラウスやスーツが着られない」という申し入れに対応しませんでした、
裁判の結果和解が成立し、両者は以下の内容に合意しました。
・会社は解決金として200万円を支払う
・会社は「厚生労働省の指針に沿った合理的配慮の提供」および「組織的な職場環境の改善」に努める
このように、障害者差別解消法に違反した場合、罰則こそありませんが、訴訟されるリスクは十分にあります。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
4. 障害者差別解消法を違反しないためにできること3つ

前章では、実際に発生した差別事例について解説しました。
社内で同様の障がい者差別を起こさないためには、何ができるでしょうか。
この章では、以下のように企業が障害者差別解消法を違反しないためにできる3つのことを解説します。
| ・合理的配慮の内容をまとめたマニュアルを周知させる
・障がい者本人とコミュニケーションをとる ・相談窓口・トラブル対応などの担当者を決定する |
それでは、それぞれについて詳しく解説していきます。
4-1. 合理的配慮の内容をまとめたマニュアルを周知させる
企業として障害者差別解消法を遵守するためには、障害者差別解消法と合理的配慮に関するマニュアルを作成し、周知しましょう。
このマニュアルでは、障害者差別解消法の概要はもちろん、「合理的配慮」について、詳しく解説することが重要です。
なぜなら、合理的配慮の最適な内容は、業種やシチュエーション、障がいの種類などによって全く異なるからです。従業員それぞれの判断に任せるだけでは、不十分で不適切な対応になってしまうこともあるでしょう。
従業員の理解不足による障がい者差別を避けるためには、マニュアルで具体的な事例や適切な対応方法を共有し、全員に周知徹底することが求められます。
具体的には、以下のような内容を盛り込んだマニュアルが効果的です。
| ・視覚障がい者に対して:重要事項は声に出して読む
・聴覚障がい者に対して:筆記でのコミュニケーションを取る ・曖昧な表現の理解が難しい障がい者に対して:「はい」か「いいえ」で答えられる質問をする ・緊張しやすい特性がある障がい者に対して:休憩を多く取り入れる など |
このようなマニュアルを作成・周知することで、従業員が障害者差別解消法と合理的配慮について共通の認識ができ、正しい対応が可能になります。
| マニュアルは作成・周知するだけではなく「研修」を行う |
| 作成したマニュアルは、配布するだけではなく、従業員がマニュアルの内容を理解できるよう研修を行いましょう。
障害者差別解消法に違反しないために、前述したようなマニュアルの作成と周知はとても大切です。しかし、それだけでは十分な対策とは言えません。
特に、以下のような立場の従業員には、より詳細かつ実践的な研修が必要です。
・障がいのある従業員が配属される部署に所属する従業員 ・同部署の教育担当者、管理職 ・店舗などで接客やサービスを行うスタッフ
上記の従業員は、障がいのある人と直接的に関わる機会が多く、特に適切な対応が求められます。 |
4-2. 障がい者本人とコミュニケーションをとる
特に、障がいのある人に対して差別的な行いをしないために最も効果的なのは、障がい者本人とのコミュニケーションです。
前述のように、必要な合理的配慮は状況によって異なるため、それぞれの人にとって適切な対応を行うことが求められます。
企業側が一方的に配慮の内容を決定するのではなく、以下のように障がい者本人の意見や要望を十分に聞くことが大切です。
<イベントなどに関するケース>
| 参加希望者に障がい者がいる場合、「安全性が十分に確保されていないこと」などを理由に参加を断るのではなく、まずは安全性に具体的な懸念があるかを本人と話し合う |
<障がい者雇用に関するケース>
| 合理的配慮を行う経済的負担を理由だけで採用を諦めず、企業に無理のない範囲でできる合理的配慮がないかを障がい者本人に相談する |
<合理的配慮に関するケース>
| 「イメージや一般的な知識」を基に合理的配慮の内容を判断するのではなく、実際に利用する障がい者や雇用する障がい者と話し合って必要な合理的配慮を決定する |
参考:
障害者差別解消に関する相談事例集
障害者差別解消法 【合理的配慮の提供等事例集】
このように、障がい者本人と建設的なコミュニケーションを重ね、互いに納得できる解決策を見出すことが重要です。
4-3. 相談窓口・トラブル対応などの担当者を決定する
あらかじめ障がいのある従業員に関する相談窓口や、障がいのある従業員からの相談・トラブル対応に関する担当者を決定しておきましょう。
繰り返しになりますが、合理的配慮の最適な内容は、障がいの特性や程度、業種、シチュエーションなどによって異なるため、ケースバイケースで判断しなければなりません。
義務化が始まったばかりということもあり、その解釈や適用範囲をめぐってトラブルが発生する可能性もあるでしょう。
今後企業がこれらの状況に対応していくためには、専門の相談窓口や担当者を設置し、そこに知見を蓄積していくことが求められます。
|
障がい者雇用を検討している企業様は 「コルディアーレ農園」の利用をご検討ください |
| マニュアルの整備や専任担当者の配置、教育、窓口の設置など、障害者差別解消法への対応を今からすぐに始めるのは難しい部分もあるかと思われます。
・障がい者を雇用したいが、障害者差別解消法に違反しないための施策を行うのが難しい ・合理的配慮や障害者差別に関する知見がない
このような悩みがある企業様は、ぜひ「コルディアーレ農園」をご検討ください。
私たち(株)JSHが運営するコルディアーレ農園は、地方在住の障がい者と障がい者雇用にお困りの企業様をつなぐ障がい者雇用支援サービスです。
農園で働く障がい者の方々は、企業の従業員として直接雇用され、コルディアーレ農園で勤務します。
弊社が以下の全ての工程をサポートするため、企業様は障害者差別解消法への対応を即座に整える必要なく、障がい者雇用を実現できます。
・障がい者の採用 ・職場の確保 ・職場環境の整備 ・障がいのある従業員の教育体制の構築 ・管理スタッフの教育 など
障がい者雇用を検討しているものの「障害者差別解消法への対応が難しい」という企業様はぜひ「コルディアーレ農園」にお問い合わせください。 |
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
5. まとめ
この記事では、企業が障害者差別解消法に違反した場合について解説しました。
〇2024年7月現在、事業者が障害者差別解消法を守れなかったケースがあっても、今すぐに罰則が科せられることはありません。
〇しかし、以下の2つのケースでは、罰則が科されることがあります。
| ・行政機関から状況報告を求められた際に、正しく応じなかった場合:罰則として20万円以下の過料
・企業が自主的に改善できないと判断された場合:助言/指導/勧告などの行政処置 |
〇企業が障害者差別解消法を違反しないためには、以下の3つの対策が効果的です。
| ・合理的配慮の内容をまとめたマニュアルを周知させる
・障がい者本人と定期的なコミュニケーションをとる ・相談窓口・トラブル対応などの担当者を決定する |
〇障がい者雇用を検討しているものの、上記のような「障害者差別解消法への対応が難しい」という企業様はぜひ「コルディアーレ農園」にご相談ください。
おすすめ記事
-

詳細を見る
2026年1月16日
【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件
「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]
法律・制度
-

詳細を見る
2026年1月13日
水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説
「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]
法律・制度
-

詳細を見る
2026年1月13日
ロクイチ報告とは|概要から提出意義、押さえるべき知識まで徹底解説
「ロクイチ報告とはどういうものか知りたい」 「用紙が届いたのだが、必ず提出しなければいけな[...]
法律・制度










