コラム詳細
2024/09/12
autorenew2025/11/06
障がい者枠の雇用について解説!対象企業が知っておくべき知識と採用方法
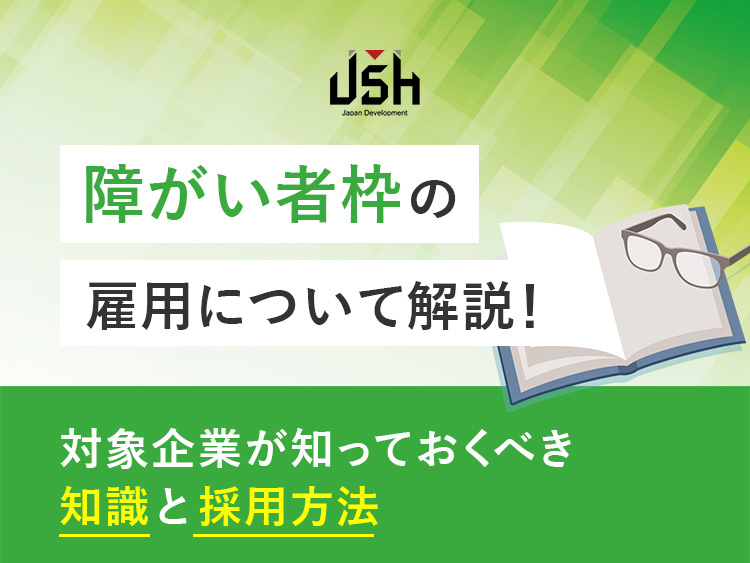
障害者雇用促進法により、40人以上の常用労働者がいる企業(雇用主)には、法定雇用率(2.5%)以上の障がい者を雇う義務があります。
しかし、
・障がい者枠で雇用する場合に、どのような仕事を任せられるかが分からない
・障がい者枠で雇用したくても、なかなかマッチするような人材が見つからない
という企業も多いのではないでしょうか。
必要な数の障がい者枠の雇用ができなかった場合、不足する人数に応じて1人あたり月5万円の「障害者雇用納付金」を納めなければなりません(※労働者数100人を超える企業の場合)。
さらに、障がい者枠を満たせないままだと納付金を納めるだけではなく、行政指導や社名公表の対象になる可能性もあります。こうした事態を避けたいという企業も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、「障がい者枠とは何か?」「なぜ障がい者の雇用が必要なのか」という基本的な部分の解説をするとともに、障がい者枠を満たせない企業が多い理由や、満たすための具体的なステップまで詳しく解説していきます。
「障がい者雇用を推進したいけれど、どうすればいいか分からない!」とお悩みの企業担当者様は、ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。
【目次】
1. 従業員40人以上の企業は「障がい者雇用枠」での雇用が必要
2. 障がい者雇用枠を満たせていない(半数程度は未達成)企業が多い
3. 障がい者雇用枠を満たすのが難しい4つの理由
4. 「障がい者雇用枠」での雇用を成功させる方法
5. まとめ
1. 従業員 40人以上の企業は「障がい者雇用枠」での雇用が必要

まずは、なぜ企業にとって障がい者枠の雇用が必要なのかを解説していきます。既に内容をご存知の方は、「2. 障がい者雇用枠を満たせていない企業が多い(半数程度が未達成)」からお読みいただければ幸いです。
1-1. 従業員に占める障がい者の割合を2.5%以上にしなければならない
企業が一般枠と別に「障がい者枠」を雇用しなければならない理由としては、障害者雇用率制度にもとづき、一定規模以上の企業は、従業員に占める障がい者(身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者)の割合を「法定雇用率」以上にする義務があると決まっているからです。
例えば、2024年時点では民間企業の法定雇用率が2.5%なので、40人以上の常用労働者がいる民間企業の場合に障がい者を雇用する義務が発生します。
| 事業者区分 | 法定雇用率 |
| 民間企業 | 2024年:2.5%(40人ごとに1人以上雇用) |
| 2026年:2.7%(37.5人ごとに1人以上雇用) | |
| 国・地方公共団体など | 2024年:2.8%(36人ごとに1人以上雇用) |
| 2026年:3.0%(33.5人ごとに1人以上雇用) | |
| 都道府県などの教育委員会 | 2024年:2.7%(37.5人ごとに1人以上雇用) |
| 2026年:2.9%(34.5人ごとに1人以上雇用) |
なお、表を見ていただくと分かる通り、法定雇用率は2026年7月から「2.5%」→「2.7%」に上がることが決まっています(民間企業の場合)。
企業が障がい者を雇う上で知っておくべきことについては、別記事「【2024年】障害者雇用促進法とは?押さえるべき改正内容も解説」の記事もぜひ参考になさってください。
1-2. 従業員が多いほど「障がい者雇用枠」の人数も増えていく
2.5%という割合が一定なので、従業員数が多くなればなるほど、法定雇用率を満たすための人数も増えていきます。
| 常用雇用労働者の数 | 法定雇用率を満たす障がい者の人数 |
| 従業員数40人 | 1人 |
| 従業員数100人 | 2人(小数点以下は切り捨て) |
| 従業員数500人 | 12人(小数点以下は切り捨て) |
| 従業員数1,000人 | 25人 |
| 従業員数5,000人 | 125人 |
大手企業などは、障がい者の長期で安定した雇用を実現するために、特例子会社を設立しているケースもあります。
2. 障がい者雇用枠を満たせていない(半数程度は未達成)企業が多い

ここからは、法律で定められている法定雇用率を、実際に企業は達成できているのかという点について解説していきます。
2-1. 法定雇用率を達成できている企業の割合は50.1%(2023年)
厚生労働省が発表した「令和5年 障害者雇用状況の集計結果」によると、法定雇用率を達成できている企業の割合は50.1%でした。半数の企業は、障がい者雇用枠を満たせていないことが分かります。
また、同じ資料によると、以下の状況が分かっています。
・法定雇用率未達成企業のうち、不足数が0.5人または1人である企業が66.7%と多い
・法定雇用率未達成企業のうち、障がい者を1人も雇用していない企業が58.6%と多い
この結果を見ると、障がい者の雇用義務がなかった会社が初めて雇用する時のハードルが高いという実情が見えてきます。
2-2. 都道府県によって障がい者雇用の難易度に格差がある
同じ資料での都道府県別の法定雇用率達成企業割合を見ると、東京都など人口の多い都道府県ほど達成企業割合が低いことが分かります。
厚生労働省の「令和5年 障害者雇用状況の集計結果(PDF)」で法定雇用率を達成した企業の割合を都道府県別で見ると、秋田県・新潟県・福井県などでは6割を超えている一方で、東京では34.4%と低い割合となっています。
法定雇用率の達成割合が低い地域は大規模な企業が多く(=雇用義務がある企業が多い)、優秀な障がい者を奪い合うような状態になっていると考えられます。

2章で示した通り、法律で定められている義務があっても、法定雇用率を満たせている企業は半数にとどまります。ここからは、企業が障がい者雇用枠を満たすのが難しい理由について考察していきます。
3-1. 理由1:障がい者にどの仕事を任せれば良いかが分からない
法定雇用率の対象になったばかりの企業など、障がい者雇用のノウハウがない職場に多いのが、「どのような仕事を任せて良いのかが分からない」という理由です。
特に、今まで障がい者を雇った経験がない企業の場合、業務のどの部分を任せるかイメージするのが難しいという点があります。障がい者雇用を受け入れるには、まず障がいについての理解を深める必要がありますが、そのような検討をする余力がないというケースも多いでしょう。
その結果、障がい者雇用枠の募集を出すところまで行かずに、法定雇用率の達成を諦めてしまうケースが多いようです。
3-2. 理由2:障がい者が働きやすい環境を整えるのが難しい
法律で求められている障がい者雇用枠を満たせない理由として、環境整備にまで手が回らないという点もあるでしょう。
障害者雇用率制度のルールにも書かれている通り、障がい者を受け入れるためには以下のような環境を整える必要があります。
| 障がい者のための職場づくりについて望まれること
・安全確保のための施設などの整備や職場環境を改善すること ・障がいの種類や程度に応じた安全管理や健康管理を実施すること ・障がい者の種類や程度に応じた職域を開発すること ・採用試験を行う場合にも、応募者の障がいや希望を踏まえた配慮を用意すること ・十分な教育訓練期間を設けること ・能力向上のための教育訓練を実施すること ・障がい特性を踏まえた相談、指導、援助など ・職場全体で障がい及び障がい者についての理解や認識を深めること
|
障がい者は人それぞれに障がいの程度や特性などが異なるため、それぞれに合わせて設備を整えたり、勤務時間を調整したりと、丁寧な調整が必要となります。
人手が足りていない職場ほど、このような調整が難しく、法定雇用率の達成を諦めているケースもあるでしょう。
3-3. 理由3:雇用しても短期間で離職されてしまう
障がい者の雇用が難しい理由として、雇用しても早期離職されてしまうという面もあります。
3-2とも関連しますが、せっかく雇用をしても、職場が「障がい者にとって働きやすい環境」になっていなければ、すぐに辞めてしまうというケースがあります。
施設・設備の整備だけでなく、全社的に障がいについての理解を深めて、相談しやすい仕組みなどメンタル面からも支えることが大切です。
3-4. 理由4:都市部では障がい者雇用の難易度が高い
2-2でも触れた通り、東京都などの都市部では、障がい者枠での採用を進めたくても雇用の難易度が高いという状況になっています。
その理由として、法定雇用義務のある企業(従業員数が多い企業)が都市部に集中している一方で、障がい者の在住エリアは都市部に集中している訳ではないという理由があります。このことにより、需要と供給のミスマッチが起きています。
例えば、都市部(東京23区)・大阪市・名古屋市で雇用義務がある企業の雇用義務人数を合計すると約28万人にのぼります。一方で、想定される障がい者の想定就労可能人数は約31万人しかいないという状況になっています。採用可能倍率は1.08倍で、企業にとっては、求める人材像を選びにくい採用難という状況と言わざるを得ません。
※地方の状況は逆で、雇用義務企業の割合が少なく障がい者の数は多いため、企業は雇用意欲のある障がい者の中から人材像に合う方を見つけやすい状況です。例えば九州の場合、採用可能倍率は10.29倍となっています。

本記事の最後の章として、難易度が高い「障がい者雇用」を成功させる方法について解説します。
ここまで述べた通り、障がい者雇用が法律で義務化されていようとも、なかなか簡単には雇用が進んでいない実情があります。特に、今まで障がい者を雇用したことが無いというようなゼロイチのフェーズでは、なかなか初めの一歩が踏み出しにくいものです。
こうした初めての障がい者雇用枠の採用を実現するためのステップを、5ステップで解説していきます。
4-1. まずは障がい・障がい者雇用についての理解を深める(ハローワークを活用)
まずは障がい者雇用を進めるための第一歩として、障がいそのもの(3種類の障がいの種類・特性など)や、障がい者雇用についての理解を深めていく必要があります。
全国のハローワークでは、障がい者雇用を進める事業主向けの支援窓口があります。厚生労働省のページに事業主向け支援の詳細が掲載されているので、ぜひ活用しましょう。
| ハローワークによる事業主向け支援の例
・採用の準備段階から採用後の定着支援まで一貫したチームでの支援 ・障がい者雇用の理解を深めるセミナーの実施 ・仕事の切り出しなどもサポート ・求人票の作成支援 ・求人にマッチした求職者を探すサポート ・求人と求職者のマッチングを図る面接会も実施 |
さらに、障がい者を雇い入れた場合や、施設などの整備・雇用管理の措置を行った場合には、助成金を受けられる制度もあります。助成金やハローワークのサポートを受けながら、環境を整えていきましょう。
4-2. 具体的な部署や職種の検討を行う
障がい者雇用への理解を深めて、雇用するための準備がある程度整ったら、具体的な部署や職種の検討を行いましょう。
前述したハローワークの支援サポートを活用する他に、各地域にある「地域障害者職業センター」の活用もおすすめです。初めて障がい者の雇用に取り組む企業への支援やセミナー、企業内研修、ジョブコーチ派遣などさまざまなサポートを受けられます。
こうした支援の手を借りながら、自社で障がい者を雇い入れる時に、どの部署でどのような職務を行ってもらうのか、雇用条件などをしっかりと決めていきましょう。
4-3. 障がい者枠での採用活動を行う
具体的な雇用条件がある程度決まったら、ハローワークなどの職業紹介サービスを使って採用活動を行います。
ハローワークでは、求人票の作成支援や、求人にマッチした求職者を探すサポート、求人と求職者のマッチングを図る面接会なども行っているので、積極的に活用しましょう。
また、厚生労働省が推進している「障害者 トライアル雇用」という制度を使えば、原則3か月の雇用期間の中でお互いのミスマッチを防げるのでおすすめです。
制度については「障害者トライアル雇用の全ガイド|期間・求人・助成金を含む制度内容」の記事も参考になさってください。
4-4. 雇用した障がい者が定着しやすい環境を整える
障がいのある方を雇用できても安心せず、職場定着を支える管理体制をハード面とソフト面で整えていきましょう。
具体的な施策は職場によって異なりますので、ハローワークや地域障害者職業センターのジョブコーチ支援精度をうまく活用して進めていくのがおすすめです。
また、業務から切り出してお任せした仕事内容があっているかなどを定期的に確認し、相談しやすい関係性を築くことも重要です。
4-5. 採用・定着が難しい場合は民間の雇用支援サービスの活用も検討する
「障がい者枠で採用をかけても応募がない」「バリアフリーや受け入れ部署など環境整備が難しい」などでなかなか障がい者雇用枠での雇用が安定しない場合には、民間の雇用支援サービスの活用も検討しましょう。
前述したように、都市部では障がい者を雇いたい企業が多く、地方では働きたくても職場が見つからない障がい者が多いという雇用機会格差が生じています。
そのため、特に都市部では障がい者雇用の採用枠で募集をかけても、なかなか応募者が集まりにくい現状があります。こうしたケースをサポートできるのが民間の雇用支援サービスです。
例えば私どもJSHでは、障がい者雇用支援サービス「コルディアーレ農園」を通して、地方在住の就労意欲の高い障がい者を都市部の企業へご紹介するという取り組みを行っています。

地方創生による社会貢献を実現し、雇用した障がい者が安心して長く働けるような環境を作りたい企業様はぜひご相談ください。
| コルディアーレ農園をもっと知りたい方はこちら |
| コルディアーレ農園についての資料請求はこちら |
5. まとめ
本記事では、障がい者枠での雇用の現状や、雇用するための方法などについて解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。
従業員40人以上の企業は「障がい者枠」の雇用が必要
| ・従業員に占める障がい者の割合を2.5%以上にしなければならない
・従業員が多いほど「障がい者枠」の人数も増えていく |
障がい者雇用枠を満たせていない企業が多い(半数程度が未達成)
| ・法定雇用率を達成できている企業の割合は50.1%(2023年)
・都道府県によって障がい者雇用の難易度に格差がある |
障がい者雇用枠を満たすのが難しい理由
| ・障がい者にどの仕事を任せれば良いかが分からない
・障がい者が働きやすい環境を整えるのが難しい ・雇用しても短期間で離職されてしまう ・都市部では障がい者雇用の難易度が高い |
「障がい者雇用枠」での雇用を成功させる方法
| ・まずは障がい・障がい者雇用についての理解を深める(ハローワークを活用)
・具体的な部署や職種の検討を行う ・障がい者枠での採用活動を行う ・雇用した障がい者が定着しやすい環境を整える ・採用・定着が難しい場合は民間の雇用支援サービスの活用も検討する |
障がい者雇用枠での採用や定着が難しい、ノウハウがない、など何かお悩みの企業様がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽に資料請求からでもお問い合わせください。
おすすめ記事
-

詳細を見る
2026年2月10日
ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説
「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]
事例
-

詳細を見る
2026年1月16日
【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件
「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]
法律・制度
-

詳細を見る
2026年1月13日
水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説
「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]
法律・制度










