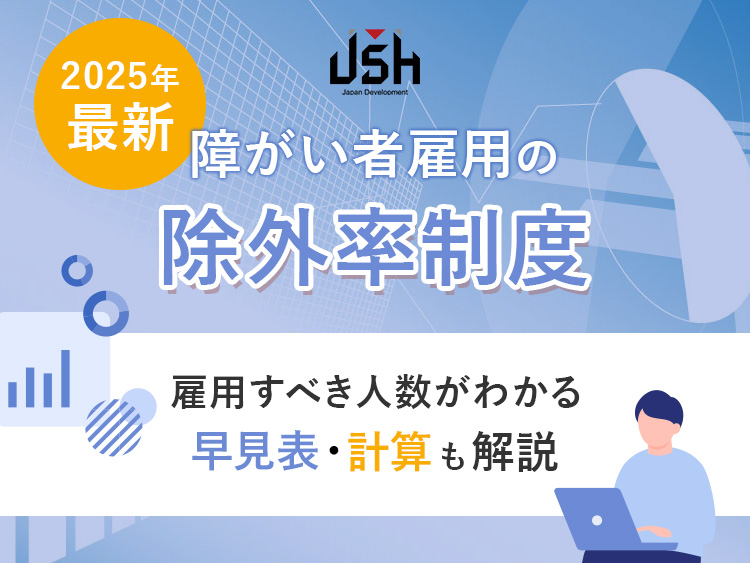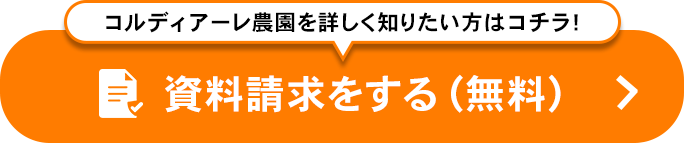コラム詳細
2025/02/20
autorenew2025/02/20
障がい者雇用における現場の声14選!よく上がる声から学ぶ成功の秘訣とは
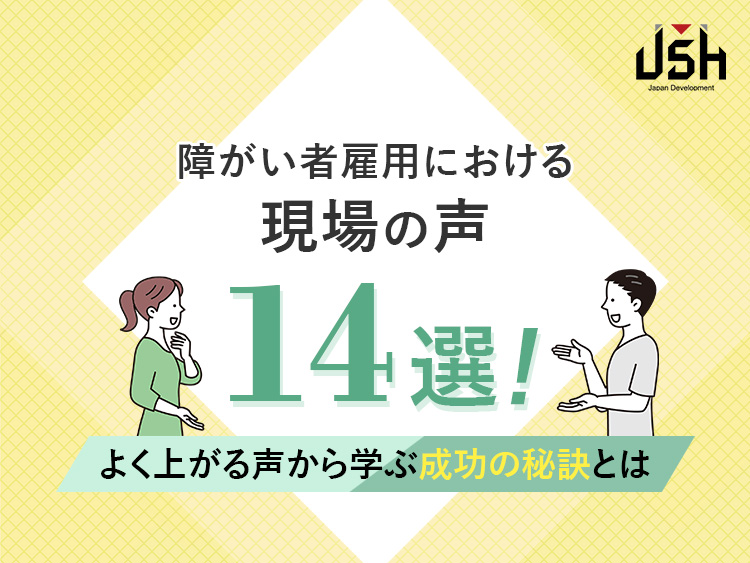
「障がい者雇用における現場の声はどのようなものがある?」
「障がい者雇用のリアルな現場の意見が聞きたい、知りたい」
これから自社でも障がい者雇用に向けた取り組みを始めるために、障がい者雇用におけるリアルな現場の声や課題を知りたいとお考えなのではないでしょうか。
先にお伝えすると、障がい者雇用における現場の声でよく上がるのが、以下の4パターンです。
| 関わり方に関する声 | 「適切なサポートやフォローが難しい」
「配慮の仕方が分からない」
「どう接したら良いか分からない」
「一緒に働く仲間であるという意識が持ちづらい」 |
| 業務の振り方に関する声 | 「お願いできる仕事が少ない」
「どのように業務を教えたらいいのか分からない」
「どの業務をやってもらったら良いか分からない」
「障がい者の適性や能力に見合った仕事を割り振れていない」 |
| 体調・メンタル面に関する声 | 「安定して出社できていない社員が多い」
「体調面の管理やフォローに不安がある」
「業務外のストレスによって業務に支障が出ている」 |
| 指導の仕方に関する声 | 「通常行っている業務をやってくれないことがある」
「生活態度や仕事に対する姿勢を注意しても伝わらない」
「注意したいことがあってもためらってしまう」 |
障がい者雇用の現場(受入部署)について現状をあらかじめ知っておけば、事前に対策を考えて実行することができます。
そこでこの記事では、よくあるパターン別に現場の声や、それぞれの声が上がりやすくなる背景をご紹介します。
さらに、そうした現場の声からわかる、障がい者雇用を成功に導くポイントも解説します。
この記事を読めば、障がい者雇用を行う企業の現場でどんな声があるのか、それに対してどのような対応ができるのか一通り把握することができます。
これから自社で障がい者雇用を進める前に、起こり得るリスクをできる限り減らしておきたい方は、ぜひ最後まで読み進めてください。
【目次】
1. 【関わり方】障がい者雇用の現場の声
2. 【業務の振り方】障がい者雇用の現場の声
3. 【体調・メンタル面】障がい者雇用の現場の声
4. 【指導の仕方】障がい者雇用の現場の声
5. 現場の声から読み解く障がい者雇用を成功に導くポイント
6. まとめ

障がい者の従業員と現場の従業員が、互いに理解し合えていない場合には、以下の通り、障がい者との関わり方に関する声が上がりやすいです。
| 関わり方に関する現場の声 |
| 「適切なサポートやフォローが難しい」
「配慮の仕方が分からない」
「どう接したら良いか分からない」
「一緒に働く仲間であるという意識が持ちづらい」 |
これまで障がい者を受け入れていなかった部署や現場が、初めて障がいのある従業員と共に働くとなると、どうしても理解の及ばない部分が出てきて、こうした声が挙がりやすくなるのです。
例えば、身体障がい者の中には、一見すると健常者と区別のつかない方もいらっしゃいます。
(身体内部の臓器に疾患等がある内部障がいがある方など)
そのような障がい者の方に対して、採用担当者から「適宜サポートや配慮を行ってください」とだけ指示されても、何をどうすれば良いのか分からないのは当然のことと言えます。
また、場合によっては、自分の力でできることに対してサポートを行ってしまい、トラブルの種となってしまうこともあるでしょう。

こうしたすれ違いが起こり、障がい者とそうでない従業員の間に距離ができて終えば、仲間意識を持つことも難しくなってしまいます。
このように、障がいのある従業員とそうではない現場従業員の間で相互理解が無いと、ご紹介したような声が上がってしまうことをご理解いただけるでしょう。

障がい者の従業員がどんな仕事をどれくらいできるのか把握できていない場合には、以下の通り、業務の振り方に関する声が上がりやすいです。
| 業務の振り方に関する声 |
| 「お願いできる仕事がない」
「どのように業務を教えたらいいのか分からない」
「どの業務をやってもらったら良いか分からない」
「障がい者の適性や能力に見合った仕事を割り振れていない」 |
そもそもひと口に障がい者と言っても、障がいの特性も違えば、本人の仕事に対する意向も異なります。
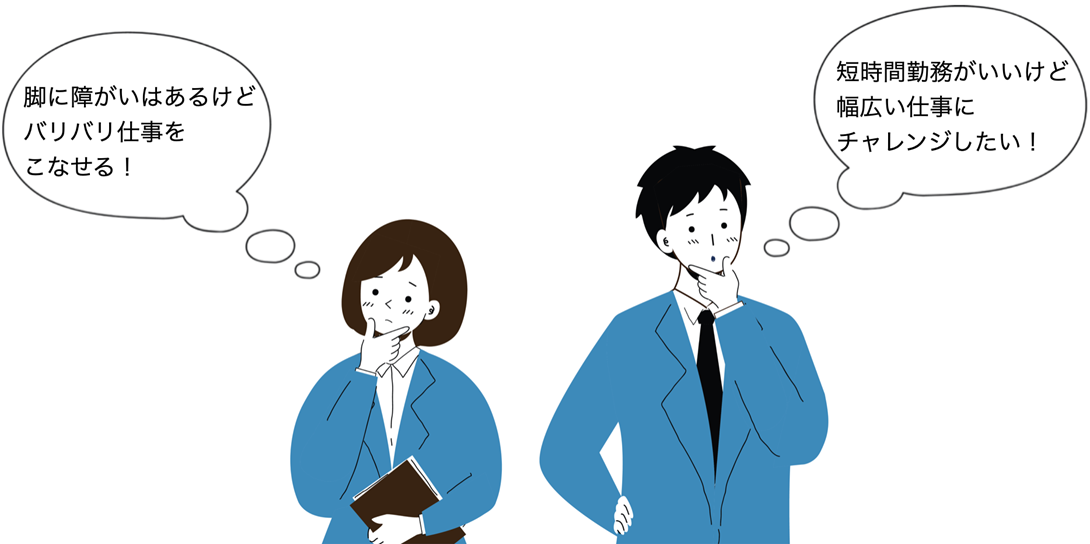
このように、一人ひとり、
・(障がい特性の観点から)行える業務、行えない業務
・働ける時間
・今後のキャリアアップへの意向
が異なるにも関わらず、本人にしっかりヒアリングを行っていないと、次のような状況が起こります。
| 障がい特性や仕事に対する意向を把握できていないと… |
| ・車椅子を利用しているものの、高ささえ合えば作業台で業務を行えるのに事務仕事しかできないと勘違いしてしまう
・知的障がいがあり発話はできなくても指示内容は理解できるのに、どう教えれば良いかわからない
・精神障がいはあるが、短時間勤務なら事務仕事をこなせるのに、単純作業に従事させる |
結果的に、現場において、業務の振り方に悩む声が上がりやすくなってしまうのです。

社内に障がい者の従業員をサポートする仕組みが構築できていない場合には、以下の通り、体調やメンタル面に関する不安の声が上がりやすいです。
| 体調・メンタル面に関する声 |
| 「安定して出社できていない社員が多い」
「体調面の管理やフォローに不安がある」
「業務外のストレスによって業務に支障が出ている」 |
障がいのある方は、健常者に比べると業務の負担が大きくなりやすい側面もありますが、そこに対してのサポートの仕組みがないと、共に働く現場の従業員も心配になってしまうのです。
例えば、精神障がいがある方の中には、だるさや疲れやすさを感じやすい方もいらっしゃいます。
そのような状態で通勤し、毎日業務をこなすのは、想像以上に負担の大きなことです。
このように、健常者の方が当たり前のように行えることでも、障がい者の方にとっては負担が大きい場合があるのです。
だからこそ、社内や働く現場にはそうした背景を汲んだサポート体制を構築するのが望ましいですが、現実的には難しい部分もあります。
その場合、現場の従業員が、障がい者の従業員の体調やメンタルを考慮する必要性が出てきますが、当然限界があります。
結果的に、うまく体調・メンタルの負担を考慮したサポートがうまくできなかったり、やり方がわからず、悩む声が上がりやすくなるのです。

現場で障がいに対する理解が足りていないと、指導の仕方に関する声が上がりやすいです。
| 指導の仕方に関する声 |
| 「通常行っている業務をやってくれないことがある」
「生活態度や仕事に対する姿勢を注意しても伝わらない」
「注意したいことがあってもためらってしまう」 |
障がいのある方には、障がい特性上、できること・得意なこともあれば、できないこともあります。
当然のことのように思われるかもしれませんが、障がい特性を理解していないと、この事実を忘れがちになり、次のような勘違いが起こる場合もあるのです。

本来は「できない」ところに対して、何ができるのかすり合わせて、その中で業務や改善の指導をすべきですが、こうした勘違いにより、「できる人に対して行う指導」をしてしまいがちです。
それではいつまで経っても状況は改善しませんから、現場の従業員は「指導をしてもやってくれない・改善してくれない」という思いを抱くようになります。
さらには、注意することさえやめてしまうケースもあるでしょう。

ここからは、現場の声から読み解く障がい者雇用を成功に導くポイントを深掘りしていきます。
| 障がい者雇用を成功に導くポイント |
| ・障がいの特性について障がい者者本人とよく話し合う
・支援機関と連携しながら進めていく |
それでは、1つずつ見ていきましょう。
5-1.障がいの特性について障がい者本人とよく話し合う
障がい者雇用を成功させる一番のポイントは、障がいの特性について障がい者本人とよく話し合うことです。
なぜなら、
・障がいの特性
・得意なことや苦手なこと
などは、障がいの種類や人によって違うからです。
例えば、「身体障がい」といっても、視覚障がい・聴覚障がいなど、障がいの度合いや内容は様々です。
そのため、できる業務内容もそれぞれ異なりますし、働く上で必要な配慮を行う場合にも、人によって本当に必要とする配慮の内容は異なります。
したがって、まずは障がい者本人とよく話し合い、障がいの特性や必要な配慮についてしっかりとすり合わせを行うことで、
・関わり方に関する現場の声
・業務の振り方に関する現場の声
・指導の仕方に関する現場の声
を未然に防ぎやすくなるはずです。
5-2.支援機関との連携しながら進めていく
次に、障がい者雇用を成功させるためには、支援機関との連携も重要になってきます。
自社だけで障がい者雇用を進めていく場合、サポートできる内容などにはどうしても限界があります。
障がいのある従業員が業務外に問題やストレスを抱えており、それが原因で業務に支障が出ている場合、企業側で対応できることでは解決しない可能性が高いです。
また、体調面の管理についても、適切なサポートは難しいと言えます。
障がい者の方の心身の安定を図るためには、例えば次のような対応が必要ですが、社内にこうした担当者を立てるのは、コストや労力を考えると難しい場合が多いでしょう。
・医療従事者を常駐させ、体調面のケアを行う
・障がい特性に詳しいカウンセラーがカウンセリングを行う
・障がい特性に応じたストレスケア
そのような場合は、積極的に外部の支援機関と連携するようにしましょう。
障がい者雇用専門の支援機関と連携することで障がい者の体調やメンタルに対するサポート体制の構築につながります。
その結果、
・関わり方に関する現場の声
・体調・メンタル面に関する現場の声
は上がりづらくなるでしょう。
具体的な支援機関や受けられるサポートは、以下の通りです。
| ハローワーク | ・法定雇用率達成のための助言や指導
・障がい者雇用に関する各種助成金の相談窓口 ・特例子会社設立の相談 |
| 地域障害者職業センター | ・ジョブコーチの派遣
・企業向けセミナーの開催 |
| 障害者就業・生活支援センター (通称なかぽつ) |
・障がい特性に応じた雇用や対応に関するアドバイス
・他の支援機関との連絡調整 |
| 特別支援学校 | ・卒業生の紹介
・卒業後3年間の職場定着支援 |
| 就労支援を行う民間企業 | ・人材紹介
・面接同行や選考のアドバイス ・職場定着に向けたカウンセリング |
障がい者雇用に取り組むうえで、自社だけでは適切にサポートを行う自信がないという場合は、こうした支援のもと、障がい者への理解を深め、適切なサポートを提供しましょう。
| 障がい者雇用支援サービスを活用するなら
JSHのコルディアーレ農園にご相談ください |
| 「自社で障がい者に適切なサポートや配慮を行うのは限界がある」
という場合は、ぜひJSHの障がい者雇用支援サービス『コルディアーレ農園』をご検討ください。
当社では、農園型の障がい者雇用支援サービスをご提供しているので、障がい者雇用に関することなら、何でもご相談いただければ幸いです。
JSHは、企業さまに屋内型農園の「コルディアーレ農園」の区画と水耕栽培設備を貸し出し、主に九州在住の障がい者人材をご紹介しています。
障がい者の方には環境が整備された農園で、葉物野菜やハーブなどの栽培に携わっていただいています。
コルディアーレ農園では、精神科勤務経験のある看護師が唯一常駐するなど、多数の有資格者による手厚いサポートがあるため、高い定着率を期待していただけます。
弊社の農園型障がい者雇用支援サービスを導入いただいている企業さまは200社弱で、その継続率は99%(2024年6月時点)にも上ります。
まずは、お気軽に下記ボタンからコルディアーレ農園の資料をご請求ください。
|
6.まとめ
この記事では「障がい者雇用における現場の声14選」と、現場の声からわかる障がい者雇用の成功ポイントをご紹介しました。
| 関わり方に関する声 | 「適切なサポートやフォローが難しい」
「配慮の仕方が分からない」
「どう接したら良いか分からない」
「一緒に働く仲間であるという意識が持ちづらい」 |
| 業務の振り方に関する声 | 「やってもらう仕事がない」
「どのように業務を教えたらいいのか分からない」
「どの業務をやってもらったら良いか分からない」
「障がい者の適性や能力に見合った仕事を割り振れていない」 |
| 体調・メンタル面に関する声 | 「安定して出社できていない社員が多い」
「体調面の管理やフォローに不安がある」
「業務外のストレスによって業務に支障が出ている」 |
| 指導の仕方に関する声 | 「通常行っている業務をやってくれないことがある」
「生活態度や仕事に対する姿勢を注意しても伝わらない」
「注意したいことがあってもためらってしまう」 |
| 障がい者雇用を成功に導くポイント |
| ・障がいの特性について障がい者者本人とよく話し合う
・支援機関と連携しながら進めていく |
これから障がい者雇用を進める方にとって、この記事がお役に立てることを願っています。
おすすめ記事
-
2025年7月7日
autorenew2025/07/07
【2025年最新】特定求職者雇用開発助成金の5つのコースと申請方法
「人手不足ではあるものの、採用や育成にかかるコストがネックになっている。助成金を調べていたところ“特定求職者雇用開発助成金”が目にとまったけれど、活用できるのか?」 「障がいのある方の雇用に活用できる助成金を調べていたら […]
詳細を見る
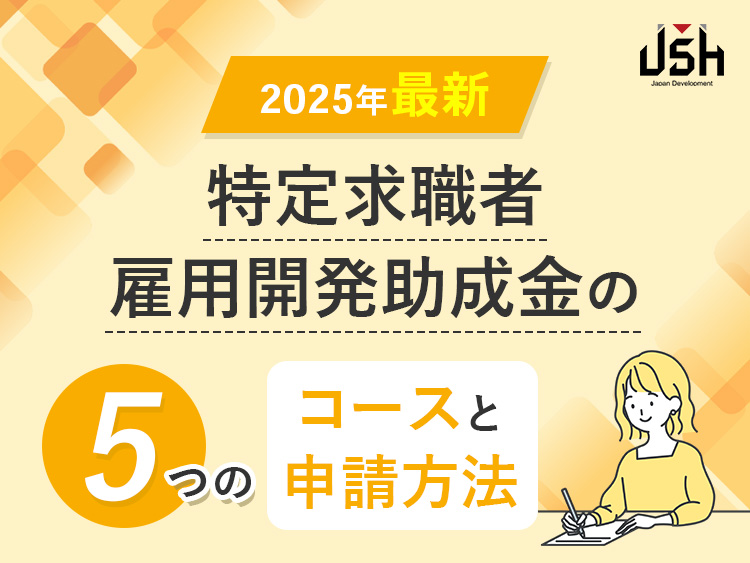
-
2025年7月3日
autorenew2025/07/03
地方創生2.0とは?1.0との違いや基本的な考え方を全解説
「ニュースで”地方創生2.0”という言葉を耳にした。企業として、どうやって携わっていくのか気になる」 「2025年から国が地方創生2.0に取り組むようだけど、企業としては何かするべき?どのようなことが求められるの?」 昨 […]
詳細を見る
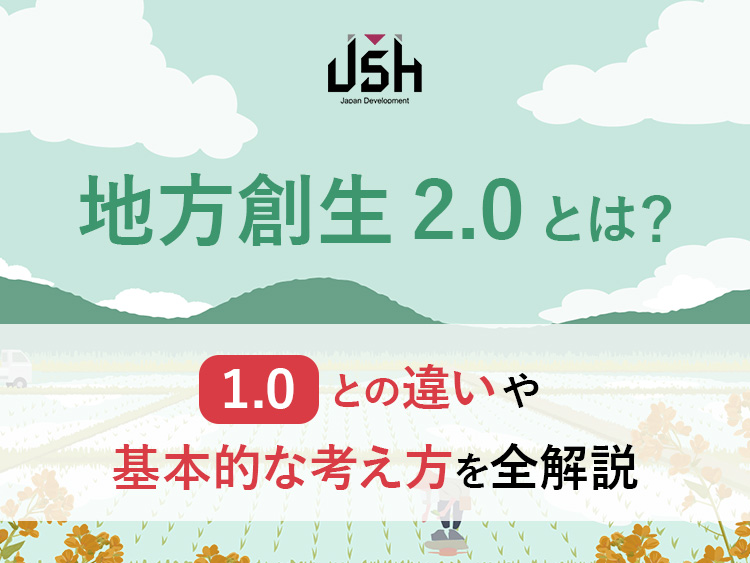
-
2025年7月3日
autorenew2025/07/03
【2025年最新】障がい者雇用の除外率制度|雇用すべき人数がわかる早見表・計算も解説
「障がい者雇用における除外率の一覧を見たい」 「除外率の一覧を確認したうえで、確実に法定雇用率の達成を目指したい」 2025年4月より、除外率が適用される業種や適用率が変更されたこともあり、このようにお考えなのではないで […]
詳細を見る