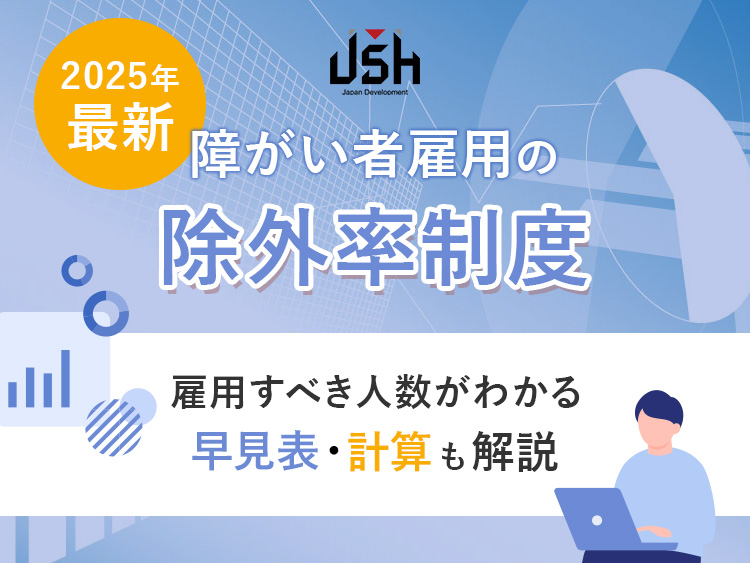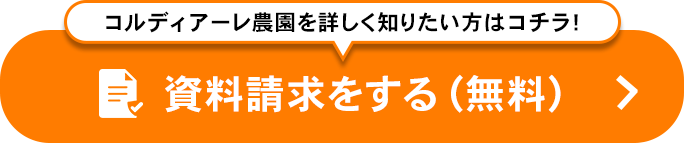コラム詳細
2025/02/20
autorenew2025/03/05
障がい者雇用の義務違反にはペナルティあり|違反リスクや対処法を解説
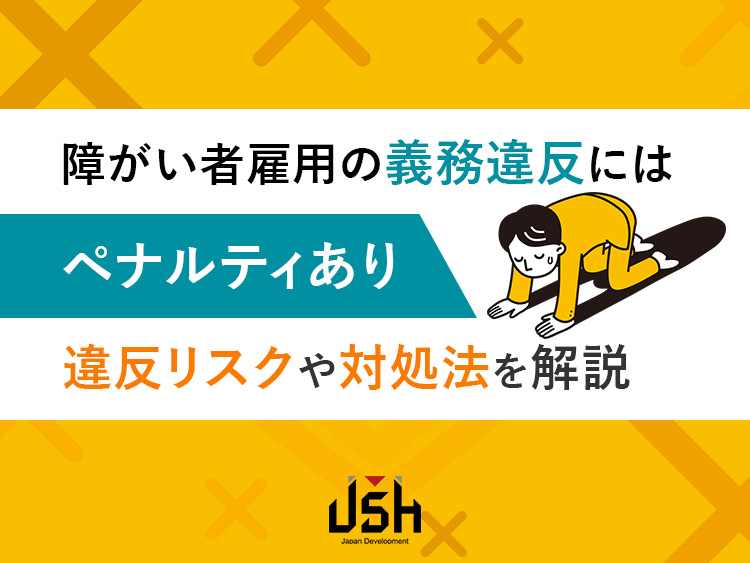
「障がい者雇用における法律や義務に違反するとどうなるのか?」
「違反することは自社にとってどんなリスクになるのだろうか?」
このように、障がい者雇用に関わる様々な規定や義務に違反してしまった場合、どうなるのかと今まさに不安を感じているのではないでしょうか。
一定規模以上の企業や事業主には、「障害者雇用促進法」に基づいて障がい者を雇用する義務があり、その義務を怠ったり目標値を達成できない場合は違反と見なされます。
そして、障がい者雇用の法的義務に違反した場合、企業には以下のようなペナルティが課せられます。
| 障がい者雇用における企業の義務 | 違反した場合のペナルティ |
| 障がい者を雇用する義務 |
・障害者雇用納付金を徴収される (不足人数1人につき月額50,000円) ・ハローワークから指導が入る ・企業名を公表される |
| 障がい者の雇用状況を届け出る義務 | ・30万円以下の罰金 |
| 差別の禁止と合理的配慮を提供する義務 |
・直接的な罰則はなし (虚偽の報告・報告を怠ると指導や罰金あり) |
※法定雇用率で算出された障がい者雇用の義務人数が5名以上の場合のみ、障がい者職業生活相談員を選任することも義務として定められています。
違反によるペナルティを受けた場合、企業は社会的なイメージや信用を大きく損なうリスクがありますし、障がいの有無に関わらず多様な人材が働きやすい企業であるために、法律はしっかり遵守すべきです。
そのためには、障がい者雇用の違反事項を明確に把握し、事前に違反対策を実施することが重要です。
そこでこの記事では、以下の内容を解説します。
| この記事で分かること |
| ・障がい者雇用の法的義務の内容
・法的義務を違反した場合のペナルティ ・法的義務の違反を避けるための施策 ・どうしても法的義務を守れなかった場合の対応 |
法律を遵守しながら安心して障がい者雇用を進めたいとお考えの方は、ぜひ最後まで読み進めてください。
【目次】
1. 障がい者雇用の法的義務に違反すると罰金や行政指導のペナルティが課せられる
2. 障がい者を雇用する義務に違反した場合の具体的なペナルティ
3. 障がい者雇用の状況を届け出る義務に違反した場合の具体的なペナルティ
4. 障がい者雇用の義務違反を避けるために行うべき3つの施策
5. 採用や定着がうまくいかず結果的に違反することになってしまった場合の対応
6. 法律を遵守して安定した障がい者雇用を目指すなら支援機関のサポートを利用しよう
7. まとめ
1.障がい者雇用の法的義務に違反すると罰金や行政指導のペナルティが課せられる

障がい者雇用において、企業や事業主には以下のような法的義務が課せられており、その義務に違反すると罰金や行政指導などのペナルティが課せられます。
| 障がい者雇用において企業や事業主に定められている法的義務 |
| ・障がい者を雇用する義務
・障がい者雇用の状況を届け出る義務 ・障がい者を差別せず、合理的配慮を提供する義務 |
※法定雇用率で算出された障がい者雇用人数が5名以上の場合のみ、障がい者職業生活相談員を選任することも義務として定められています。
これらの義務は、障がいの有無問わずお互いを尊重し合い、共生できる社会を実現するための「障害者雇用促進法」に基づいて定められています。
まずは自社が求められている義務の内容と、違反した場合のペナルティについてそれぞれ全容を把握しておきましょう。
1-1.障がい者を雇用する義務
企業や事業者には「常用従業員数に対して〇%の障がい者を雇用しなければならない」という義務があります。この割合を法定雇用率、法定雇用率を定めている法律を障害者雇用促進法と言います。
2025年2月現在の法定雇用率と、障がい者雇用義務の対象になる企業は以下の通りです。
| 法定雇用率 | 2.5% |
| 対象となる企業 | 常用している従業員数が40人以上の企業 |
しかし、2026年7月にはさらに法改正が予定されており、以下のように法定雇用率や対象企業の規模が変更されますので併せてご確認ください。
| 2026年6月まで | 2026年7月から | |
| 法定雇用率 | 2.5% | 2.7% |
| 対象となる企業 | 常用従業員数40人以上 | 常用従業員数37.5人以上 |
障害者雇用促進法の対象になっている企業は年に一度、障がい者の雇用情報をハローワークに届け出なければいけません。
その際に法定雇用率が達成されていない企業には、以下のようなペナルティが段階的に課せられます。
| 障がい者を雇用する義務に違反した場合のペナルティ |
| 1.障害者雇用納付金を徴収される
2.ハローワークからの指導が入る 3.企業名が公表される |
具体的なペナルティの内容は「2.障がい者を雇用する義務に違反した場合の具体的なペナルティ」でも解説していますので、詳しくはそちらをご覧ください。
1-2.障がい者雇用の状況を届け出る義務
障害者雇用促進法において常用従業員数40名以上の企業には、毎年6月1日時点での障がい者の雇用状況を届け出ることが義務付けられており、これを「ロクイチ報告」と呼びます。
ロクイチ報告の詳細は以下の通りです。
| ロクイチ報告で報告書に記入すること | |
| 事業主の情報 | ・企業名
・代表者氏名 ・住所 など |
| 雇用の状況 | ・常用労働雇用者の人数
・常用身体障がい者・精神障がい者・知的障がい者の人数 ・実雇用率 など |
| その他 | ・特定の身体障がい種類ごとの人数
・障がい者雇用を推進する担当者の役職名や氏名 ・書類記入者の所属部課名や氏名 |
参照:厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領等・様式第6号(PDF)」
このロクイチ報告は、例え雇用している障がい者の人数が0であっても必ず報告しなければなりません。
もし報告書を提出しなかったり、虚偽の報告を行った場合は30万円以下の罰金が科せられますので、必ず期日の7月15日までに正確な内容を報告してください。
具体的なペナルティの内容は「3.障がい者雇用の状況を届け出る義務に違反した場合の具体的なペナルティ」でも解説していますので、詳しくはそちらをご覧ください。
1-3.障がい者差別の禁止、合理的配慮を提供する義務
障害者雇用促進法では、企業や事業主に障がい者差別の禁止と合理的配慮を提供することも義務付けられています。
それぞれの具体的な内容は、以下の通りです。
| 障がい者差別の禁止 | ・障がい者だからという理由で採用を拒否しないこと
・障がい者のみに不利な条件を設けないこと ・障がいのない人を優先しないこと |
| 合理的配慮を提供する義務 | ・車椅子利用者のために机や作業台の高さを調整する
・知的障がい者が分かりやすい写真や図を使ってマニュアルを作成する |
参照:厚生労働省「雇用の分野における障害者への差別禁止・合理的配慮の提供義務」
差別の禁止や合理的配慮を提供する義務は、企業規模や業種を問わず全ての企業が対象になっており、どのような配慮を行うかは、障がい者本人と事業主が話し合って決めることになります。
しかし、合理的配慮はあくまでも事業主の過度な負担とならない範囲で行うものとされていて、その範囲を逸脱しての配慮は義務を負う必要はありません。
障がい者差別の禁止や合理的配慮を提供する義務自体は「障害者雇用促進法」によって定められたものですが、違反した場合の直接的な罰則やペナルティは今のところ設けられていません。
ただし違反があった場合、行政機関からの指導や勧告が入るため、企業のイメージダウンにつながり、障がい者雇用を推進しづらくなってしまいます。
したがって、罰則がないからといって後回しにするのではなく、しっかりと企業の義務を果たせるような取り組みを行うことが必要です。
| 【企業や事業主に求められている努力義務】
企業や事業主には、障がい者雇用における法的義務以外にも努力義務として以下のような取り組みが求められています。
・障がい者雇用の促進や継続を図るための担当者を選任すること ・障がい者の職業能力の開発や向上に努めること
上記の取り組みは、違反したからといって直接的な罰則やペナルティはありません。
しかし、努力する姿勢が見られなかったり取り組みを怠っていると、行政指導や罰金の対象になる可能性がありますので、企業や事業主の義務としてしっかり取り組んでいく必要があります。
企業や事業主に求めれられている努力義務について、より詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
参考記事:「障害者雇用の5つの努力義務とは│怠った場合の罰則や影響・取組事例」 |
2.障がい者を雇用する義務に違反した場合の具体的なペナルティ

2章では、障害者雇用促進法で定められている「障がい者を雇用する義務」に違反した場合のペナルティやその内容について解説します。
具体的には、以下のようなペナルティが段階的に科されることになります。
| 障がい者を雇用する義務に違反した場合の具体的なペナルティ |
| 1.障害者雇用納付金を徴収される
2.ハローワークからの指導が入る 3.企業名が公表される |
それでは、1つずつ詳しく見ていきましょう。
2-1.障害者雇用納付金を徴収される
障がい者雇用において法定雇用率が達成できなかった場合、企業はまず「障害者雇用納付金」と呼ばれる納付金を支払わなければなりません。
障害者雇用納付金とは、障がい者雇用における事業主同士の経済的負担のバランスを調整するために設けられた制度で、障がい者雇用のための様々な助成金・給付金の財源になっています。
障がい者を雇用する義務に違反した企業のうち、対象になる企業と具体的に支払う金額は以下の通りです。
| 納付金徴収の対象となる企業 | 常用従業員が100人を超える企業 |
| 納付金額 | 法定雇用率の達成に不足している人数 × 月額50,000円 |
納付金額は年間の不足人数を合計して算出され、翌年度の4月1日〜5月15日までの間に一括で支払う必要があります。
例えば、1年間を通して毎月3人の障がい者雇用の人数が不足していた場合、
| 3人 × 50,000円 × 12ヶ月 = 1,800,000円 |
の納付金を一括で支払わなければなりません。
障害者雇用納付金は罰金ではなく、納付金を納めたからといって障がい者雇用の義務が免除されたわけではありません。
また、長い間法定雇用率が未達成の状態が続くと、ハローワークからの指導や企業名公表の対象になるリスクが高くなります。
指導や企業名公表については以下よりさらに詳しく解説していますので、このまま読み進めてください。
2-2.ハローワークからの指導が入る
障がい者雇用において、毎年6月1日の時点で法定雇用率が未達成の企業は、ハローワークから指導が入ることになります。
指導の対象になる企業の条件は、以下の通りです。
| 法定雇用率未達成の企業の中で行政指導の対象になる条件 |
| ・実雇用率が全国平均実雇用率未満で、かつ不足人数が5人以上の場合
・実雇用率に関係なく、不足人数が10人以上の場合 ・雇用義務数が3〜4人の企業で、雇用障がい者の人数が0人の場合 |
特に、不足人数が10人以上の企業は、企業の規模に関わらず行政指導の対象となる可能性が高くなります。
行政指導の対象となってしまった場合、まずはハローワークから2年間の「雇入れ計画書」の作成と提出を命じられ、その計画書に沿って障がい者雇用を進めていかなければなりません。
雇入れ計画書の作成から2年経っても雇用状況が改善されない場合は、さらに9ヶ月間の「特別指導」が行われることになります。
特別指導では、
| ・対象の企業に対して雇用事例の提供やアドバイスを行う
・求職情報の提供や面接会への参加を勧められる |
など、障がい者雇用に向けたさらに具体的な指導が行われます。
2-3.企業名が公表される
ハローワークからの2年9ヶ月の指導期間を経てもなお法定雇用率が達成できない場合には、未達成企業として厚生労働省のホームページなどで企業名を公表されることになります。
過去10年の間で実際に23社の企業が企業名を公表されており、これは障害者雇用促進法の第47条に基づいて定められていることです。
企業名が公表されてもなお雇用状況が改善されない場合には、再びハローワークからの行政指導を受けることになり、それでも改善されない場合には企業名を再公表されます。実際に、過去10年間で企業名を公表された23社のうち、4社は企業名の再公表に至った企業です。
企業名を公表されることで起こり得るリスクや影響は、以下の通りです。
| 企業名を公表されることで起こり得るリスクや影響 |
| ・企業の社会的責任を果たしていないと思われ、企業のイメージダウンに繋がる
・ニュース記事やブログなどで情報が拡散され、半永久的に情報が残り続ける ・企業のイメージダウンにより、障がいの有無に関わらず優秀な人材を確保しづらくなる ・企業で働く従業員のモチベーションダウンにも繋がる ・取引先の新規開拓が困難になる可能性が高くなる |
上記の通り、企業名が公表されてしまうと企業は大きなダメージを受けてしまいます。
こうしたリスクを回避する意味でも、障がい者を雇用する義務に違反しないことは重要なのです。
3.障がい者雇用の状況を届け出る義務に違反した場合の具体的なペナルティ

障害者雇用促進法で定められている「障がい者雇用の状況を届け出る義務」に違反した場合には、30万円以下の罰金が科せられます。
障がい者雇用の状況を届け出る義務において、具体的に罰金の対象になるのは以下のような行動です。
| 障がい者雇用の状況を届け出る義務において罰金の対象になる行動 |
| ・障がい者雇用の状況を報告しない
・障がい者雇用の状況を報告するにあたり、虚偽の届け出をする |
障害者雇用促進法の第5章には罰則に関する規定が記載されており、これらの罰金は障害者雇用促進法第5章の内容に基づいたものであることを理解しておきましょう。
| 【障がい者雇用において罰金の対象になるその他の事例】
障がい者雇用において、罰金の対象になるのは「障がい者雇用の状況を届け出る義務」以外にも以下のような事例が挙げられます。
・ハローワークからの「雇入れ計画」に対して計画書の作成・提出をしない ・障がい者を解雇する際に「解雇届」を提出しない ・行政からの立入調査に協力しない
上記のように、ハローワークからの指導や立入調査に協力せず、障がい者雇用における企業の義務の義務を果たす努力をしない場合も30万円以下の罰金の対象になります。 |

ここまでは、障がい者雇用における法的義務に違反した場合の具体的な罰則やペナルティについて解説してきました。
結論からお伝えすると、一番いいのは企業が社会的責任をきちんと果たし、法律違反にならないようにすることです。
そこで4章では、障がい者雇用における違反を避けるために行うべき3つの施策について解説していきます。
| 障がい者雇用の義務違反を避けるために行うべき3つの施策 |
| ・採用活動の強化
・職場環境や社内体制の整備 ・職場定着の強化 |
それでは、以下より詳しく見ていきましょう。
4-1.採用活動の強化
障がい者雇用の義務違反を避けるためには、まず採用活動を行って障がい者を雇用する必要があります。
そのために、採用準備・採用活動・受け入れ準備の段階で気をつけるべきポイントを以下にまとめました。
| 採用準備 | ・法定雇用率の達成に必要な雇用人数を明確にする
・障がい者雇用における企業の方針を決めて社内に共有する ・障がい者が適正を発揮できる業務を切り出す ・業務内容や配属先を決めて、どんな人材を募集するかを決める |
| 採用活動 | ・ハローワークや特別支援学校、就労支援機関などと連携して人材を募集する
・採用前に実習やインターンシップを実施して、ミスマッチを防ぐ ・面接時には、障がいの状況や通院頻度、必要な配慮についてヒアリングする |
| 受け入れ準備 | ・入社する障がい者の特性や必要な配慮について、事前に社内に共有する
・配属先の従業員に対して事前研修を行う |
障がい者雇用における採用活動で最も重要なのは、企業と応募者の適切なマッチングを図ることです。
双方にとって最適なマッチングができていれば、企業側は過度な負担を強いられずとも障がい者を雇用でき、応募者側も安心して働けるため安定した雇用にも繋がります。
そのためには、企業側は業種に応じた適切な業務の切り出しを行い、障がい者が適切に能力を発揮できるような体制を整えておくことが必要です。
また、採用前に職場実習やインターンシップなどを実施することも効果的で、企業側・応募者それぞれが入社した際の具体的なイメージを持ちやすくなるため、大幅なミスマッチを防げる可能性が高くなります。
4-2.職場環境や社内体制の整備
採用活動を通して人材を確保することができたら、職場環境や社内体制を整備しなければなりません。
どんな環境整備や配慮が必要なのかは、障がいの特性や個人によって様々です。そのため、環境や体制の整備にあたっては障がい者本人とよく話し合い、本人が本当に必要としている配慮の内容について十分なすり合わせを行うことが最も重要です。
職場環境や社内体制の整備としてできる具体的な取り組みには、以下のようなものがあります。
| 職場環境の整備 | ・エレベーターやスロープを設置する
・トイレのバリアフリー化を行う ・自動ドアを導入する ・フレックス制や在宅勤務などの制度を設ける |
| 社内体制の整備 | ・障がい者雇用の目的や必要な配慮について社内で情報を共有する
・専門の相談員を配置するなど、気軽に相談できる仕組みを作る |
職場環境や社内体制を整備しておくことで新たな人材の受け入れ体制を整えるとともに、現在障がい者雇用で働いている従業員にとってもより働きやすい環境になります。
4-3.職場定着の強化
障がい者雇用において、早期離職を防ぎ安定した雇用を行うためには、職場で長く働いてもらえるような取り組みを行うのも重要です。
障がい者雇用の職場定着を強化するための具体的な取り組みは、以下のようなものがあります。
| 障がい者雇用の職場定着を強化するための取り組み |
| ・必要な配慮について、本人と定期的な面談やヒアリングを行って把握・実施する
・職業生活相談員などを配置して、職場での困り事を気軽に相談できる体制を整える ・専門の支援機関と連携して、必要に応じた支援やアドバイスを受ける ・障がいのある従業員を適切に評価し、能力に応じた昇給・キャリアアップを行う |
障がいのある従業員を適切に評価したり能力に応じた昇給・キャリアアップを行うことは、障がい者本人にとって働く意欲やモチベーションを維持することに繋がります。
5.採用や定着がうまくいかず結果的に違反することになってしまった場合の対応

もし、採用や職場定着が上手くいかず結果的に法律に違反することになってしまった場合は、「2.障がい者を雇用する義務に違反した場合の具体的なペナルティ」でも解説した納付金の支払いやハローワークからの指導に従いましょう。
納付金の未申告や未払い・ハローワークからの指導に従わない場合には、30万円以下の罰金が科せられる対象になってしまいます。
また、法定雇用率がいつまで経っても未達成の場合には、最悪の場合企業名が公表されることになります。企業名を公表されてしまうと企業にとって大きなリスクや悪影響があるため、できれば避けたいところです。
障がい者の雇用状況を一刻も早く改善するためには、ハローワークからの指導に従うのはもちろん、「4.障がい者雇用の義務違反を避けるために行うべき3つの施策」でも解説した施策を試してみることがおすすめです。
6.法律を遵守して安定した障がい者雇用を目指すなら支援機関のサポートを利用しよう

法定雇用率の達成や法的義務の遵守に向けた取り組みを行う際、自社だけではどうしても改善や対応が難しいと感じたら、専門の支援機関に頼るもの選択肢の一つです。
障がい者雇用における代表的な支援機関と、企業に向けて提供しているサポートは以下の通りです。
| ハローワーク | ・法定雇用率達成のための助言や指導
・障がい者雇用に関する各種助成金の相談窓口 ・特例子会社設立の相談 |
| 地域障害者職業センター | ・ジョブコーチの派遣
・企業向けセミナーの開催 |
| 障害者就業・生活支援センター (通称なかぽつ) |
・障がい特性に応じた雇用や対応に関するアドバイス
・他の支援機関との連絡調整 |
| 特別支援学校 | ・卒業生の紹介
・卒業後3年間の職場定着支援 |
| 就労支援を行う民間企業 | ・障がい者人材の紹介
・面接同行や選考のアドバイス ・職場定着に向けたカウンセリング |
上記のような専門の支援機関と連携することで、法律を遵守することはもちろん安定した障がい者雇用を実現することができます。
障がい者雇用や法的義務を守るために困ったことがあれば、積極的に利用するのがおすすめです。
| 【法律を遵守し安定した障がい者雇用の実現を目指すなら、株式会社JSHにご相談ください】
安定した障がい者雇用の取り組みを進めていく中で、自社のみでの対応に限界を感じるなら、株式会社JSHにご相談ください。
株式会社JSHでは、「地方在住の働く意欲のある障がいのある方」と「障がい者を雇用したい企業」を繋ぐ農園型障がい者雇用支援サービス「コルディアーレ農園」を運営しています。
コルディアーレ農園では、障がいのある方がいきいきと働けるような快適な職場環境を提供することで、安定した障がい者雇用をサポートします。
一例としては、精神科勤務経験のある看護師が唯一常駐するなど、多数の有資格者による手厚いサポートがあり、高い定着率を期待していただけます。
障がい者雇用における採用活動や、職場定着への不安・負担を軽減したいとお考えの企業様は、ぜひ以下より詳細をご確認ください。
|
7.まとめ
この記事では、「障がい者雇用の義務に違反した場合」について解説してきました。
企業や事業主には、「障害者雇用促進法」によって障がい者を雇用する義務があり、その義務を怠ったり目標値を達成できない場合は違反と見なされます。
企業に定められた義務と違反した場合の具体的なペナルティは、以下の通りです。
| 障がい者雇用における企業の義務 | 違反した場合のペナルティ |
| 障がい者を雇用する義務 |
・障害者雇用納付金を徴収される ・ハローワークから指導が入る ・企業名を公表される |
| 障がい者の雇用状況を届け出る義務 | ・30万円以下の罰金 |
| 差別の禁止と合理的配慮を提供する義務 |
・直接的な罰則はなし (ただし、行政からの指導が入る可能性あり) |
特に、法定雇用率の未達成企業として企業名を公表された場合、企業の社会的信用やイメージを損なうなどのリスクがあるため、企業名の公表だけは何としても避けなければなりません。
そのために、企業が行うべき3つの施策は以下の通りです。
| 障がい者雇用の義務違反を避けるために行うべき3つの施策 |
| ・採用活動の強化
・職場環境や社内体制の整備 ・職場定着の強化 |
しかし、障がい者雇用に向けた採用活動や職場の定着が上手くいかず、その結果違反となってしまった場合は、障害者雇用納付金の支払いとハローワークからの指導に従いましょう。
障がい者雇用に向けた採用活動や職場への定着にお悩みの方は、株式会社JSHが運営する農園型障がい者雇用支援サービス「コルディアーレ農園」のご利用もご検討ください。
おすすめ記事
-
2025年7月7日
autorenew2025/07/07
【2025年最新】特定求職者雇用開発助成金の5つのコースと申請方法
「人手不足ではあるものの、採用や育成にかかるコストがネックになっている。助成金を調べていたところ“特定求職者雇用開発助成金”が目にとまったけれど、活用できるのか?」 「障がいのある方の雇用に活用できる助成金を調べていたら […]
詳細を見る
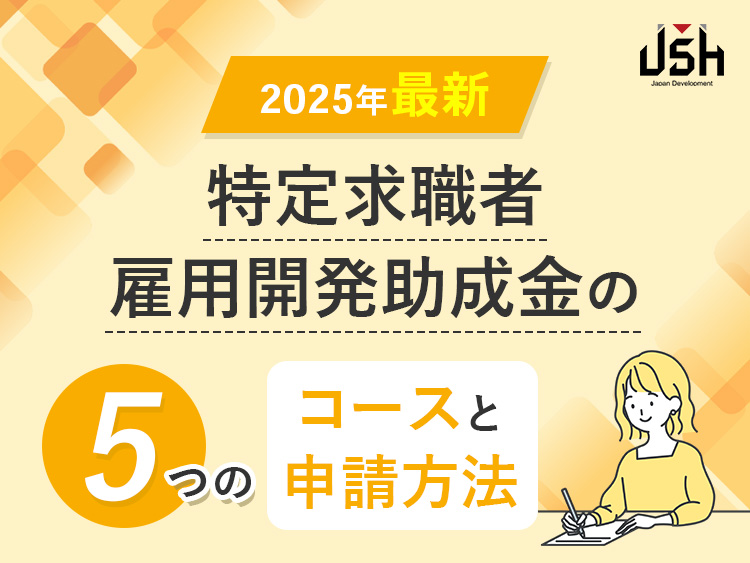
-
2025年7月3日
autorenew2025/07/03
地方創生2.0とは?1.0との違いや基本的な考え方を全解説
「ニュースで”地方創生2.0”という言葉を耳にした。企業として、どうやって携わっていくのか気になる」 「2025年から国が地方創生2.0に取り組むようだけど、企業としては何かするべき?どのようなことが求められるの?」 昨 […]
詳細を見る
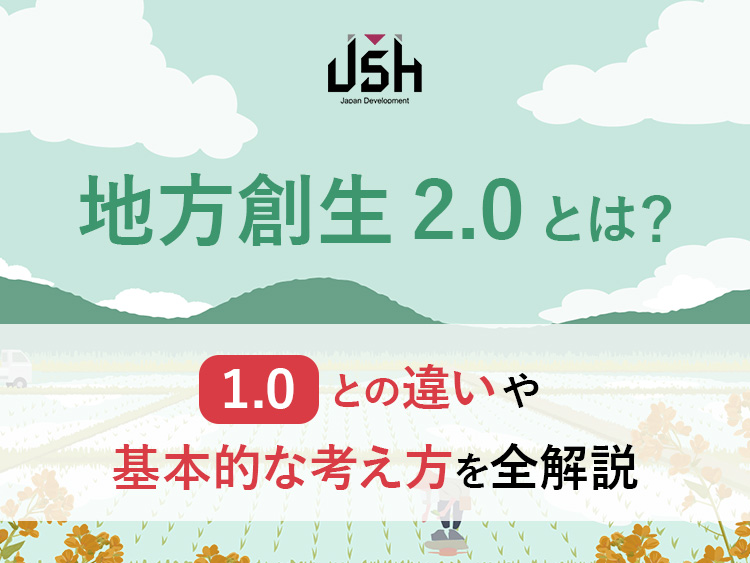
-
2025年7月3日
autorenew2025/07/03
【2025年最新】障がい者雇用の除外率制度|雇用すべき人数がわかる早見表・計算も解説
「障がい者雇用における除外率の一覧を見たい」 「除外率の一覧を確認したうえで、確実に法定雇用率の達成を目指したい」 2025年4月より、除外率が適用される業種や適用率が変更されたこともあり、このようにお考えなのではないで […]
詳細を見る