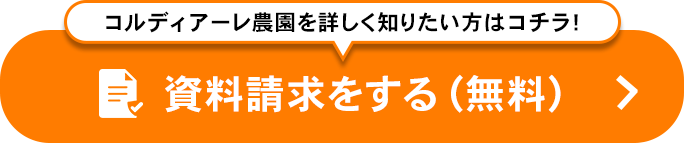コラム詳細
2025/03/17
autorenew2025/11/25
法定雇用率の算定対象となる難病患者は障害者手帳所持者のみ!ルールを解説
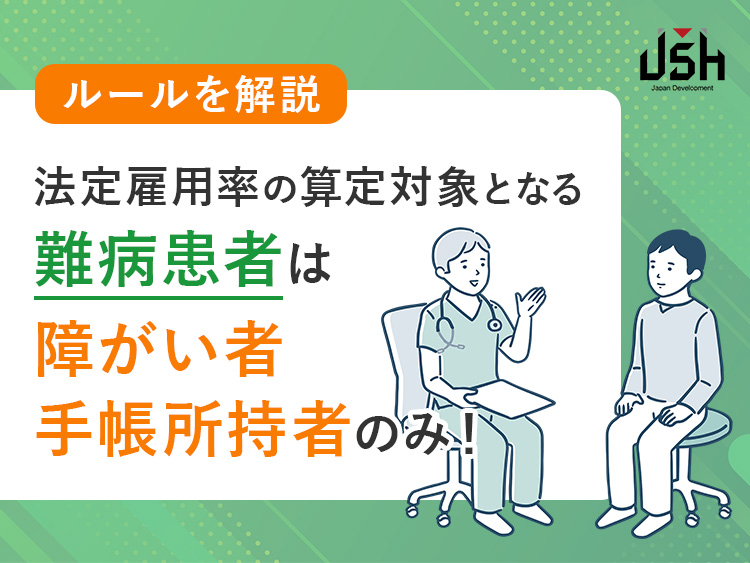
「自社で障がい者雇用の法定雇用率を達成したいが、難病患者は算定されるのか?」
「難病患者の方が法定雇用率に算定されるのであれば、積極的に雇用を検討するのだけれど……」
障がい者雇用を進めている企業の方が、障がい者人材の募集・採用活動を行っている時に、難病患者の方からの応募があるなどして、法定雇用率に算定されるのか知りたくなり、検索したのではないでしょうか。
結論から申し上げますと、障がい者手帳を持っている難病患者の方であれば、法定雇用率に算定されますが、持っていない方は算定されません。
現状、法定雇用率の算定対象となるのは、以下のいずれかの障がい者手帳を所持する障がい者の方のみだからです。
| 身体障がい者 | 身体障害者手帳 |
| 知的障がい者 | 療育手帳 |
| 精神障がい者 | 精神障害者保健福祉手帳 |
厚生労働省「障害者雇用率制度・納付金制度について関係資料」によると、難病患者のうち、障がい者手帳を所持しているのは、約56%です。
障がい者手帳の有無に関わらず、難病患者の方の採用はもちろん可能ですが、難病患者だからと言って、必ずしも法定雇用率に算定される訳ではありません。
この記事では、以下のポイントについて、詳しくご紹介します。
| この記事で分かること |
| ・法定雇用率に算定される難病患者は、障がい者手帳を持つ方のみ
・難病患者を法定雇用率の対象にするよう、働きかける動きがある ・難病患者が法定雇用率の対象になる予定はなし(2024年11月現在) ・法定雇用率の算定対象となる、障がい者雇用のハードルは年々上がっている ・障がい者雇用が難しいと感じたら、社外の支援サービスを積極的に利用すべき |
障がい者雇用における法定雇用率の算定対象を理解し、あなたの企業で達成できるように、ぜひ最後まで読み進めていただけると幸いです。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
【目次】
1. 法定雇用率に算定される難病患者は障がい者手帳を持つ方のみ
2. 難病患者を法定雇用率の対象にするよう働きかける動きもある
3. 難病患者が法定雇用率の対象になる予定はなし(2024年11月現在)
4. 法定雇用率の達成を目指すなら多様な障がい者を雇用できる体制が必要
5. 障がい者雇用の体制整備には社外の支援サービスも積極的に利用しよう
6. まとめ
1. 法定雇用率に算定される難病患者は障がい者手帳を持つ方のみ
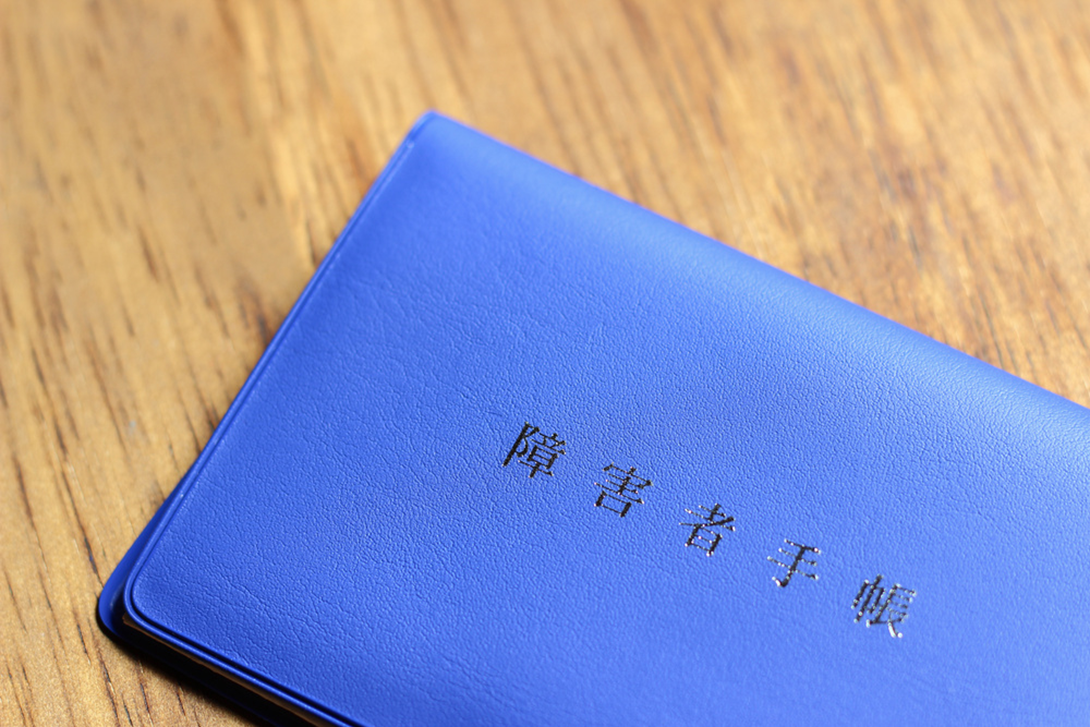
冒頭でもお伝えした通り、法定雇用率に算定される難病患者は、障がい者手帳を持つ方のみです。
法定雇用率に算定するルールを理解するために、参考にしてみましょう。
1-1.「難病患者である」だけでは算定されない
法定雇用率には、「難病患者である」という理由だけでは、算定されません。
なぜなら、障害者雇用促進法では、「従業員が一定数以上の規模の事業主は従業員に占める身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の割合を『法定雇用率』以上にする」と、義務付けられているからです。
この「身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者」とは、障がい者手帳を所持しているかで判断します。
障がいがあっても、程度が非常に軽い方が障がい者手帳の取得が難しいのと同様に、難病患者の方であっても、取得できる方もいればできない方もいるのです。
そのため、難病患者の方は、障がい者手帳を所持していなければ、法定雇用率には算定されません。
1-2. 障がい者手帳を所持する難病患者は約56%
厚生労働省「障害者雇用率制度・納付金制度について関係資料」によると、難病患者のうち、障がい者手帳を持つ方は約56%です。
難病として指定されている疾病は341(2024年11月現在)ありますが、その多くが身体機能に影響する症状が出るため、難病患者の方と障がい者手帳は実は密接な関係にあるのです。
指定難病のうち、医療費助成の受給者数が多い以下の疾病は以下の3つですが、どれも深刻な身体障がいを伴いやすくなります。
| 潰瘍性大腸炎 | 【症状】
・大腸の粘膜にびらんや潰瘍ができ、血便を伴う下痢や激しい腹痛などが現れる
【発生しやすい障がい】 ・内部障がい(直腸の機能障がい) |
| パーキンソン病関連疾患 | 【症状】
・手の震えや動作や歩行の困難など、運動障がいを示す ・進行すると、自力歩行が困難になり、車いすや寝たきりになる場合がある
【発生しやすい障がい】 ・肢体不自由 |
| 全身性エリテマトーデス | 【症状】
・自分自身の体を免疫系が攻撃してしまい、全身のさまざまな場所に赤い発疹ができる ・発熱、全身倦怠感などと、関節、皮膚、腎臓、肺、中枢神経などの内臓のさまざまな症状が一度に、あるいは経過とともに起こる
【発生しやすい障がい】 ・内部障がい(じん臓機能障がい、呼吸器機能障がいなど) |
このように、難病の症状が身体障がいに繋がるケースが多く、約56%の障がい者手帳を所持している方については、法定雇用率の算定が可能です。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
2. 難病患者を法定雇用率の対象にするよう働きかける動きもある

難病患者の方のうち、法定雇用率に算定される障がい者手帳を持つ方は約56%なので、裏を返せば、約44%の方は障がい者手帳を「取得していない」、もしくは「取得したくてもできない」状況です。
どうして難病患者の方の中に、そのような方がいるのかというと、障がい者手帳を取得するには、基本的には「症状が固定していて、回復の見込みがない状態」が求められるからです。
しかしながら、難病患者の方は、症状が悪化する時もあれば、一時的に良くなる時もあって、症状が固定せず、障がい者手帳の取得が難しい場合があります。
その点を受けて、障がい者手帳の有無に関わらず、難病患者の方を法定雇用率の対象にするよう働きかける動きが出てきました。
主だったものは、以下の通りです。
| 2015年
日本弁護士連合会 |
・障がい者手帳を持たない難病患者を、雇用義務の対象とするように求める意見書を公表
・「難病があっても周囲の理解や配慮があれば、しっかりとした仕事ができる」と主張 |
| 2022年
衆参両院 |
・障害者総合支援法改正時の付帯決議で、雇用率制度における難病患者の扱いの検討を求める
・政府は難病患者の実態を把握するための調査に着手し、結果を踏まえて、2024年度以降に制度見直しに向けた検討を進めている |
| 2024年5月
日本難病・疾病団体協議会 |
・参議院議員会館を訪れ、超党派の国会議員に約36万人分の署名とともに嘆願書を手渡す
・難病患者の就労拡大に向けて、国が企業に対して義務付けている障がい者雇用の法定雇用率の算定対象に含めることを求める |
このように、難病患者の法定雇用率への算定を求める働きかけがあり、いずれは状況が変わる可能性があるものの、現時点では変わっていません。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
3. 難病患者が法定雇用率の対象になる予定はなし(2024年11月現在)

難病患者を法定雇用率の対象にするよう、働きかける動きはあるものの、2024年11月現在、政府による具体的な検討結果や予定については、まだ発表されていません。
既存のルールを変えるのは時間がかかる上に、一度変えたルールはすぐには元に戻せないため、各所からデータや意見を取りまとめて、慎重に検討中であると考えられます。
繰り返しにはなりますが、現時点で法定雇用率に算定できるのは、障がい者手帳を所持する身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者のみです。(難病患者も障がい者手帳があれば算定可能)
そのため、難病患者の方を受け入れるサポート体制がない企業が、「今後、算定対象になる可能性があるから」というような見通しで雇用を始めるのは、おすすめできません。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
4. 法定雇用率の達成を目指すなら多様な障がい者を雇用できる体制が必要
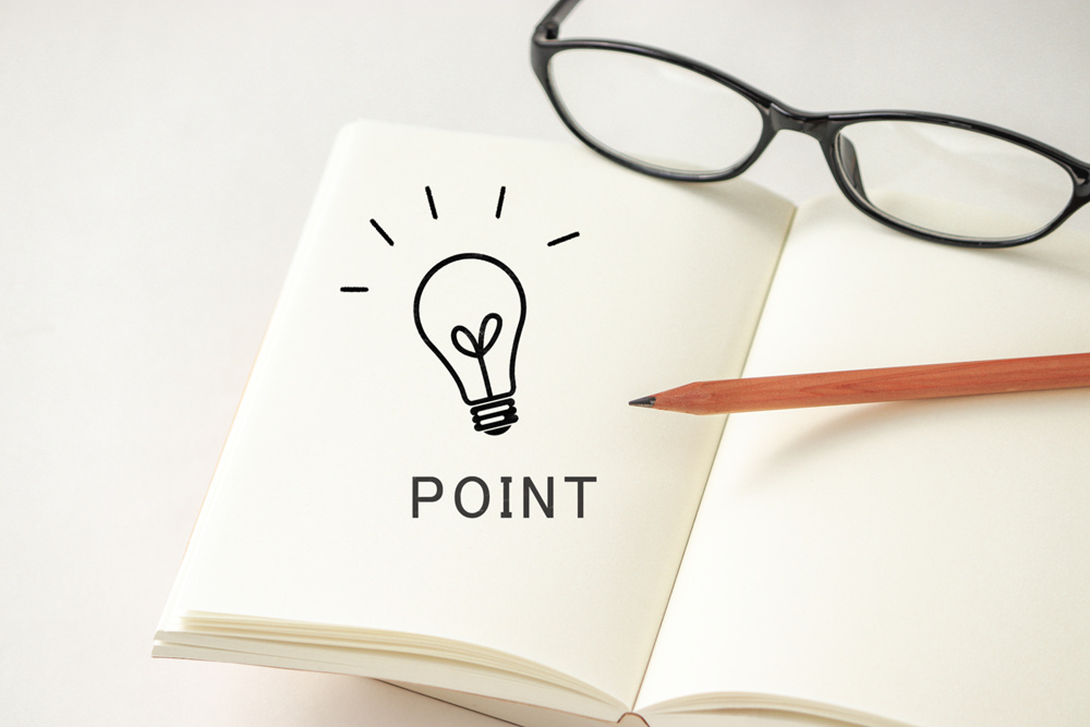
障がい者手帳を持っていない難病患者の方が、現時点では法定雇用率の算定対象とはならず、今後もその予定は未定であることがお分かりになったかと思います。
ただ、(障がい者手帳を持たない)難病患者の方は算定対象外であっても、算定の対象となる障がい者の条件は緩和されてきているのです。
具体的には、2024年4月より、労働時間が週20時間未満の短時間労働者も算定できるようになっています。
| 週所定労働時間 | 10時間以上20時間未満 | 20時間以上30時間未満 | 30時間以上 |
| 身体障がい者 | - | 0.5 | 1 |
| 重度身体障がい者 | 0.5 | 1 | 2 |
| 知的障がい者 | - | 0.5 | 1 |
| 重度知的障がい者 | 0.5 | 1 | 2 |
| 精神障がい者 | 0.5 | 0.5※ | 1 |
参考:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
※一定の要件を満たす場合、0.5ではなく1とカウントする特例措置あり
法定雇用率の達成を目指すなら、こうした短時間労働者や重度の障がいのある方に目を向け、より多様な障がい者の方を雇用していくことが肝要です。
特に都市部では、障がい者人材の獲得競争が激化しており、以下のような状況も珍しくありません。
| ・募集しても応募がない
・定着しない(より条件の良い企業に転職される) |
このような状況を打破するために、短時間労働者のための体制整備や、重度の障がいを持つ方へのサポートを充実させ、幅広い障がい者人材の雇用に取り組むことが必要なのです。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
5. 障がい者雇用の体制整備には社外の支援サービスも積極的に利用しよう

障がい者雇用において、多様な障がい者を雇用できる体制整備が必要であることをお伝えしました。
ただ、自社のみでそうした体制を整備するのは限界がある場合もあるはずです。
その際は、無理に社内で何とかしようとするのではなく、以下の社外の支援サービスを利用してみるのがおすすめです。
| 利用できる社外の支援サービス4つ |
| ・ハローワーク
・地域障害者職業センター ・障害者就業・生活支援センター ・障がい者雇用支援サービスを行う民間企業 |
法定雇用率の達成のサポートにもなるはずなので、ぜひ参考にしてみてください。
5-1.ハローワーク
ハローワークでは、準備段階から採用後の定着支援まで、障がい者雇用における幅広い知識や情報を無料で教えてくれます。
そのため、以下のようなお悩みがある企業は、ハローワークに相談してみましょう。
| ・何から始めたらいいか分からない
・障がい者雇用に必要な知識や、採用方法を知りたい ・助成金を活用したい |
また、どこに相談すればよいのか迷った時もハローワークに相談すると、他の支援機関と連携して、あなたの企業の障がい者雇用をサポートしてくれます。
厚生労働省「障害者に関する窓口」より、相談窓口の住所や電話番号をご確認ください。
5-2.地域障害者職業センター
地域障害者職業センターでは、主に障がい者の就職支援や職業リハビリテーションに関する相談を、無料で受け付けています。
そのため、以下のように感じている企業は、地域障害者職業センターへの相談がおすすめです。
| ・障がい特性に合った仕事を割り当てたい
・障がいに応じた合理的配慮をしたい |
ハローワークよりも専門的な支援を行っているため、「事業主支援計画」の策定や、障がい者職業カウンセラーによる具体的な支援の提供も受けられます。
地域障害者職業センターは各都道府県に設置されているので、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センター」より、住所や電話番号をご確認ください。
5-3.障害者就業・生活支援センター
障がいがある方の就職活動や職場でのサポートを行っている障害者就業・生活支援センターでは、障がい者本人を中心に、企業や家族に対しても、無料で支援を行っています。
そのため、以下のようなお悩みがある企業は、障害者就業・生活支援センターに相談してみましょう。
| ・障がい者の生活リズムや健康管理のサポートをしたい
・職場定着率が低迷しているものの、改善方法が分からない |
就業面の問題だけでなく、その基盤となる生活面からもサポートしてくれるため、障がい者の方の職業生活の自立に役立ちます。
障害者就業・生活支援センターは全国に設置されているので、「令和6年度障害者就業・生活支援センター 一覧」より、住所や電話番号をご確認ください。
5-4.障がい者雇用支援サービスを行う民間企業
障がい者雇用支援サービスを行う民間企業は、他の相談先とは違って、サービスによっては有料となりますが、企業のニーズに合わせた柔軟なサポートが受けられます。
そのため、以下のように感じている企業は、障がい者雇用支援サービスを行う民間企業に相談してみましょう。
| ・企業の仕事内容や、職場環境に適した障がい者雇用の方法を知りたい
・企業に合った障がい者の雇用率向上施策を提案してほしい |
あなたの企業の業種に合わせた障がい者の方向けの仕事の見つけ方や、企業の規模や配置に合わせた具体的な合理的配慮の方法を、提案してもらえるケースもあります。
あなたの企業で法定雇用率を達成できるように、社外の支援サービスも活用して、障がい者雇用を進めていきましょう。
| 障がい者雇用支援サービスを活用するなら
JSHのコルディアーレ農園にご相談ください |
| 障がい者雇用に難しさを感じていて、企業のニーズに合わせた柔軟なサポートが受けられる「障がい者雇用支援サービス」に魅力を感じた方は、ぜひJSHにご相談ください。
JSHでは、企業様に屋内型農園の「コルディアーレ農園」の区画と水耕栽培設備を貸し出し、主に九州在住の障がい者人材をご紹介しています。
障がい者人材をお探しの企業さまと、働きたい障がい者の方の架け橋となるサービスです。 
コルディアーレ農園では、障がい者の方に、整備された環境の下で葉物野菜やハーブなどの栽培に携わっていただいています。
また、精神科勤務経験のある看護師が唯一常駐するなど、多数の有資格者による手厚いサポートがあるため、高い定着率を期待していただけます。
弊社の農園型障がい者雇用支援サービスを導入いただいている企業さまは190社以上で、その継続率は99%にも上ります。
少しでも興味を持って下さった方は、お気軽に下記ボタンからコルディアーレ農園の資料をご請求ください。
|
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
6. まとめ
法定雇用率と難病患者について、詳しくご紹介させていただきました。改めて、ポイントをおさらいしましょう。
法定雇用率に算定できる難病患者は、障がい者手帳を持つ方のみです。「難病患者である」という理由だけでは算定されません。
なお、難病患者のうち、障がい者手帳を持つ方は約56%です。
難病患者の方を法定雇用率の対象にするよう、働きかける動きはありますが、2024年11月現在、難病患者が法定雇用率の対象になる予定はありません。
その中で、幅広い障がい者人材を雇用するためには、以下の社外の支援サービスも積極的に利用してみましょう。
| ・ハローワーク
・地域障害者職業センター ・障害者就業・生活支援センター ・障がい者雇用支援サービスを行う民間企業 |
この記事を元に、法定雇用率の算定対象を理解し、あなたの企業における障がい者雇用を進められることを、お祈りしています。
おすすめ記事
-

詳細を見る
2026年1月16日
【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件
「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]
法律・制度
-

詳細を見る
2026年1月13日
水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説
「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]
法律・制度
-

詳細を見る
2026年1月13日
ロクイチ報告とは|概要から提出意義、押さえるべき知識まで徹底解説
「ロクイチ報告とはどういうものか知りたい」 「用紙が届いたのだが、必ず提出しなければいけな[...]
法律・制度