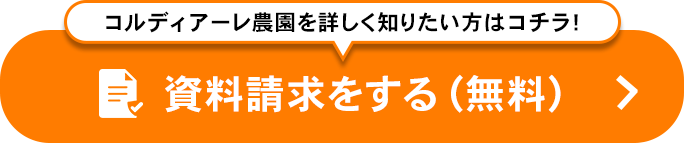コラム詳細
2025/03/17
autorenew2025/11/25
障害者基本法と障害者差別解消法の違いを解説!それぞれの法律遵守ポイントとは
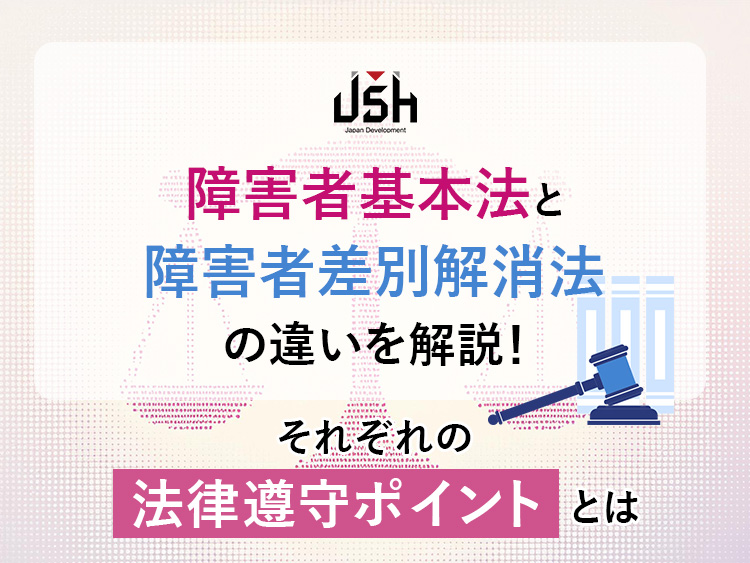
「障害者基本法と障害者差別解消法の違いについて知りたい」
「障害者基本法と障害者差別解消法をどちらも遵守するには何をしたらいいのだろう?」
障がい者雇用や事業を運営するに当たって押さえておくべき法律はいくつも存在しますが、特に関わりの深い法律に「障害者基本法」と「障害者差別解消法」があります。
しかし、それぞれの法律の概要を見ても違いが分からず、お困りの方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、障害者基本法と障害者差別解消法について明確な違いをまとめ、解説しています。
障害者基本法と障害者差別解消法の主な違いは、以下の一覧表の通りです。
| 障害者基本法 | 障害者差別解消 | |
| 目的 | 障がいの有無に関わらず、全ての国民が平等に暮らせる社会を作ること | 障がいを理由にした差別をなくすこと |
| 性質 | 障がい者に関する施策全般が対象で、基本的な方針を示している | 差別の解消だけに特化し、具体的な行動や義務を定めている |
| 内容 | ・障がい者の雇用機会の確保と促進
・適切な商品やサービス、情報の提供 ・環境の改善や整備 |
・障がいを理由にした差別の禁止
・合理的配慮の提供 |
| 法的な拘束力 | 弱い(具体的な罰則や罰金はなし) | 強い(一部に罰則や罰金がある) |
障がい者雇用をスムーズに進めるためには、まずは2つの法律について正確に理解し、法律遵守のために行動を起こす必要があります。
怠れば、自社で法令違反が発生してしまう事態になりかねません。
そのようなことにならないために、この記事では以下の内容を解説します。
| ・「障害者基本法」と「障害者差別解消法」の主な違い
・2つの法律を遵守するポイント ・障がい者雇用における特に重要なポイント |
2つの法律の違いを理解し、障がい者雇用に向けた取り組みをスムーズに進めていきたい方は、本記事をぜひ最後まで読み進めてください。
また、障害者差別解消法についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も併せて参考にしてください。
障害者差別解消法とは?事業者に義務化された合理的配慮も詳しく解説
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
【目次】
1. 「障害者基本法」と「障害者差別解消法」の違い一覧
2. 障害者基本法と障害者差別解消法の違い(1)目的と性質
3. 障害者基本法と障害者差別解消法の違い(2)企業に求めること
4. 障害者基本法と障害者差別解消法の違い(3)法的な拘束力
5. 法律の違いを押さえて両方とも遵守するポイント
6. 障がい者雇用においては「合理的配慮の提供」が課題となりやすい
7. まとめ
1.「障害者基本法」と「障害者差別解消法」の違い一覧
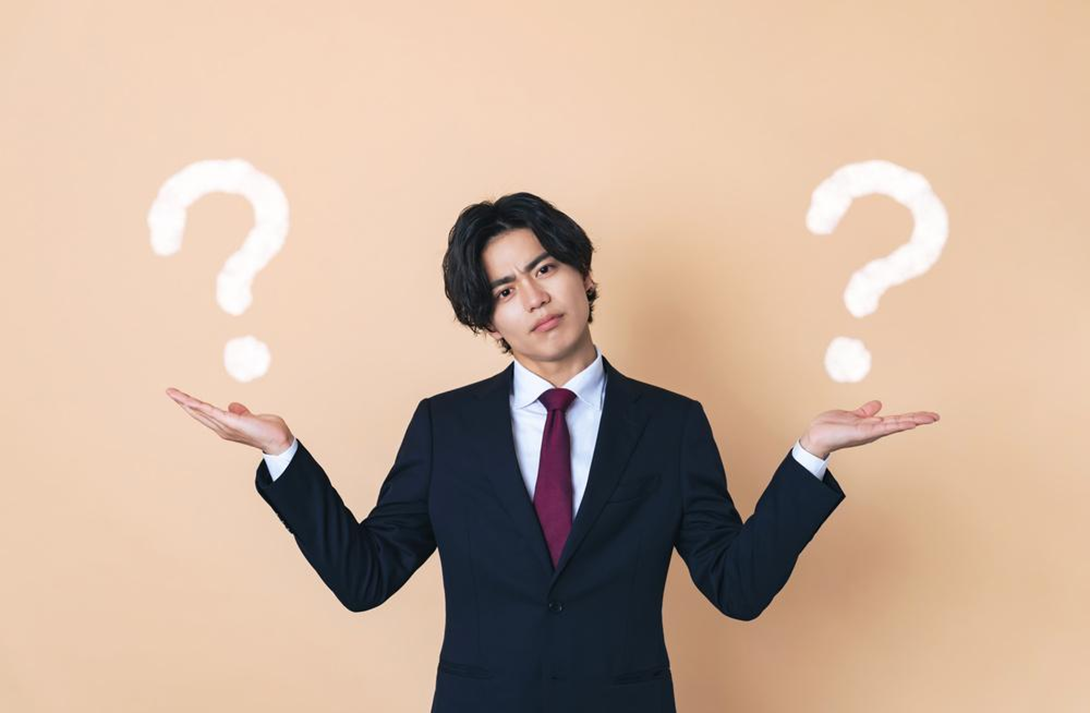
「障害者基本法」と「障害者差別解消法」の大きな違いは、以下の通りです。
| 障害者基本法 | 障害者差別解消 | |
| 目的 | 障がいの有無に関わらず、全ての国民が平等に暮らせる社会を作ること | 障がいを理由にした差別をなくすこと |
| 性質 | 障がい者に関する施策全般が対象で、基本的な方針を示している | 差別の解消だけに特化し、具体的な行動や義務を定めている |
| 企業に求めること | ・障がい者の雇用機会の確保と促進
・適切な商品やサービス、情報の提供 ・環境の改善や整備 |
・障がいを理由にした差別の禁止
・合理的配慮の提供 |
| 法的な拘束力 | 弱い(具体的な罰則や罰金はなし) | 強い(一部に罰則や罰金がある) |
障害者基本法と障害者差別解消法は、障がい者の権利を守り社会への参加を促進するという大きな役割は同じですが、目的に少しずつ違いが見られます。
したがって、法律の中身もそれぞれの目的に応じた内容となっており、大きく分類すると「性質」「企業に求める内容」「法的な拘束力」で違いがあります。
次章以降ではそれぞれの違いについて詳しく解説していきますので、どうぞこのまま読み進めてください。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
2.障害者基本法と障害者差別解消法の違い(1)目的と性質

障害者基本法と障害者差別解消法は、それぞれの目的が異なるため性質にも大きな違いがあります。
| 障害者基本法 | 障害者差別解消法 | |
| 目的 | 障がいの有無に関わらず、全ての国民が平等に暮らせる社会を作ること | 障がいを理由にした差別をなくすこと |
| 性質 | 障がい者に関する施策全般が対象で、基本的な方針を示している | 差別の解消だけに特化し、具体的な行動や義務を定めている |
それぞれ法律の目的と性質について、詳しく見ていきましょう。
2-1.障害者基本法の目的・性質
障害者基本法は、障がいの有無に関わらず全ての国民が平等に暮らせる社会を作るために、障がい者の権利や福祉に関する「国の基本的な方針」を定めた法律です。
障害者基本法第一条によると、障害者基本法の目的は次のように明記されています。
| 第一条
この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 |
引用:内閣府 障害者基本法(昭和四十五年五月二十一日法律第八十四号)
つまり障害者基本法の目的とは、障がいのある人もない人も平等に尊重され、お互いの個性を認め合いながら共に生きる社会を作ることです。
この法律の目的の中心となるのは、以下のような内容です。
| ・全ての人の基本的な人権を尊重する
・障がいの有無で差別をしない ・障がい者の自立と社会参加を支援する |
障害者基本法では、国や地方自治体の役割を明確にし、障がい者支援のための基本的な事項を定めています。
そして、障がい者の支援や関連する施策を計画的にに進めていくための「大きな枠組み」を作る役割を果たしているのです。
2-2.障害者差別解消法の目的・性質
障害者差別解消法は、障害者基本法の基本的な考え方を実現させるために、より具体的な行動や義務を定めた法律です。
障害者差別解消法第一条によると、障害者差別解消法の目的は次のように明記されています。
| 第一条
この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。 |
引用:内閣府 障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)
つまり障害者差別解消法の目的とは、障がいのある人もない人も平等に扱われ、お互いを尊重し合える社会を作ることです。
障害者基本法と似た内容ではありますが、障害者差別解消法は障がいを理由とした差別の解消に特化している点が大きく異なる点です。
この法律の目的の中心となるのは、以下のような内容です。
| ・障がいのある人の基本的人権を守る
・障がいを理由とした差別をなくす ・政府機関や企業が障がい者差別をなくすための対策を取る |
障害者差別解消法は、日常生活や社会の中で起こる差別を解消するための「具体的な行動」を明確に示す役割を果たしています。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
3.障害者基本法と障害者差別解消法の違い(2)企業に求めること

障害者基本法と障害者差別解消法は、企業に求めることにも違いがあります。
| 障害者基本法 | 障害者差別解消法 | |
| 企業に求めること | ・障がい者の雇用機会の確保と促進
・適切な商品やサービス、情報の提供 ・環境の改善や整備 |
・障がいを理由にした差別の禁止
・合理的配慮の提供 |
それぞれ法律が企業に求めることは何か、詳しく見ていきましょう。
3-1.障害者基本法が企業に求めること
障害者基本法では、国・地方自治体・事業主が協力して障がい者の雇用を支援し、働きやすい環境を作ることが求められています。
障害者基本法第十九条・二十一条・二十二条・二十七条によると、障害者基本法が事業者や事業主に求める対応について、次のように明記されています。
| 第十九条
国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体並びに事業者における障害者の雇用を促進するため、障害者の優先雇用その他の施策を講じなければならない。
2 事業主は、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。 |
| 第二十一条
2 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、当該公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進に努めなければならない。
4 国、地方公共団体及び公共的施設を設置する事業者は、自ら設置する公共的施設を利用する障害者の補助を行う身体障害者補助犬の同伴について障害者の利用の便宜を図らなければならない。 |
| 第二十二条
3 電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、当該役務の提供又は当該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。 |
| 第二十七条
2 事業者は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供等に努めなければならない。 |
引用:内閣府 障害者基本法(昭和四十五年五月二十一日法律第八十四号)
つまり障害者基本法では、企業に対して以下のような対応を求めています。
| 第十九条 | ・障がい者の雇用を増やすための特別な取り組みを行う
・障がい者の能力を正しく評価し、適切な仕事の機会を与える ・個々の障がい者の特性に合わせた雇用管理を行い、長く働けるようにする |
| 第二十一条 | ・障がい者が利用しやすいように、施設の構造や設備を改善するよう努力する
・国、地方自治体、公共施設の運営者は、障がい者が補助犬(盲導犬など)を連れて施設を利用できるようにする |
| 第二十二条 | ・通信、放送、情報提供サービスを行う企業やパソコンや通信機器を作る企業は、障がい者が使いやすい製品やサービスを提供するよう努力する |
| 第二十七条 | ・障がい者が消費者として適切に保護され、利益を得られるようにする
・障がい者に分かりやすい方法で情報を提供するよう努力する |
障害者基本法では、企業に対してこうした対応に努めることを求めており、障がいのある人もない人も、全ての人が暮らしやすい社会を作ることを目指しています。
3-2.障害者差別解消法が企業に求めること
障害者差別解消法では、障がいを理由とした差別をなくすための事業者や事業主に対する具体的な対応や取り組みについて定めてあります。
障害者差別解消法第五条・八条によると、障害者差別解消法が事業者や事業主に求める対応について、次のように明記されています。
| 第五条
行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。 |
| 第八条
事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 |
引用:内閣府 障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)
つまり障害者差別解消法では、企業に対して以下のような対応を求めています。
| 第五条 | ・障がいのある人々が社会で直面する障壁をなくすために、適切で合理的な配慮をする
・自社のバリアフリー化や必要な設備の設置、関係する職員に対しての研修や教育を通して、障がい者にとって過ごしやすい環境を作れるよう努力する |
| 第八条 | ・障がいを理由として差別をしない
・障がいを理由として障がい者の権利を侵害しない ・障がい者が社会的な障壁を取り除いてほしいと伝えてきた場合、事業者は過度な負担にならない範囲で対応する ・その人の性別、年齢、障がいの状態に応じて、適切で合理的な方法で対応する |
障害者差別解消法では、これらのより具体的な対応を通じて障がいを理由とする差別を解消することを目指しています。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
4.障害者基本法と障害者差別解消法の違い(3)法的な拘束力

障害者基本法と障害者差別解消法は、法的な拘束力にも大きな違いがあります。
| 障害者基本法 | 障害者差別解消法 | |
| 法的な拘束力 | 弱い(具体的な罰則や罰金はなし) | 強い(一部に罰則や罰金がある) |
それぞれの法律の拘束力の違いについて、詳しく見ていきましょう。
4-1.障害者基本法の法的な拘束力
障害者基本法は、2章でも解説したように国の考え方や方針を示す「理念法」としての役割が強く、法的な拘束力は弱い法律です。
実際に障害者基本法の中に「罰則」という項目はなく、違反した場合の直接的な罰則や罰金は定められていません。
また、「3-1.障害者基本法が企業に求めること」でご紹介した内容も、努力や便宜を図ることを求めており、具体的な対応を義務化しているわけではありません。
このように、障害者基本法自体にはそこまで強い拘束力がないことが分かります。
4-2.障害者差別解消法の法的な拘束力
障害者差別解消法は、障がい者への差別をなくすための具体的な行動や禁止事項を定めた「実施法」です。したがって、法律に違反した場合には罰則や罰金が科せられます。
実際に、障害者差別解消法第二十五条・第二十六条によると、障害者差別解消法の罰則について、次のように明記されています。
| 第二十五条
第十九条※の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
※第十九条:協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 |
| 第二十六条
第十二条※の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
※第十二条:主務大臣は、第八条※※の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
※※第八条:事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 |
引用:内閣府 障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)
つまり障害者差別解消法では、以下の内容に違反した場合には罰則が課せられます。
| 第二十五条 | 国や地方公共団体の機関で働く人・働いていた人が、正当な理由なく機関で知った情報を漏洩した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 第二十六条 | 障がい者の差別解消や合理的配慮の提供に取り組む中で、政府から報告を求められたにも関わらず、報告を怠ったり虚偽の報告をした場合20万円以下の罰金 |
障害者差別解消法は、上記のような具体的な罰則が設けられていることから、障害者基本法よりも法的な拘束力が強いと言えます。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
5.法律の違いを押さえて両方とも遵守するポイント

ここまで、「障害者基本法」と「障害者差別解消法」の違いについて詳しく解説してきました。
そこで5章では、2つの法律の違いを押さえた上でどちらも遵守するためのポイントについて解説します。
| 2つの法律を遵守するためのポイント |
| ・ポイント1|障がいを理由に差別をしないこと
・ポイント2|合理的配慮を提供すること ・ポイント3|差別の禁止・合理的配慮の提供について社内に周知させること ・ポイント4|障がい者本人と対話して相互理解を図ること |
上記の3つは優先順位の高いものから紹介していますが、それぞれが深い関わりを持っているため、どれか一つではなくまんべんなく取り組むことが重要です。
それでは、詳しい内容を見ていきましょう。
5-1.ポイント1|障がいを理由に差別をしないこと
2つの法律を遵守するポイントで最も重要なのは、障がいを理由に差別をしないことです。
なぜなら、障がいを理由とした差別の禁止はどちらの法律にも明記されており、障害者差別解消法においては国・地方自治体・民間企業の全てに対して法的義務として定められているからです。
実際に、障害者基本法では第四条と十九条に、障害者差別解消法では全体を通して障がいを理由とした差別の禁止について言及しています。
障がいを理由に差別しないための実践例には、以下のようなものがあります。
| サービスの提供を拒否しない | ・車椅子の利用を理由に、レストランへの入店を拒否しない
・障がいがあることを理由に、賃貸物件の紹介を拒否しない |
| 制限や条件を付けない | ・障がいを理由にイベントへの参加を制限したり特別な条件を付けない
・障がいのある人に対して、必要以上に介護者の同行を求めない |
| 平等な対応をする | ・障がいのある従業員を無視せず、直接本人と話をする
・障がいを理由に、窓口での対応を後回しにしない ・障がいのある従業員の能力を正当に評価する |
障がい者への差別を禁止することで、障がい者の基本的な人権を直接的に守ることに繋がり、他の法律遵守のためのポイントを実施する上の基盤を整えることにも繋がります。
5-2.ポイント2|合理的配慮を提供すること
両方の法律を遵守するポイントの2つ目は、障がいの特性に応じた柔軟な対応(合理的配慮)を提供することです。
なぜなら、障がいの特性に応じて柔軟な対応を行うことは、障がい者が日常生活や社会生活を他の人と同じように行うためには必要不可欠な要素だからです。
実際に、障害者基本法では第四条に、障害者差別解消法では第五条・七条・八条に明記されています。
日常生活や社会生活における合理的配慮には、具体的に以下のようなものがあります。
| 環境への物理的な配慮 | ・お店の出入り口にスロープを設置したり、通路を広くしたりする
・高いところに陳列されている商品を取ってあげる ・頻繁に離席する必要がある人を、扉の近くに配置する |
| 意思疎通の配慮 | ・筆談や読み上げ、手話などでコミュニケーションを取る
・本人の依頼があれば、代筆や代読を行う |
| 柔軟なルール変更の配慮 | ・従業員の障がい特性に応じて適切な休憩時間を設ける
・立って列に並ぶ必要がある場合、周囲の了解を得た上で順番が来るまで別室や席を用意する |
上記の例はごく一部で、実際には障がい者個人の状態や場面に応じて柔軟に対応することが重要です。また、配慮を提供する側が過度な負担とならない範囲で行うことが求められています。
障がい者雇用において重要な「合理的配慮」について、より詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてください。
【2024年4月より義務化】合理的配慮の考え方や企業がすべきこと
障がい者雇用における合理的配慮とは?障がい別の事例や進め方を解説
合理的配慮の具体例まとめ|場面別・障がい別に提供のポイントを紹介
5-3.ポイント3|差別の禁止・合理的配慮の提供について社内に周知させること
障害者基本法と障害者差別解消法の両方を遵守するためには「障がいを理由に差別をしないこと」「合理的配慮を提供すること」が必要であるとお伝えしましたが、これらの必要性や方針を社内に周知させることも重要です。
企業の上層部だけが「差別をしない」「合理的配慮を提供する」という認識を持っているだけでは、店舗や障がい者が雇用される現場において徹底されない可能性があるからです。
社内への周知を行う際には、差別の禁止や合理的配慮の提供について分かりやすく説明されている、内閣府の「障害者差別解消法リーフレット」を活用して行うことをおすすめします。
また、障がい者雇用に重点を置いた合理的配慮については、以下の記事を参考にして取り組んでみてください。
障がい者雇用における合理的配慮とは?障がい別の事例や進め方を解説
5-4.ポイント4|障がい者本人と対話して相互理解を図ること
最後に、障がい者本人と対話して相互理解を図ることも大切です。
障がいの特性や必要な配慮について本人と直接対話することで、その人が本当に必要としている配慮や要望を正確に把握し、適切な対応をすることができます。
本当に必要な配慮や要望についてお互いに理解し合い、建設的な対話を行うポイントは以下の通りです。
| 建設的な対話を行うポイント |
| ・相手の声に耳を傾けて真摯に受け止める姿勢を持つ
・「前例がない」という理由で断らず、個別に検討、対応する ・一度の対話で終わらせずに、必要に応じて継続的にコミュニケーションを取る |
障がい者本人と対話して相互理解を図ることは、共生社会を実現するために長期的に取り組むべきポイントです。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
6.障がい者雇用においては「合理的配慮の提供」が課題となりやすい

障害者基本法と障害者差別解消法、2つの違いを踏まえ両方を遵守することを目指していく中で、障がい者雇用において特に重要なのは「合理的配慮の提供」ですが、ここにハードルを感じる企業は多いです。
なぜなら、そもそも障がい者雇用や合理的配慮に対して知識や経験が不足している企業が多く、スムーズに進められないことで他の従業員への負担が増えたり、社内からの理解を得にくいなどの状況が起こってしまうからです。
障がい者雇用における合理的配慮には、具体的に以下のようなものがあります。
| 採用時の合理的配慮 | ・面接時に就労支援機関の職員などの同席を認める
・視覚障がい者に対して点字や音声で採用試験を実施する ・聴覚障がい者に対して筆談で面接を行う |
| 職場環境への配慮 | ・スロープや手すりの設置など、バリアフリー化を進める
・精神障がい者が落ち着いて休めるスペースを作る |
| 業務を行う際の配慮 | ・知的障がい者に対して図や写真を活用したマニュアルを作成する
・障がい者本人が「難しい」と感じる業務を他の業務に変える |
| 勤務時間や休憩時間の配慮 | ・通勤ラッシュが苦手な人に対して時差出勤を認める
・通院や体調に応じて勤務時間や休憩、休暇の調整を行う |
障がい者雇用における合理的配慮の提供は、2024年4月より民間企業に対しても法的な義務として対応を求められるようになりました。
つまり障がい者雇用においては、障がい者が障がいのない人と同じ条件で働く機会を提供することの重要性が、それだけ高まってきている証拠だと考えられます。
合理的配慮の提供は、障がい者の権利を守り共生社会を実現させるためには必要不可欠な要素と言えるため、企業は誠実に対応することが大切です。
| 【障がい者雇用における合理的配慮の提供にお悩みなら、株式会社JSHへご相談ください】 |
| 障がい者雇用における合理的配慮の提供にお悩みなら、株式会社JSHへご相談ください。
当社では、農園型障がい者雇用支援サービス「コルディアーレ農園」を運営し、障がい者を雇用したい企業様と、地方にお住まいの働く意欲のある障がいのある方をつなぐサポートを行っています。 
コルディアーレ農園では、障がい者の方に、整備された環境の下で葉物野菜やハーブなどの栽培に携わっていただいています。
また、精神科勤務経験のある看護師が唯一常駐するなど、多数の有資格者による手厚いサポートがあるため、雇用主と連携した合理的配慮を必要に応じて提供できる体制が整っています。
このように、障がい者・企業の双方が安心できるサポートを実施していることから、弊社の障がい者雇用支援サービスを導入いただいている企業様は190社以上、継続率は99%にも上るのです。(2024年6月時点)
障害者差別解消法でも求められている合理的配慮の提供について、ノウハウや体制が不足しているとお悩みなら、まずは資料請求からお気軽にお問い合わせください。
|
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
7.まとめ
この記事では、「障害者基本法と障害者差別解消法の違い」について詳しく解説してきました。
2つの法律の主な違いは、以下の通りです。
| 障害者基本法 | 障害者差別解消 | |
| 目的 | 障がいの有無に関わらず、全ての国民が平等に暮らせる社会を作ること | 障がいを理由にした差別をなくすこと |
| 性質 | 障がい者に関する施策全般が対象で、基本的な方針を示している | 差別の解消だけに特化し、具体的な行動や義務を定めている |
| 内容 | ・障がい者の雇用機会の確保と促進
・適切な商品やサービス、情報の提供 ・環境の改善や整備 |
・障がいを理由にした差別の禁止
・合理的配慮の提供 |
| 法的な拘束力 | 弱い(具体的な罰則や罰金はなし) | 強い(一部に罰則や罰金がある) |
また、2つの法律の違いを押さえ、法律を遵守するためのポイントは以下の通りです。
| 2つの法律を遵守するためのポイント |
| ・ポイント1|障がいを理由に差別をしないこと
・ポイント2|合理的配慮を提供すること ・ポイント3|差別の禁止・合理的配慮の提供について社内に周知させること ・ポイント4|障がい者本人と対話して相互理解を図ること |
これから障がい者雇用に取り組むにあたり、この記事が2つの法律を理解するためのお役に立てていれば幸いです。
おすすめ記事
-

詳細を見る
2026年2月10日
ESG経営とは?導入すべきメリットから取組事例・注意点まで解説
「ESG経営とは、どういうものか知りたい」 「どうして今、注目されているのだろうか。ESG[...]
事例
-

詳細を見る
2026年1月16日
【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件
「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]
法律・制度
-

詳細を見る
2026年1月13日
水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説
「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]
法律・制度