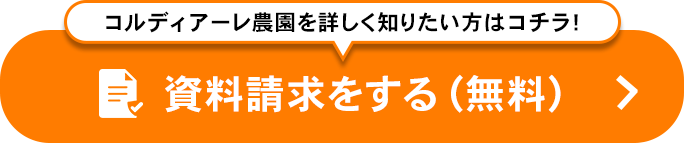コラム詳細
2025/03/17
autorenew2025/11/25
障がい者の退職理由とその対処法|障がい種類別に上位3つを解説
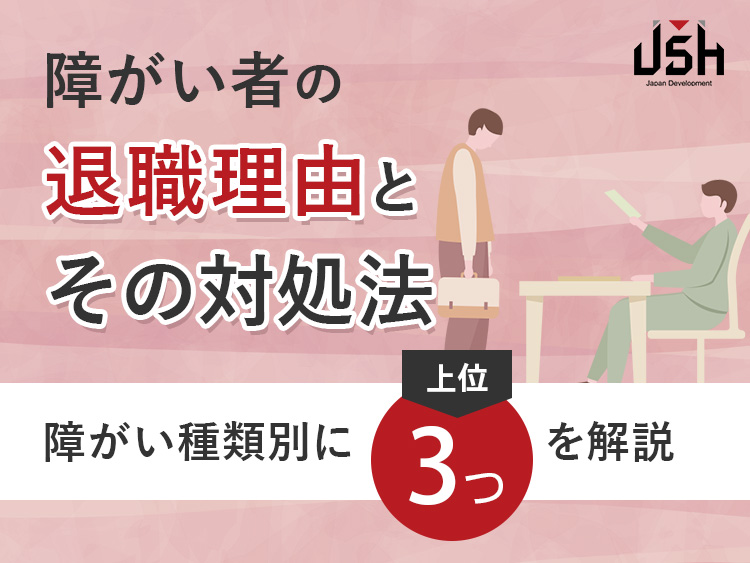
「障がい者雇用に取り組んでいるが、退職するケースも多い。なぜ?」
「障がい者雇用の定着率を上げたいが、企業側は何をしたらいいのか?」
障がい者雇用において企業には法定雇用率の達成や法律の遵守が求められる中、このようなお悩みに直面する企業や担当者は少なくありません。
そこで、障がい者雇用における退職理由を把握し対策を練ることで、なんとか障がい者雇用の定着率を上げたいとお考えの方もいるのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、障がい者雇用における障がい種類別の退職理由には、以下のようなものが挙げられます。
| 身体障がい者の方に多い退職理由 | 1.障がい・病気のため
2.業務遂行上の課題あり 3.労働環境が合わないため |
| 精神障がい者の方に多い退職理由 | 1.障がい・病気のため
2.人間関係の悪化 3.業務遂行上の課題あり |
| 知的障がい者の方に多い退職理由 | 1.業務遂行上の課題あり
2.人間関係の悪化 3.障がい・病気のため |
参照:障害者職業総合センター「障害のある求職者の実態等に関する調査研究」
障がい者雇用における離職を防ぐためには、退職理由がどうあれ企業側が障がいや特性についての理解を深め、その方に合った適切な配慮やサポートを行うことが必要です。
そこでこの記事では、「障がい者雇用における退職理由への対処法」も併せて解説しています。この記事を読めば、障がい者雇用における、障がい種類別の退職理由と、その具体的な対処法が分かります。
障がい者雇用の定着率をなんとかして改善したい方は、ぜひ最後まで読み進めてください。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
【目次】
1. 障がい者雇用における障がい種類別の退職理由
2. 離職を防ぐには退職理由に関わらず「障がいへの理解を深める」ことが最重要
3. 身体障がい者の方に多い退職理由への対処法
4. 精神障がい者の方に多い退職理由への対処法
5. 知的障がい者の方に多い退職理由への対処法
6. 障がい者雇用の離職率を下げるためには支援機関との連携も重要
7. まとめ
1.障がい者雇用における障がい種類別の退職理由
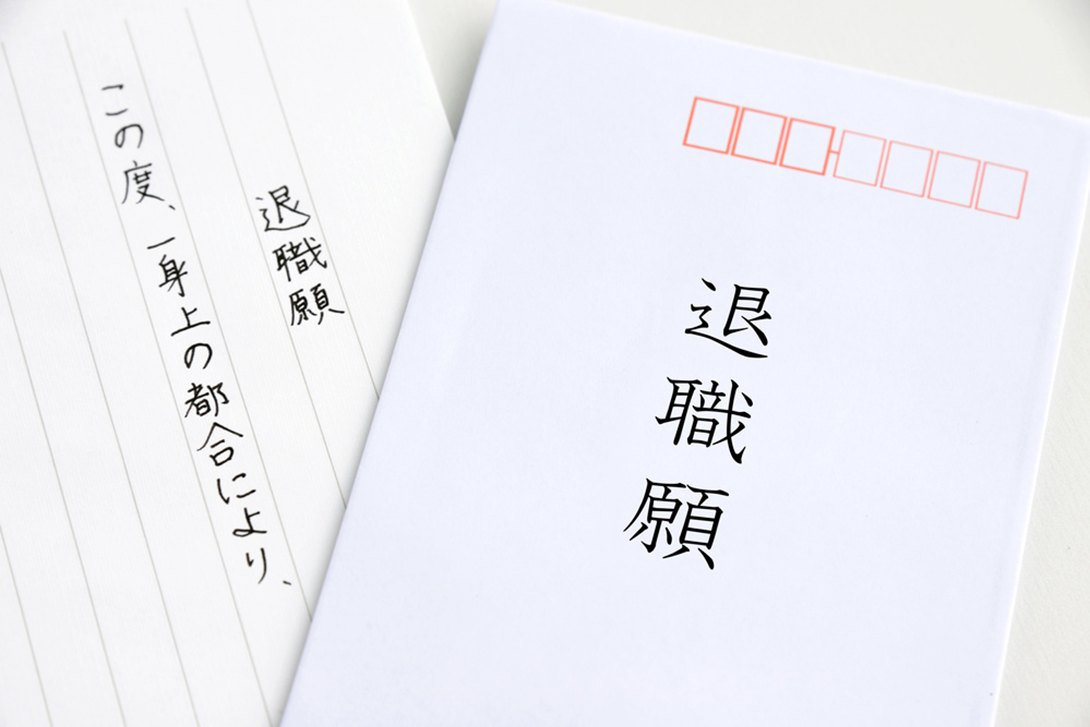
障がい者雇用における障がい種類別の退職理由上位3つには、以下のようなものが挙げられます。
| 身体障がい者の方に多い退職理由 | 1.障がい・病気のため
2.業務遂行上の課題あり 3.労働環境が合わないため |
| 精神障がい者の方に多い退職理由 | 1.障がい・病気のため
2.人間関係の悪化 3.業務遂行上の課題あり |
| 知的障がい者の方に多い退職理由 | 1.業務遂行上の課題あり
2.人間関係の悪化 3.障がい・病気のため |
参照:障害者職業総合センター「障害のある求職者の実態等に関する調査研究」
上記に挙がっている退職理由は、障がい者の職業生活における自立をサポートするために設立された「障害者職業総合センター」が、2020年に発表した調査報告書に基づいてまとめています。
1章では、障がい者雇用において
| ・身体障がい者
・精神障がい者 ・知的障がい者 |
の3種類に分けて、退職理由をそれぞれ深掘りしていきます。
1-1.身体障がい者の方に多い退職理由
身体障がい者の方に多い退職理由上位3つは、以下の通りです。
| 身体障がい者の方に多い退職理由 |
| 1.障がい・病気のため:49.8%
2.業務遂行上の課題あり:9.0% 3.労働環境が合わないため:8.2% |
参照:障害者職業総合センター「障害のある求職者の実態等に関する調査研究」
身体障がい者の方が退職する理由で最も多かったのが「障がい・病気のため」で、退職理由全体の中の約5割を占めていました。
障がい者雇用の中で、身体障がい者の方が「障がいや病気のため」に退職する理由には以下のような背景が考えられます。
| 身体障がい者の方が退職に至る背景 |
| ・障がいによって体力が低下し、長時間労働や通勤が困難になってしまった
・職場のバリアフリー化が進んでおらず、業務がスムーズに遂行できない |
身体障がい者の方は、そもそも抱えている障がいや病気が原因で体力的・精神的に負担が大きく、仕事がしづらい状況です。
その上でさらに、業務の進め方や職場の環境が合わないことで負担やストレスを感じ、退職に至ったと考えられます。
したがって、障がいの特性や必要な配慮について障がい者本人とよく話し合い、双方が無理のない範囲で業務を進められる仕組みを考えることが早期退職を防ぐ鍵となります。
1-2.精神障がい者の方に多い退職理由
精神障がい者の方に多い退職理由上位3つは、以下の通りです。
| 精神障がい者の方に多い退職理由 |
| 1.障がい・病気のため:61.3%
2.人間関係の悪化:13.2% 3.業務遂行上の課題あり:8.6% |
参照:障害者職業総合センター「障害のある求職者の実態等に関する調査研究」
精神障がい者の方が退職する理由で最も多かったのが「障がい・病気のため」で、退職理由の6割以上を占めていました。
障がい者雇用の中で、精神障がい者の方が「障がいや病気のため」に退職する理由には以下のような背景が考えられます。
| 精神障がい者の方が退職に至る背景 |
| ・職場での人間関係や仕事のプレッシャーがストレスに感じ、症状が悪化してしまった
・就労によって通院や服薬の時間が確保できずに、症状が悪化してしまった ・障がいについて開示せずに就職したので、合理的な配慮が得られずストレスになってしまった |
精神障がい者の方は、人間関係や過度なノルマなどの精神的なストレスによって症状が変動しやすいのが特徴です。
また、精神障がいは本人が開示しない限り周囲の人からは分かりづらいため、あえて開示せずに就職するケースがあります。
しかし、障がいを開示しないことで職場から適切な配慮が得られないため、それがストレスとなり症状が悪化して退職に至る方も少なくありません。
そのため、障がい者を雇用する際は、本人の障がい特性について可能な範囲で話を聞き、入社後のミスマッチを防ぐことが重要です。
1-3.知的障がい者の方に多い退職理由
知的障がい者の方に多い退職理由上位3つは、以下の通りです。
| 知的障がい者の方に多い退職理由 |
| 1.業務遂行上の課題あり:22.2%
2.人間関係の悪化:21.0% 3.障がい・病気のため:18.5% |
参照:障害者職業総合センター「障害のある求職者の実態等に関する調査研究」
知的障がい者の方が退職する理由は、上位3つがほとんど同じ割合を占めていました。つまり、知的障がい者の方の場合は、退職理由が個人によって大きく左右することが分かります。
障がい者雇用の中で、知的障がい者の方が退職する理由には以下のような背景が考えられます。
| 知的障がい者の方が退職に至る背景 |
| ・作業環境が障がいの特性に合わず、業務を遂行できなくなった
・個人によって得意、不得意に差があり、配属先では能力を十分に発揮できなかった ・指示の理解が追いつかず、周囲とのコミュニケーションが上手くいかなかった ・職場の雰囲気に馴染めず、孤立感を感じてしまった ・職場環境や作業内容の変更に適応できず、不安やストレスを感じて体調を崩してしまった |
知的障がい者の方は、周囲とのコミュニケーションに課題がある場合もあります。それによって、業務がスムーズに進められずに同僚とトラブルになったり、周囲に馴染めないことで孤立感を感じてしまい、退職に至ったと考えられます。
したがって知的障がい者の方の場合は、主に人間関係をスムーズにするためのサポートを行うことが、早期退職を防ぐことにも大きく影響します。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
2.離職を防ぐには退職理由に関わらず「障がいへの理解を深める」ことが最重要

障がい者雇用において障がいのある従業員の離職を防ぐには、障がいの種類や退職理由に関わらず「企業側が障がいへの理解を深めること」が一番重要です。
障がいについて深く理解することで、障がいに応じて本当に必要な配慮やサポートすることができます。
障がいに応じた必要な配慮とは、具体的に以下のようなものが挙げられます。
| 障がいに応じた具体的な配慮の例 |
| ・聴覚障がいのある方:筆談や手話通訳を活用し、円滑なコミュニケーションを図る
・知的障がいのある方:分かりやすい表現に言い換えて説明するなど、意思疎通に配慮する ・視覚障がいのある方:音声による情報提供や点字資料の用意などで意思の疎通を図る ・肢体不自由のある方:車椅子で移動しやすいようにスロープやエレベーターを設置する |
障がい者雇用における企業の義務の一つに「合理的配慮」も含まれているため、法律を遵守する観点でも重要なポイントであると言えます。
離職を防ぐためにどのような配慮や対処をすればいいのかは、続けて障がい種類別に詳しく解説していますので、参考にしてください。
具体的な配慮の内容や必要なサポート自体は個人によって違いますが、「理解しよう」と努力している姿勢が伝わるだけでも、障がいのある従業員との信頼関係を築くキッカケになります。
職場への安心感や信頼関係があれば障がいのある方も安心して働くことができるため、結果的に離職を防ぐことにも繋がるでしょう。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
3.身体障がい者の方に多い退職理由への対処法

3章では、身体障がい者の方に多い退職理由への対処法を解説します。
身体障がい者の方に多い退職理由上位3つと、その対処法は以下の通りです。
| 退職理由 | 対処法 |
| 障がい・病気による退職 | ・障がいの状況や体調に応じた柔軟な勤務制度を整える
・通院、治療のための休暇を取りやすくする |
| 業務遂行上の課題があることによる退職 | ・必要な機器や補助具を導入して、業務の効率を上げる
・障がいや特性に合わせた業務の割り当てを行う |
| 労働環境が合わないことによる退職 | ・物理的な職場の環境を整える
・相談しやすい人間関係作りをサポートする |
それでは、具体的な対処法を以下より詳しく解説します。
3-1.「障がい・病気による退職」への対処法
身体障がい者の方の「障がい・病気による退職」を防ぎたい場合は、以下のような制度の導入や勤務時間の調整が必要です。
| 「障がい・病気による退職」への対処法 |
| ・障がいの状況や体調に応じて短時間勤務やリモートワークを選べるなど、柔軟な勤務制度を整える
・通院、治療のための休暇を取りやすくすることで、仕事と治療の両立を支援する |
身体障がい者の方にとって、病気の治療と仕事を両立できることが退職を防ぐ鍵となります。そのため、まずは障がいの状況や体調に応じて柔軟に勤務体制を変更できれば、身体障がい者の方にとって働きやすさが格段にアップします。
さらに、通院・治療のための休暇を取りやすくすることで仕事と治療の両立がスムーズになるため、障がいのある方も安心して働き続けられるようになります。
3-2.「業務遂行上の課題があることによる退職」への対処法
身体障がい者の方の「業務遂行上の課題があることによる退職」を防ぎたい場合は、以下のような設備の導入や仕組みが必要です。
| 「業務遂行上の課題があることによる退職」への対処法 |
| ・必要な機器や補助具を導入して、業務の効率を上げる
・障がいや特性に合わせた業務の割り当てを行う |
まずは、必要な機器や補助具を導入して、業務の効率を上げることから始めましょう。
例えば、車椅子の方が社内をスムーズに移動するためのスロープ(持ち運びようでも構いません)や、聴覚障がいのある方がコミュニケーションを取りやすくするための筆談ツールなどがそれにあたります。
これらは、ネット通販でもすぐに購入できるものです。
企業が障がい者を雇うために設備や補助具を導入する際は、国や専門の機関から補助金や助成金が支給されるため、そういった制度も活用するのがおすすめです。
(助成金例:障害者作業施設設置等助成金)
また、障がいや特性に合わせた業務の割り当てを行うことで、能力を十分に発揮できる可能性が高くなります。
例えば、体力的に立ち仕事が困難な方でも、座って行う作業なら長時間の勤務に適応しやすい可能性があるでしょう。
3-3.「労働環境が合わないことによる退職」への対処法
身体障がい者の方の「労働環境が合わないことによる退職」を防ぎたい場合は、以下のような設備の導入や取り組みが必要です。
| 「労働環境が合わないことによる退職」への対処法 |
| ・手すりやスロープの設置など、物理的な職場の環境を整える
・メンター制度の導入など、相談しやすい人間関係作りをサポートする |
まずは、手すりやスロープなどを設置して、身体障がい者の方でも快適に業務に取り組めるような環境作りをすることが重要です。
本格的なスロープの設置工事を行う場合には10〜20万ほどの費用がかかりますが、駅などで使われるような持ち運び式の簡易スロープなら2万円程度でネット通販でも購入できるので、比較的手軽に導入できるでしょう。
また、業務上の悩みや困り事を気軽に相談できるメンター制度を導入することで、社内により良い人間関係を作れるようにサポートできます。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
4.精神障がい者の方に多い退職理由への対処法

次に、精神障がい者の方に多い退職理由への対処法を解説します。
精神障がい者の方に多い退職理由上位3つと、その対処法は以下の通りです。
| 退職理由 | 対処法 |
| 障がい・病気による退職 | ・短時間勤務やフレックス制など勤務時間に柔軟に対応する
・体調不良時には休みが取りやすいようにする ・通院のための休暇や服薬のための時間を設ける |
| 人間関係の悪化による退職 | ・社内研修を通して適切な声掛けやコミュニケーションを把握する
・コミュニケーション支援専門の職員を配置する ・ストレスチェックを受け、その結果に応じて適切な対応を行う |
| 業務遂行上の課題があることによる退職 | ・個人の能力に合わせて業務を割り当てる
・業務を簡略化するなどして、取り組みやすいようにする ・ジョブコーチなど支援機関にもサポートに入ってもらう |
それでは、具体的な対処法を以下より詳しく解説します。
4-1.「障がい・病気による退職」への対処法
精神障がい者の方の「障がい・病気による退職」を防ぎたい場合は、以下のような制度の導入や勤務時間の調整が必要です。
| 「障がい・病気による退職」への対処法 |
| ・短時間勤務やフレックス制など、勤務時間に柔軟に対応する
・体調不良時には休みが取りやすいようにする ・通院のための休暇や服薬のための時間を設ける |
精神障がい者の方も、短時間勤務やフレックス制などの勤務時間、勤務形態に柔軟に対応することは必要です。
また、体調不良時には休みが取りやすいような企業であれば、仕事への過度な責任感やプレッシャーを軽減しつつ療養に専念しやすいでしょう。
さらに、通院のための休暇や服薬のための短い休憩時間などがあることで、体調を安定させて安心して業務に取り組むことができます。
4-2.「人間関係の悪化による退職」への対処法
精神障がい者の方の「人間関係の悪化による退職」を防ぎたい場合は、以下のような取り組みや配慮が必要です。
| 「人間関係の悪化による退職」への対処法 |
| ・社内研修で社内の理解を深めて、適切な声掛けや業務指示・コミュニケーションを把握する
・コミュニケーション支援専門の職員を配置する ・ストレスチェックを受け、その結果に応じて適切な対応を行う |
まずは、社内研修で障がいに対して理解を深めることが大切です。それによって、どんな声掛けや指示の出し方・コミュニケーションの取り方が適切なのか、社内で共通の意識を持つことができます。
また、精神障がいのある方の中には、他者とのコミュニケーションが難しいと感じる方も多いです。そのため、人間関係についていつでも相談できる、コミュニケーション支援専門の職員を配置するのも効果的です。
さらに、精神障がいの特性上ストレスに敏感であると言われているため、ストレスチェックを実施してその結果に応じた対応を行うと高い効果を得やすいでしょう。
4-3.「業務遂行上の課題があることによる退職」への対処法
精神障がい者の方の「業務遂行上の課題があることによる退職」を防ぎたい場合は、以下のような取り組みや配慮が必要です。
| 「業務遂行上の課題があることによる退職」への対処法 |
| ・個人の能力に合わせて業務を割り当てる
・業務を簡略化するなどして、取り組みやすいようにする ・ジョブコーチなどの支援機関にもサポートに入ってもらう |
個人の能力に合わせた業務を割り当てることで、業務に対する過度なプレッシャーが軽減できるため、心身ともに調子を保って業務に取り組むことができます。
また、業務を簡略化することで取り組みやすくなるケースは多いので、能力に合わせた業務の割り当てと並行して取り組むのが効果的です。
さらに、ジョブコーチなどの支援機関と連携することで、適切な業務の割り当てや業務の簡略化などをサポートしてもらえるため、障がい者雇用における定着率を安定させることができるでしょう。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
5.知的障がい者の方に多い退職理由への対処法

最後に、知的障がい者の方に多い退職理由への対処法を解説します。
知的障がい者の方に多い退職理由上位3つと、その対処法は以下の通りです。
| 退職理由 | 対処法 |
| 業務遂行上の課題があることによる退職 | ・複雑な業務の細分化や、マニュアルを作る
・マニュアルは写真や図を活用して、視覚的な理解を促す ・定期的に業務の進捗をみて適宜フォローや指導を行う |
| 人間関係の悪化による退職 | ・相談役を配置して職場の悩みを相談できる体制を作る
・障がいやコミュニケーションについて社内研修を行う ・チーム活動やイベントを開催し交流できる機会を増やす |
| 障がい・病気による退職 | ・定期的な健康診断や面談を行い、体調の変化に対応する
・休憩できるスペースを作ったり、休みを取りやすくする ・体調によって柔軟に働ける制度を整える |
それでは、具体的な対処法を以下より詳しく解説します。
5-1.「業務遂行上の課題があることによる退職」への対処法
知的障がい者の方の「業務遂行上の課題があることによる退職」を防ぎたい場合は、以下のような取り組みや体制が必要です。
| 「業務遂行上の課題があることによる退職」への対処法 |
| ・複雑な業務はステップを細かく分けたり、具体的なマニュアルや手順書を作る
・手順書や注意事項には写真や図を活用して、視覚的に理解しやすくする ・上司や支援者が定期的に業務の進捗をみて、適切なフォローと指導を行う |
まず、複雑な業務はステップを細かく分けて順を追って進めていくと、今は何をすべきなのかが明確になるため、スムーズに業務を進めることができます。
また、写真や図を入れた視覚的にも理解しやすいマニュアルや手順書を作成しておくと、手順を覚えるのが苦手な方でも安心して作業を進められるでしょう。
さらに、上司や支援者が定期的に業務の進捗を確認して適切なフォローや指導を行うことで、報告・連絡・相談が滞ることなく業務を進めることができます。
5-2.「人間関係の悪化による退職」への対処法
知的障がい者の方の「人間関係の悪化による退職」を防ぎたい場合は、以下のような体制や取り組みが必要です。
| 「人間関係の悪化による退職」への対処法 |
| ・メンターや相談役を配置して、職場の悩みを気軽に相談できる体制を作る
・障がいの特性や適切なコミュニケーションの取り方について社内研修を行う ・障がいのある従業員を含めたチーム活動やイベントを開催し、自然に交流できる機会を増やす |
知的障がいのある方は複数人とのコミュニケーションが苦手な傾向があるため、特定のメンターや相談役を決めて、職場での悩みや困り事を気軽に相談できる体制を作るのが重要です。
また、障がいの特性や適切なコミュニケーションの取り方について社内で理解や情報を共有し、チームでの活動や社内イベントを通して自然に交流できる機会を増やすことことも必要です。
これらの取り組みによって、知的障がいのある従業員が疎外感を感じることなく安心して業務に取り組むことができると考えられます。
5-3.「障がい・病気による退職」への対処法
知的障がい者の方の「障がい・病気のためによる退職」を防ぎたい場合は、以下のような制度や取り組みが必要です。
| 「障がい・病気による退職」への対処法 |
| ・定期的な健康診断や面談を行い、体調の変化に対応する
・体調不良の際に休憩できるスペースを作ったり、休みを取りやすくする ・短時間勤務や在宅勤務など、体調によって柔軟に働ける制度を整える |
まずは、定期的な健康診断や面談を行い体調を安定させることが重要で、もし不調や異変が見つかっても、早めに見つかれば深刻になる前に対応することができます。
また、業務中の急な体調不良があった際に休憩できる専用のスペースを作ったり、休み自体を取りやすくする仕組みを整えることも必要です。
短時間勤務や在宅勤務など、体調や特性によって柔軟に働ける制度を整えることで、安心して働くことができるでしょう。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
6.障がい者雇用の離職率を下げるためには支援機関との連携も重要
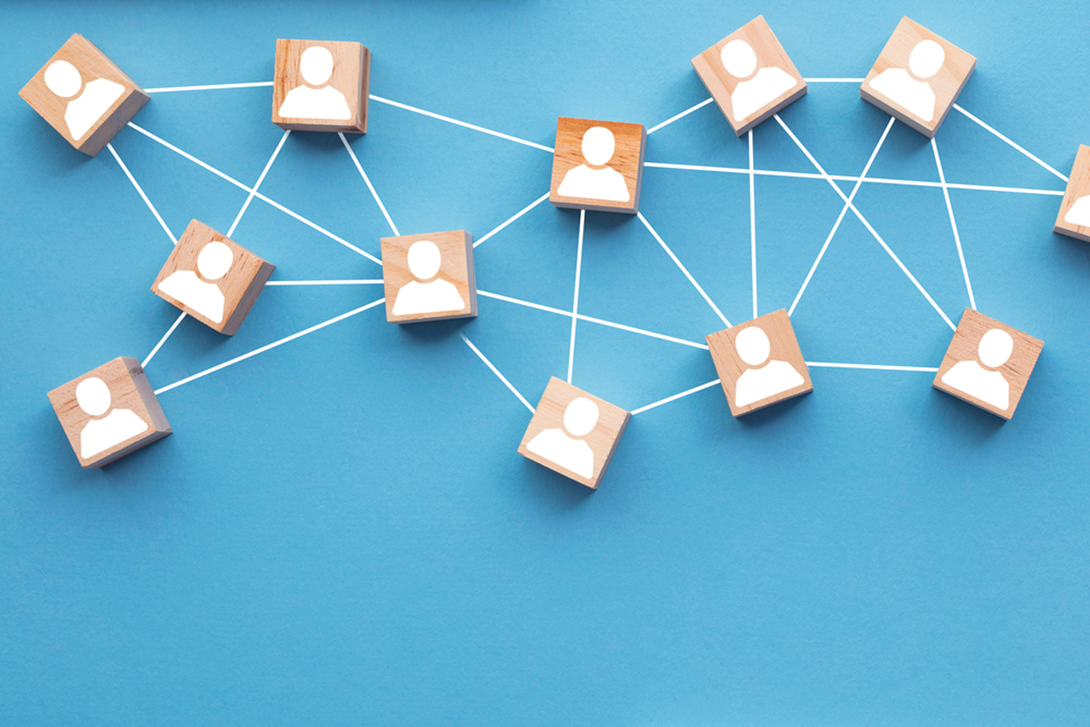
障がい者雇用の離職率を下げるためには、支援機関と連携して体制や仕組みを整えることも重要です。
支援機関と連携することで、専門的な知識を元に多方面からサポートが受けられます。そのため、それぞれの退職理由へ対処する際にも、進め方に迷ったり新たな課題が見つかった場合に相談・解決しやすいでしょう。
障がい者雇用を自社だけで進めることに限界を感じた場合には、支援機関を積極的に利用するのがおすすめです。
例えば、具体的な支援機関と受けられるサポートには、以下のようなところがあります。
| 障害者就業・生活支援センター | 障がいのある方の就業や生活面を一体的にサポートしてくれる |
| 地域障害者職業センター | 障がいのある方を雇用する企業へのアドバイスと支援をしてくれる |
| ハローワーク | 法定雇用率達成のための施策や取り組みをアドバイスしてくれる |
上記のような機関は、企業側・障がいのある方両方に対して、長く安定して働けるようアドバイスをしてくれます。
| 【障がい者雇用における定着課題を解消し、安定した雇用を目指すなら株式会社JSHにお任せください】
株式会社JSHでは農園型障がい者雇用支援サービス「コルディアーレ農園」を通して、障がいのある方と障がい者を雇用したい企業が安定して雇用関係を結べるようなサポートを行っています。
例えば、
・農園スタッフによる業務サポートや送迎サポート ・看護師含む専門スタッフによる定着支援サポート
を提供することで、障がいのある方も安心してのびのびと働ける環境作りを行っています。
障がい者雇用における退職理由の解消し、安定した雇用を実現したいとお考えの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
|
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
7.まとめ
この記事では、「障がい者雇用における障がい種類別の退職理由とその対処法」について解説してきました。
障がい者雇用における退職理由は、以下の通りです。
| 身体障がい者の方に多い退職理由 | 1.障がい・病気のため
2.業務遂行上の課題があったため 3.労働環境が合わないため |
| 精神障がい者の方に多い退職理由 | 1.障がい・病気のため
2.人間関係の悪化 3.業務遂行上の課題あり |
| 知的障がい者の方に多い退職理由 | 1.業務遂行上の課題あり
2.人間関係の悪化 3.障がい・病気のため |
参照:障害者職業総合センター「障害のある求職者の実態等に関する調査研究」
障がい者雇用における離職を防ぐためには、退職理由がどうあれ、企業側が障がいや特性についての理解を深め、その方に合った適切な配慮やサポートを行うことが必要です。
また、「障がい者雇用における退職理由への対処法」は以下の通りです。
| 身体障がい者の退職理由 | 対処法 |
| 障がい・病気による退職 | ・障がいの状況や体調に応じた柔軟な勤務制度を整える
・通院・治療のための休暇を取りやすくする |
| 業務遂行上の課題があることによる退職 | ・必要な機器や補助具を導入して、業務の効率を上げる
・障がいや特性に合わせた業務の割り当てを行う |
| 労働環境が合わないことによる退職 | ・物理的な職場の環境を整える
・相談しやすい人間関係作りをサポートする |
| 精神障がい者の退職理由 | 対処法 |
| 障がい・病気による退職 | ・短時間勤務やフレックス制など勤務時間に柔軟に対応する
・体調不良時には休みが取りやすいようにする ・通院のための休暇や服薬のための時間を設ける |
| 人間関係の悪化による退職 | ・社内研修を通して適切な声掛けやコミュニケーションを把握する
・コミュニケーション支援専門の職員を配置する ・ストレスチェックを受け、その結果に応じて適切な対応を行う |
| 業務遂行上の課題があることによる退職 | ・個人の能力に合わせて業務を割り当てる
・業務を簡略化するなどして、取り組みやすいようにする ・ジョブコーチなど支援機関にもサポートに入ってもらう |
| 知的障がい者の退職理由 | 対処法 |
| 業務遂行上の課題があることによる退職 | ・複雑な業務の細分化や、マニュアルを作る
・マニュアルは写真や図を活用して、視覚的な理解を促す ・定期的に業務の進捗をみて適宜フォローや指導を行う |
| 人間関係の悪化による退職 | ・相談役を配置して職場の悩みを相談できる体制を作る
・障がいやコミュニケーションについて社内研修を行う ・チーム活動やイベントを開催し交流できる機会を増やす |
| 障がい・病気による退職 | ・定期的な健康診断や面談を行い、体調の変化に対応する
・休憩できるスペースを作ったり、休みを取りやすくする ・体調によって柔軟に働ける制度を整える |
この記事が、障がい者雇用における定着率でお悩みのあなたのお役に立つことを願っています。
おすすめ記事
-

詳細を見る
2026年1月16日
【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件
「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大き[...]
法律・制度
-

詳細を見る
2026年1月13日
水耕栽培士®とは|概要からメリット、広がる活躍シーンまで解説
「水耕栽培士®とは、どのような資格なのだろう」 「取得すると、何ができるようになるのだろう[...]
法律・制度
-

詳細を見る
2026年1月13日
ロクイチ報告とは|概要から提出意義、押さえるべき知識まで徹底解説
「ロクイチ報告とはどういうものか知りたい」 「用紙が届いたのだが、必ず提出しなければいけな[...]
法律・制度