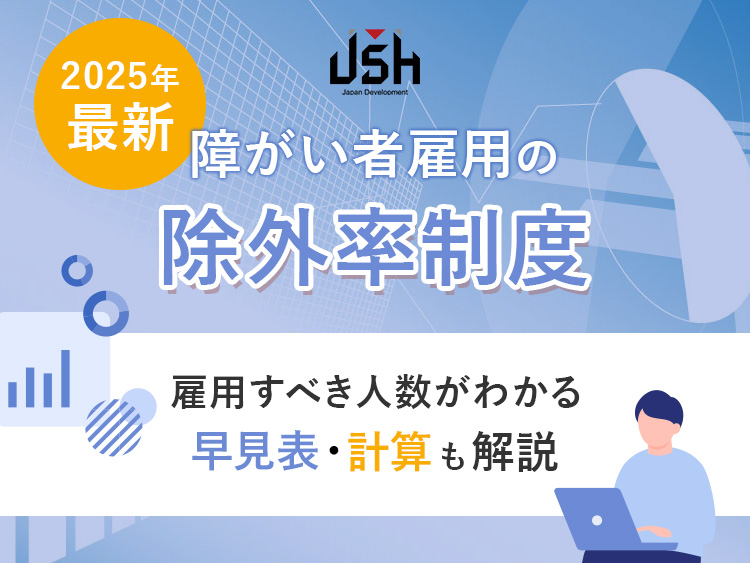コラム詳細
2021/10/26
autorenew2025/04/09
【障がい者雇用の事例】特別支援学校からの定期的な採用で雇用が安定~従業員2,000名規模のメーカーのケース~

法定雇用率の引き上げに際し、改めて障がい者雇用の取り組み方に悩まれている担当者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、障がい者雇用の一つの形として特別支援学校から定期的に採用を行っている大手メーカー様の事例をご紹介します。
特に企業規模が大きく障がい者の必要雇用数が多い企業様や、特別支援学校からの受け入れを検討したい企業様は必見です。
ぜひ参考にご覧ください。
【目次】
1.インタビュー
2.その他の企業の取り組み事例
3.まとめ
1.インタビュー
▼お話を聞かせていただいた方
【企業情報】
業種:メーカー
従業員規模:約2,000名
【担当者様情報】
部署:人事部
障がい者雇用経験年数:10年弱
【現在の障がい者雇用状況】
障がい者の採用ペースは年に1~2名程度で、担当者様ご自身はこれまで約10名ほどの採用に関与。
現在は法定雇用率を達成できているが、今後の段階的な引き上げに向けて
さらに採用を積極的に進める必要性を感じている。
どのような方法で障がい者の方を採用していますか?
基本的に採用経路は2つあり、メインは特別支援学校からの受け入れで、もう1つはハローワークからの紹介です。
ただ、採用人数自体が年に1~2名とそこまで多くないため、ほとんどが特別支援学校からです。
人材紹介エージェントからの営業もよくありますが、すでに間に合っているためお断りしています。
特別支援学校からの受け入れはどのような体制で行っていますか?
特別支援学校からは製造職での採用が多いので、実習で業務を体験してもらってから採用しています。
実習の受け入れは色々な事業部にローテーションで担当してもらっています。
実習を通してお互いの認識のすり合わせをし、実習の現場でOKが出れば採用するという流れです。
特別支援学校から採用するメリットは何ですか?
長年同じ特別支援学校とお付き合いしており、密に連絡を取り合っていて、
非常に良好な関係を築けているのでスムーズにやりとりができています。
また、業務の内容や条件もあらかじめ把握してもらっているので、
ミスマッチが少なく採用決定率が高いことは非常に助かっています。
特別支援学校と比べるとハローワークからの採用は決定率が低い傾向にあります。
応募者のやりたいことと私たちが任せたい業務が食い違ってしまうことが多いですね。
採用は順調とのことですが、職場での「定着」について課題はありますか?
ありがたいことに退職に至るケースはほとんどないのですが、
入社して数年後から休みがちになったり、休職してしまったりするケースはあります。
例えば、基本的に現場では自己判断で業務を進めず、わからないことがあれば上長の判断を仰ぐように伝えています。
しかし業務に慣れてくるうちにそれが緩んできて、自己判断で業務を遂行しミスが出てしまい、
それによって周囲との関係悪化やストレスが蓄積され、結果として休職してしまうケースなどです。
定着については、年に数回行っている現場担当者との面談でよく課題として上がってきます。
その都度障がい者支援センターの担当者に相談するなどして改善に取り組んでいます。
退職を未然に防ぐためにされている取り組みを教えてください。
障がい者支援センターと常に連携しておくことが大切だと考えています。
ですので、入社前に学校を通して障がい者支援センターに登録してもらうことを徹底しています。
また、入社前から受け入れ部署の全員と顔合わせを行うようにしています。
顔合わせのメンバーは、本人・保護者・受け入れ部署の社員・人事担当者・学校・障がい者支援センターです。
その顔合わせの場で、仕事をする場所や内容、福利厚生についてひと通り説明し、
社内の診療所や保険師の制度なども全員に共有しています。
そうすることで周囲の理解や協力も得やすくなり、本人が働きやすい環境を作ることができると考えています。
JSH担当者より
今回のお話から、特別支援学校からの定期的な採用には
以下のようなメリットがあることがわかりました。
・長期的な関係を築くことが出来るため、やりとりがスムーズ
・条件や業務内容のミスマッチがない
・紹介エージェントへの紹介手数料などの費用が削減される
また、退職を未然に防ぐためにされている工夫も非常に参考になるものでした。
2.その他の企業の取り組み事例
今回は特別支援学校からの採用を行っている企業様を取り上げましたが、
当サイトでは、他にも企業の取り組み事例に関するコラムを掲載しています。
こちらもぜひご覧ください。
「障がい者雇用率」企業ランキング|国内TOP企業の事例紹介 【ユニクロ・リクルート・楽天・イオン・トヨタ】
【障がい者雇用の事例】社内カフェをゼロから立ち上げ、法定雇用率を達成!業務切り出しの課題も解決
また、当社の障がい者雇用支援サービス『コルディアーレ農園』をご利用いただき
積極的に障がい者雇用に取り組まれている企業様の事例インタビュー集もございます。
こちらも併せてご覧ください。
3.まとめ
今回ご紹介した事例のように、障がい者雇用には様々な形がありますが、
なかなかうまくいかず悩んでいる担当者様もいらっしゃるかと思います。
株式会社JSHでは、
「募集しても採用につながらない…」
「業務の切り出しがうまくできない…」
「何かとトラブルが多く、定着率が低い…」
といった障がい者雇用に関する様々な課題を持つ企業様に向けて、
採用から定着まで包括的なサポートサービスを提供しています。
障がい者雇用にお悩みの担当者様は、ぜひお問い合わせください。
---------------------------------------------------
▼JSHの障がい者雇用支援サービスについて詳しくはこちら
地方の農園を活用した障がい者雇用支援サービス『コルディアーレ農園』
---------------------------------------------------
おすすめ記事
-
2025年7月7日
autorenew2025/07/07
【2025年最新】特定求職者雇用開発助成金の5つのコースと申請方法
「人手不足ではあるものの、採用や育成にかかるコストがネックになっている。助成金を調べていたところ“特定求職者雇用開発助成金”が目にとまったけれど、活用できるのか?」 「障がいのある方の雇用に活用できる助成金を調べていたら […]
詳細を見る
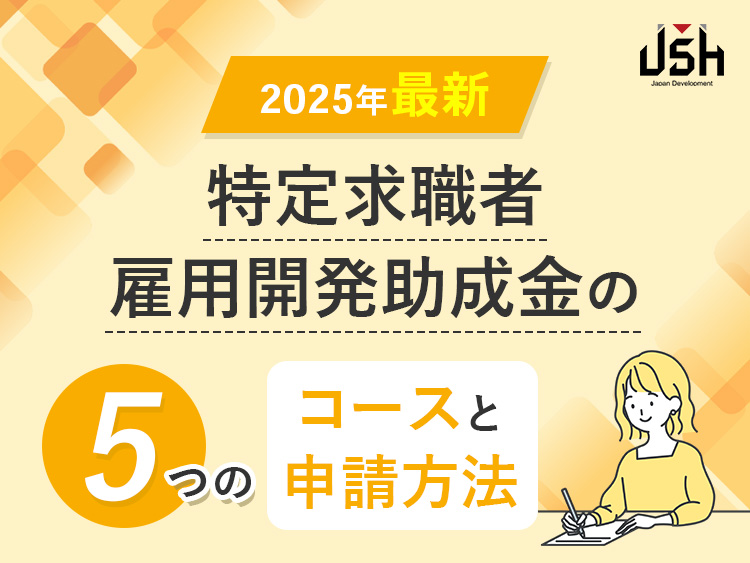
-
2025年7月3日
autorenew2025/07/03
地方創生2.0とは?1.0との違いや基本的な考え方を全解説
「ニュースで”地方創生2.0”という言葉を耳にした。企業として、どうやって携わっていくのか気になる」 「2025年から国が地方創生2.0に取り組むようだけど、企業としては何かするべき?どのようなことが求められるの?」 昨 […]
詳細を見る
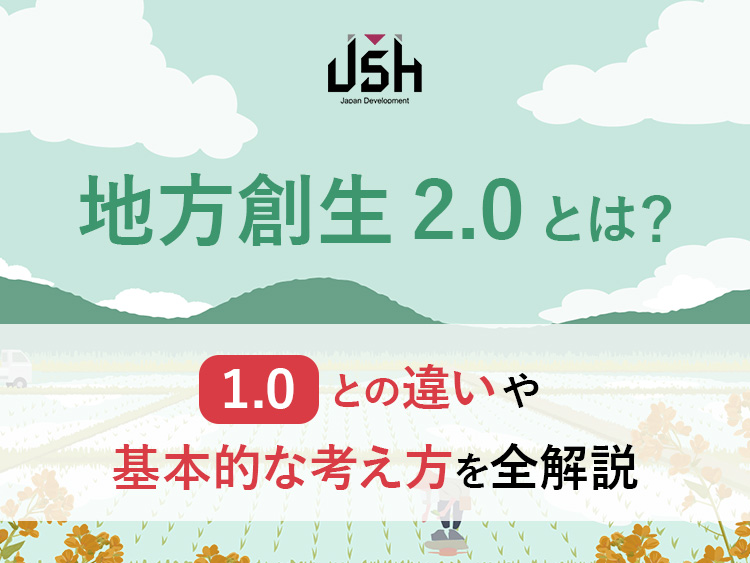
-
2025年7月3日
autorenew2025/07/03
【2025年最新】障がい者雇用の除外率制度|雇用すべき人数がわかる早見表・計算も解説
「障がい者雇用における除外率の一覧を見たい」 「除外率の一覧を確認したうえで、確実に法定雇用率の達成を目指したい」 2025年4月より、除外率が適用される業種や適用率が変更されたこともあり、このようにお考えなのではないで […]
詳細を見る