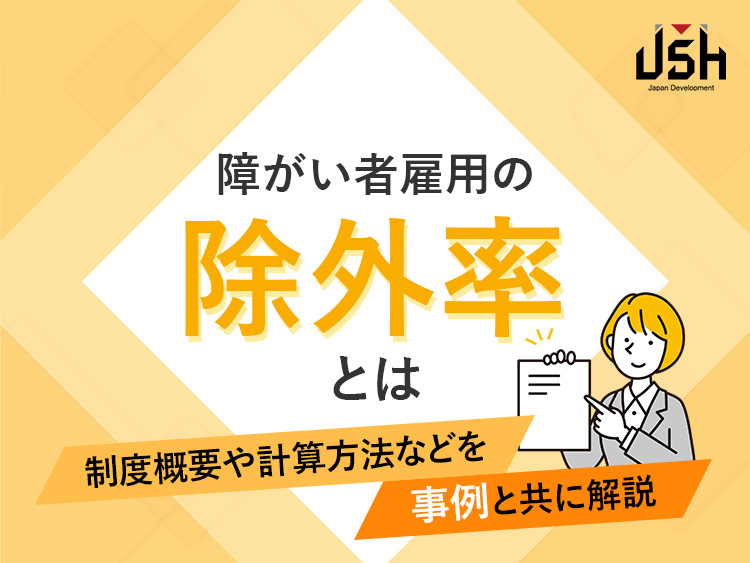コラム詳細
2021/10/26
autorenew2025/04/14
【障がい者雇用の事例】社内カフェをゼロから立ち上げ、法定雇用率を達成!業務切り出しの課題も解決
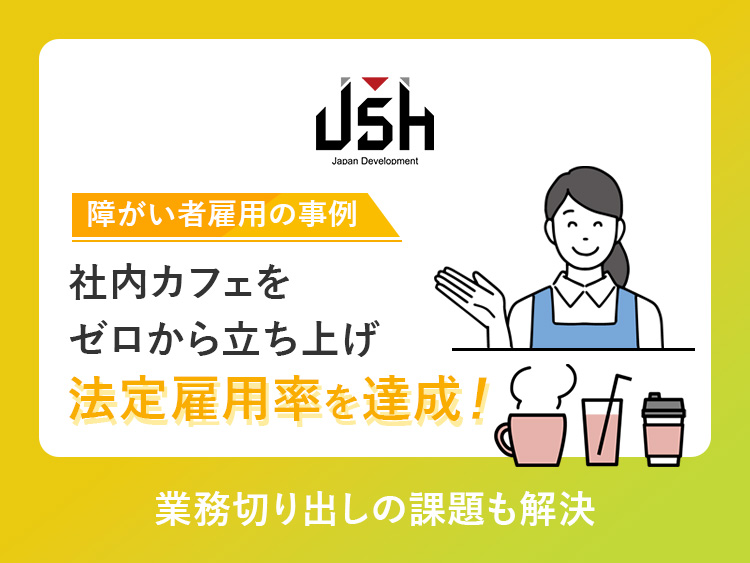
法定雇用率の引き上げに際し、改めて障がい者雇用の今後の進め方に不安や悩みを抱えられている担当者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、障がい者雇用の一つの形として社内にカフェを立ち上げ、法定雇用率を達成したIT企業様の事例をご紹介します。
新たな「働く場所」を創出したユニークな事例ですので、ぜひ参考にご覧くださいませ。
【目次】
1.インタビュー
2.その他の企業の取り組み事例
3.まとめ
1.インタビュー
▼お話を聞かせていただいた方
【企業情報】
業種:IT
従業員規模:1,000以上
【担当者様情報】
障がい者雇用経験年数:10年以上(前職含む)
【当時の障がい者雇用状況】
法定雇用率を達成するためには、オフィスでの雇用の受け入れに限界を感じていた
社内カフェを立ち上げたきっかけは何でしたか?
弊社では、障がい者雇用状況が常に不安定な状態でした。
法定雇用率を著しく下回っていた訳ではなかったので行政指導等はありませんでしたが、
数値を達成できずに納付金を収めたこともありました。
弊社はIT企業なので、基本的にオフィス内での受け入れを行っています。
障がい者社員の中にはITエンジニアとしてスキルを持っており、
ソフトウェアを使ったモデルの作成やデザインなどを行っている者もいますが、
エンジニア職ではない人たちに切り出す業務には限界が出てきました。
そんな時、社内向けのカフェを運営し、そこで障がい者を雇用する取り組みを行っている企業があることを知り、
検討し始めたのがきっかけです。
カフェの立ち上げはどのような流れで進めましたか?
実はカフェを立ち上げることになったものの、飲食業界で経験がある人は社内にいませんでした。
障がい者の募集をかけた際も、飲食業界での経験がある人からの応募はありませんでした。
全くノウハウがない状態でしたが、
同じような取り組みをしている企業さんから情報収集をしながらなんとか立ち上げを進めていきました。
その後、外部から1名飲食店経験者を雇用することができ、スーパーバイザーの役割を担ってもらいました。
立ち上げ開始から半年間ほどで徐々に形になっていきましたね。
苦労したこととして印象に残っているのは、保健関連の法規制ですね。
社内向けのカフェだったので、そこまで厳格ではなかったのですが、保健関連の手続きは複雑で大変だったことを覚えています。
どのように運営を行っていますか?
ビジネス目的の事業ではないので、売り上げは特に気にしていません。
障がい者社員が気持ちよく働けているか、コミュニケーションがしっかり取れているか
ということを重視しながら運営を行っています。
そのためにカフェのスタッフ全体で週単位のミーティング行い、個別面談も月に1回ずつ必ず設定するようにしています。
中にはサポートスタッフがついている障がい者社員もいるので、
その場合はサポートスタッフにも半年に1回くらいのペースで面談の時間をもらっています。
障がい者雇用を行う上で工夫していることを教えてください。
基本的に障がい者社員が働く場所としてカフェを立ち上げましたが、
「障がい者のための仕事」と区分しすぎることなく、疎外感を感じさせないアサインが必要だと感じます。
業務をきちんと割り振らずに放置してしまったり、
「周辺的な仕事をやってくれればそれで良い」といった姿勢を取ってしまったりすれば、すぐに限界が来てしまいます。
障がい者の社員にも「自分たちの仕事が社員の役に立っている」「世の中の役に立っている」と
実感しながら働いてもらえるような仕事をアサインしていくことが大切だと思っています。
JSH担当者より
「業務の切り出し」は障がい者雇用における代表的な課題の一つですが、
この企業様は新たに「働く場所」を創出することによってその課題を解決されました。
既存の業務を無理に切り出そうとせず、別の形を検討してみるという選択肢を持ってみるのも良いかもしれません。
2.その他の企業の取り組み事例
今回は社内カフェを立ち上げた企業様の事例を取り上げましたが、
当サイトでは、他にも企業の取り組み事例に関するコラムを掲載しています。
こちらもぜひご覧ください。
「障がい者雇用率」企業ランキング|国内TOP企業の事例紹介 【ユニクロ・リクルート・楽天・イオン・トヨタ】
【障がい者雇用の事例】特別支援学校からの定期的な採用で雇用が安定~従業員2,000名規模のメーカーのケース~/
また、当社の障がい者雇用支援サービス『コルディアーレ農園』をご利用いただき
積極的に障がい者雇用に取り組まれている企業様の事例インタビュー集もございます。
こちらも併せてご覧ください。
3.まとめ
今回ご紹介した事例のように、障がい者雇用には様々な形がありますが、
なかなかうまくいかず悩んでいる担当者様もいらっしゃるかと思います。
株式会社JSHでは、
「募集しても採用につながらない…」
「業務の切り出しがうまくできない…」
「何かとトラブルが多く、定着率が低い…」
といった障がい者雇用に関する様々な課題を持つ企業様に向けて、
採用から定着まで包括的なサポートサービスを提供しています。
障がい者雇用にお悩みの担当者様は、ぜひお問い合わせください。
---------------------------------------------------
▼JSHの障がい者雇用支援サービスについて詳しくはこちら
地方の農園を活用した障がい者雇用支援サービス『コルディアーレ農園』
---------------------------------------------------
おすすめ記事
-
2025年6月16日
autorenew2025/06/16
【双極性障がいの方の一般就労】仕事探しから面接までを流れに沿って解説
「双極性障がいがある場合の就職活動ってどうするの?」 「就職したいけど、働き続けられるか不安」 双極性障がいがある人に、このような不安を抱えている人は少なくありません。 「社会復帰したい!」という強い気持ちがあっても、「 […]
詳細を見る
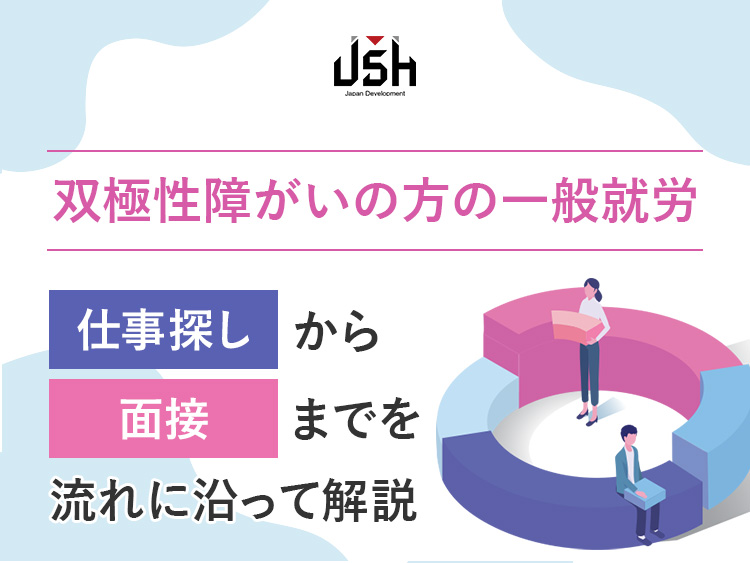
-
2025年6月5日
autorenew2025/06/05
てんかん症状がある方の障がい者雇用の実態|企業事例や採用前後の対応も解説
「てんかんの方の障がい者雇用は一般的なのだろうか?実態が知りたい。」 「てんかんの方に自社で働いてもらえるのだろうか?」 障がい者雇用の担当としてこのようにお悩みや疑問がある中で、情報を集めたくてこの記事に辿り着いたので […]
詳細を見る
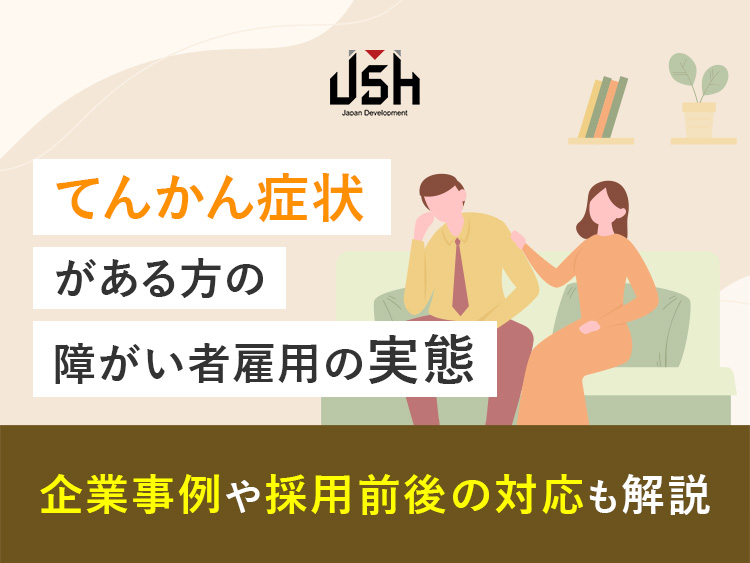
-
2025年5月23日
autorenew2025/05/23
障がい者雇用の除外率とは│制度概要や計算方法などを事例と共に解説
「障がい者雇用について調べていたら、除外率という言葉が出てきたが、どういう意味なのだろうか」 「除外率は自社にも適用されるのか知りたい」 障がい者雇用を本格的に推進するにあたり、除外率について理解を深めたいとお考えではあ […]
詳細を見る